小5特別活動「6年生に感謝の気持ちを伝える会をしよう」指導アイデア

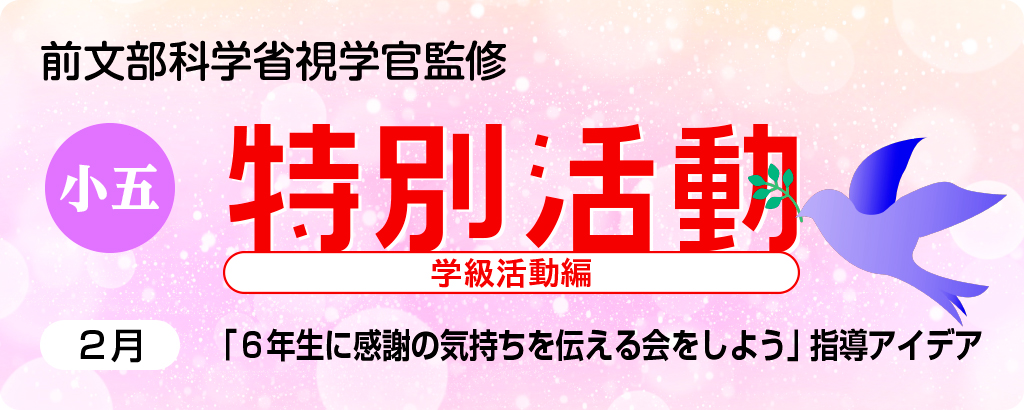
前文部科学省視学官監修による、小5特別活動の指導アイデアです。2月は、<学級活動⑴「6年生に感謝の気持ちを伝える会をしよう」>を紹介します。
学級の枠を越えて児童会との関連を図り、学級会を展開することで、高学年としてのチームワークや実践力、進級に向けての意欲を高めることを目指します。
執筆/滋賀県公立小学校教諭・永尾皓司
監修/前文部科学省視学官 帝京大学教育学部教授・安部恭子
滋賀県特別活動部会顧問 元滋賀県公立小学校校長・鈴木靖彦
目次
年間執筆計画
4月 学級活動⑴ 5年〇組の係を決めよう
5月 学級活動⑴ 学級の歌をつくろう
6月 学級活動⑵ ウ 地震のときの正しい行動の仕方
7月 学級活動⑴ 1学期がんばった会をしよう
9月 学級活動⑵ イ 互いのよさの認識
10月 学級活動⑴ 5年〇組の運動会のめあてを決めよう
11月 学級活動⑶ ウ 目指す自分になるための自主学習
12月 学級活動⑴ 来年の1年生と交流会をしよう
1月 学級活動⑶ ア 最高学年に向けて
2月 学級活動⑴ 6年生に感謝の気持ちを伝える会をしよう
3月 学級活動⑴ 5年〇組の一年を振り返る会をしよう
1.1月の学級活動⑶「最高学年に向けて」との関連
2月になると、学校では卒業式に向けて準備が始まります。多くの学校ではその1つとして5年生が主体となって、「6年生を送る会」や「6年生を送る週間」などを計画すると思います。児童会の代表委員会からの提案があり、学年の出し物の工夫や役割等について各クラスで話し合い、下学年の子供たちみんなで心を込めて準備していきます。5年生の子供たちにとっては、6年生に替わって学校のリーダーを引き継いでいく大切な時期でもあります。
前回の学級活動⑶アの題材「最高学年に向けて」で、6年生になることを楽しみにしながらも、少し不安があった5年〇組の子供たちが、最高学年になるために6年生からアドバイスをもらい、一人一人が将来に向けて実現できそうな努力目標を意思決定するとともに、これまでお世話になった6年生に感謝の思いをもつ実践例を紹介しました。今回はその続きとなるもので、学級活動⑴の「6年生に感謝の気持ちを伝える会をしよう」を紹介します。

