「受益者負担」と「設置者負担」とは?【知っておきたい教育用語】
日本国憲法では、第26条で「義務教育はこれを無償とする」と定めています。義務教育は、小学校と中学校の9年間ですから、この間に国、地方公共団体(自治体)が設置する学校での教育に係る必要は、原則、無償となります。しかし、教科書ではない教材・教具や、移動教室・修学旅行などの費用については一般的には保護者が負担しています。学校を設置する者とその学校で公的な教育制度のもとに利益を享受する子ども(家庭)が負担する費用についての基本的な考えを見ていきましょう。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
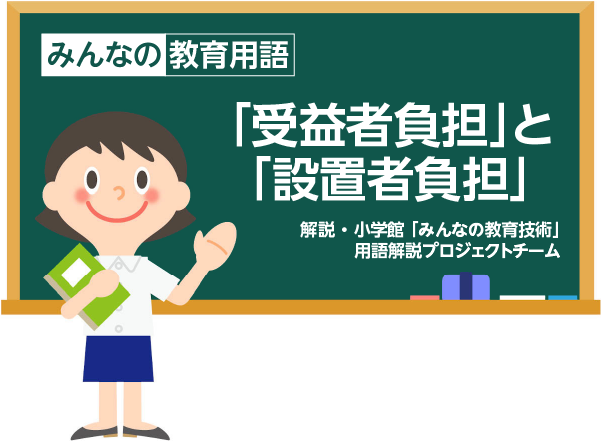
目次
「受益者負担」と「設置者負担」とは
【「受益者負担」と「設置者負担」】
学校教育における「受益者負担」と「設置者負担」の考え方は、教育制度の財政における負担の分担方法を説明するもの。教育を受ける側の「受益者」と、学校を設置・運営する側の「設置者」との間で、どのように費用を分け合うかを示している。
「受益者負担」の考えは、教育を受けることによって得られる利益(知識やスキルなど)を享受するのは子どもたち自身であり、その負担もある程度は必要だという考えに基づいています。簡単にいえば、教育を受ける人がその費用を支払うということです。一方、「設置者負担」については、教育は社会全体の利益であり、全ての子どもに教育の機会が平等に提供されることが社会的な責任であるという考えに基づいています。
このことは、公立学校と私立学校とでは異なります。
公立学校
●受益者負担
授業料は基本的に無料。
制服代や教材費、学校行事費などの教育費の一部に関しては、家庭が負担。
●設置者負担
学校の建設費や教員の給与、教育活動に必要な設備費などの多くの費用は、国や自治体が税金を使って負担。
私立学校
●受益者負担
授業料を含めた学費としての教材費や学校行事費、施設費などを家庭が負担。
教育費用の負担には、「受益者負担」と「設置者負担」のバランスが重要です。すべてを設置者が負担する「完全な無償教育」となると、社会的負担が大きくなります。行政施策としてはできるだけ受益者負担を少なくすることをめざしつつ、教育にかかる費用の一部を家庭が負担する形をとっているのが現状です。
「受益者負担」と「設置者負担」の法的根拠
日本国憲法の第26条では、教育の権利と義務について規定し、教育を受けることが国民の基本的な権利であることを明確にしています。この規定によって、教育は無償で提供されるべきであるという原則が確立されています。
教育基本法では、教育は「平等に提供されるべき」であり、「すべての国民が平等に教育を受ける機会を持つべき」という立場が強調されています。この観点から、義務教育(小・中学校)の段階では受益者負担が過度に重くならないようにするための法的な枠組みが必要とされています。さらに、学校教育法とその関連法では、義務教育は公立の場合、基本的に無償で提供することとし、受益者負担が原則として制限されています。
公立学校における受益者負担に関する具体的な規定は、主に自治体の条例や教育委員会の規則に基づいています。各自治体は、その財政状況や教育施策に応じて、教材費、校外学習費用などについての負担割合を決定しています。

