インタビュー/工藤勇一さん|「働き方改革」を進めるためのポイントは「主体性」と「当事者性」【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは⑩】
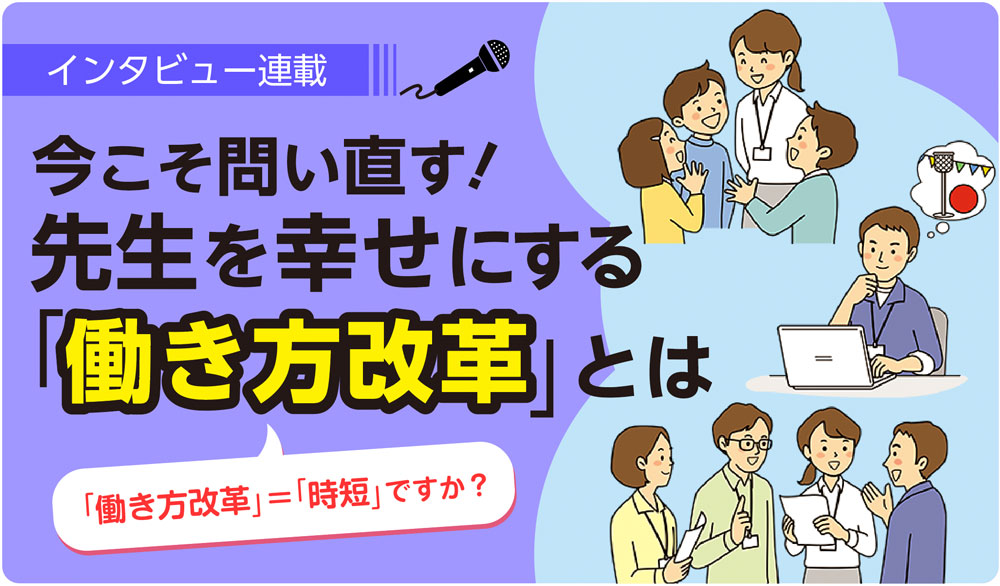
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えてきたこの連載も10回目を迎え、いよいよ最終回です。今回は教育アドバイザーの工藤勇一先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
工藤勇一(くどう・ゆういち)
1960年山形県鶴岡市生まれ。東京理科大学理学部応用数学科卒。公立学校教員、東京都教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長等を経て、2014年4月より千代田区立麹町中学校校長、2020年4月より学校法人堀井学園 横浜創英中学校・高等学校校長として、教育改革を行ってきた。内閣官房教育再生実行会議委員、内閣府規制改革推進会議専門委員、群馬県非認知教育専門家委員会委員等、公職を歴任。2024年4月より教育アドバイザーとして全国で講演活動を行う。『学校の「当たり前」をやめた。生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革』(時事通信社、2018年)、『校長の力-学校が変わらない理由、変わる秘訣』(中央公論新社、2024年)など著書多数。 
目次
求められるのは、もっと本質的な「働き方改革」
全国の学校で行われている「働き方改革」を見ると、ひたすら対症療法を行っているように感じます。もちろん、一つ一つの問題を解決していくことは大切ですが、もっと本質的な問題を解決していかなければなりません。
最大の問題は、教員が教育の一番大切なことを目的に働いていないことです。教育において一番大事なことは「自律した子供」を育てていくことだと私は考えます。自律。かみくだけば、主体性と当事者性、これこそが「生きる力」です。特にこれからの時代、社会はますます変化が激しくなり、10年後を予測することさえ困難です。企業が一生面倒を見てくれる時代は終わりました。子供たちがそんな世の中を自分の力で生きていくには、自分の力で考え行動するための主体性と当事者性が不可欠です。
学習指導要領では「生きる力」を育てるには子供たちに知徳体をバランスよく身に付けさせる必要があるとしていますが、各学校は手段である知徳体を育てることに躍起になり、「生きる力」そのものである主体性と当事者性を失わせています。
不登校の児童生徒が34万人の日本。他国とは何が違うのか?
皆さんもご存じの通り、日本では今、不登校の児童生徒が約34万人います。これに対して、欧米には日本のような不登校という教育問題は存在しません。「不登校」という概念すらありません。不登校問題はアジア型とも言われ、テストの点数を競う受験制度を基盤とした高い学業プレッシャーと、さらには集団行動を基盤とする同調圧力の強い風土がある日本や韓国、中国などに共通に見られる現象です。
なぜ欧米に不登校問題がないのかと言えば、そもそも教育に対する考え方が日本とは全く違うからです。
例えば、アメリカの場合、そもそも就学義務がありません。つまり、必ずしも保護者は子供を学校へ行かせなくてもいい、ということです。子供にどういう教育を受けさせるかは保護者が決めることであり、その責任は保護者が負っています。公立の学校へ行かせてもいいし、近くの教会で学ばせてもいいのです。アメリカは州ごとに法律が違うのですが、50州全部でホームスクーリングが認められています。つまり、自宅で学んでもいいのです。
このように、アメリカに不登校という概念がないのは、学び方を子供自身や保護者が自由に選べるからです。「学ぶのは自分である」という意識、つまり、主体性をなくさないような教育システムがつくられています。
日本人の感覚だと、「そんなに自由で将来進学や就職は大丈夫なのか?」と思うかもしれませんが、基本的にアメリカには高校受験がないですし、大学受験の仕組みも日本とは全く違います。日本のように「複数の科目の知識を暗記して、入学試験で1点でも多く点数を取った者が大学に入れる」という制度ではないのです。高校での成績、論文や面接、推薦状などを基に合否が決まります。日本で言えば、AO入試や総合型選抜入試、つまり、人物評価です。
日本では中学受験も、高校受験もあります。小学校に入学するときには、国が決めたこの小学校へ行きなさいと指定され、この学年では学習指導要領の中のこれを学びなさいと決められていて、そこから外れた子供を問題視します。欧米の国々から見たら、日本の教育システムはかなり変わっているのです。
日本と同様に韓国も不登校問題に苦しんでいますが、日本や韓国の教育と欧米の教育との根本的な違いは、どんな教育を受けるかを決めるのが学ぶ側であるかどうかです。言い換えれば、子供自身の主体性と当事者性を育む教育かどうかです。これ以上不登校の児童生徒を増やさないためにも、日本は教育に対する根本的な考え方を見直していかなくてはなりません。そしてそれこそが本当の「働き方改革」にもつながっていくものだと私は思います。

