生徒同士が対話しながら、最適解を見付けていく過程を意識 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #14】
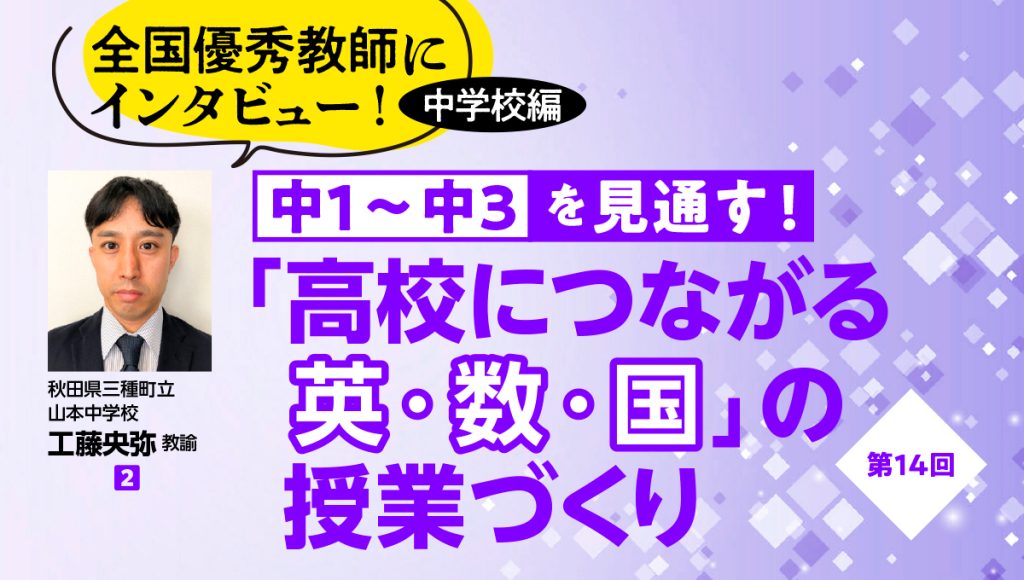
前回から、国語の全国学力・学習状況調査の結果が長年にわたって良好な秋田県で、秋田県の能代山本教育研究会国語部会の研修部長を務めている、三種町立山本中学校の工藤央弥教諭に国語の授業づくりについて聞いていきます。今回は前回紹介したような授業の裏側にある、工藤教諭の授業づくりの考え方について紹介します。

目次
付加価値のある豊かさも国語のもつ良さ
工藤教諭は、単元や授業をつくっていくにあたり、まず学習指導要領を確認し、その力を育むことを大事にしているとしながらも、それ以上に意識しているのは、生徒同士が対話しながら、最適解を見付けていく過程だと話します。
「国語を担当していると、『国語は答えがないから、どんなふうに勉強したらよいか分からない』と、生徒や保護者から言われることがあります。だからこそ私は、教材文を読んだ後、それぞれの意見を出し合いながら、対話を通して生徒たちが納得できるような、『最適解』をめざしていくような授業づくりをしていきたいと思っています。
そのように対話を通して生徒たちが考えて、自分たちの『最適解』がもてたところで、『どんなところに注目したから、そんなふうに読めたのかな?』『どういう読み方をしたから、その答えが見付けられたかな?』と考えて整理し、(再現性のある)力として生徒たちが身に付けていけるようにしたいと考えているのです。
前回紹介した『盆土産』(光村図書)のような文学的文章であれば、生徒一人一人の生活環境によって捉え方に違いが出てくると思います。実際に生活環境が変わっていくことによって、『お盆に親戚で集まり、食事をした』という生徒も少なくなっているのではないでしょうか。その違いやズレを出し合いながら、答えを最適解へと磨いていく過程を大事にしたいと思っているのです。

また『お盆』が生活経験から離れていっているからこそ、おもしろい部分もあります。作品の設定などについて読みながら考えていったときに、『なぜ、えびフライをお土産にしたのかな?』と言うと、最初は多くの生徒が『食べたことのない家族に食べさせたかったか』と考えているわけですが、次第に『お盆の時期だ』『もしかしたら、おじいさんやお母さんの分も入っているから6本だったんじゃないのかな』という意見が出てきたときに、生徒たちが『ああ〜っ』という顔をして、『そうだよな』という声が出てくるのです。
そんなところから話をしていく中で、前回触れたように『設定は大事だな』ということから改めて、『お盆という文化』に話が広がっていきます。そのように、学ぶ過程を通した付加価値がたくさんあるからこそ、『盆土産』は好きな作品でもあるのですが、同時にそのような付加価値のある豊かさも『国語』という教科がもつ良さだと思っています。
もちろん、学習指導要領の資質・能力は大事だと思っていますし、その育成をめざして授業をつくっているわけです。ただし、その力を付けるのだから教えてしまえばよいというのではなく、その学習の過程を豊かなものにしたいのです。

