子どもの「やりたい!」を大切に。理科の楽しさを伝える授業づくりとは 【理科の壺】

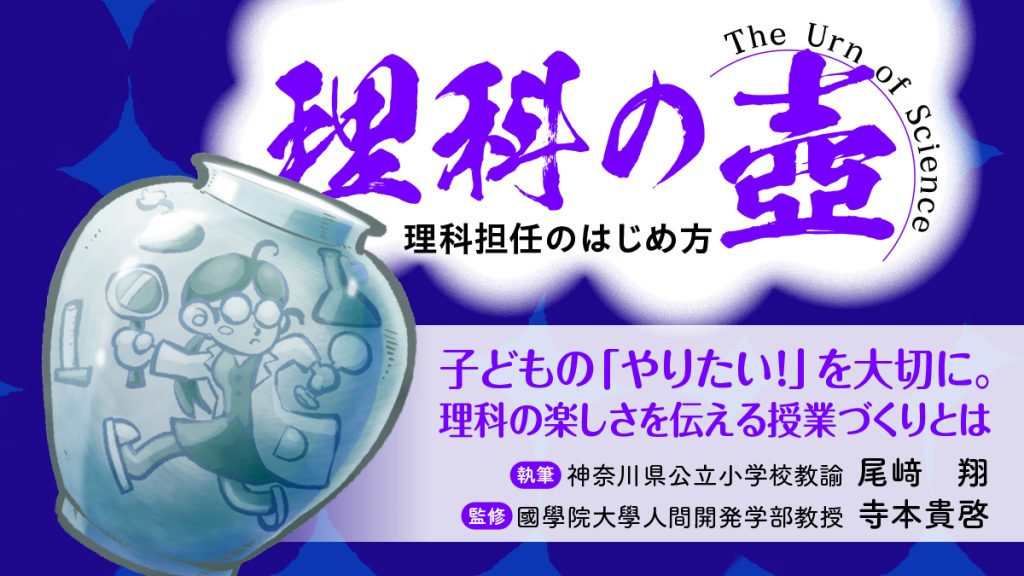
理科の授業の楽しさを伝えるには、先生自身がその楽しさを知っていると、その気持ちが子どもたちに伝わります。先生が理科を好きでない理由として、難しい、時間がかけられないなどあるかと思います。表面的に授業を流すだけでは「知識を伝達し、一通り経験をさせている」だけで、理科のおもしろさを感じて意欲的に取り組むことには繋がりません。まずは、何でもいいので1つ深くやってみるということから取り組んでみてはどうでしょうか。今回は、子どもの意欲という視点で引き出し方について考えています。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・尾﨑 翔
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.まずは教師が理科を好きになってほしい
「理科の授業」と聞くと実験準備や教材作成など、授業をするための壁が多くあるように思います。理科が好きならまだしも、嫌いな場合は「負担が大きい大変な教科」という印象を持たれている方も多いと思います。筆者の周りでも、理科の研究に熱心な方は、ほぼ全員が理科の楽しさを知っている先生です。だからこそ、子どもに理科を教えるにあたっては、まずは教師が理科を好きになってほしいと思います。
理科を好きになるきっかけは、日常生活の中にあります。自分の経験では、小学校3年のとある冬の夜中、たまたま目が覚めて窓の外を見てみると満天の星が広がっていました。そこから星に興味を持ち、不思議を探っていくうちに理科の事が大好きになりました。
小学校の理科はたくさんの観察や実験を通して、身の回りの不思議を探っていく教科だと思います。2年生までの生活科とつなげて、授業の計画を立てていくことも大切です。今回は経験がない中ではありますが、子どもたちが自主的に学習活動に取り組むことができるような手立てをご紹介できればと思います。
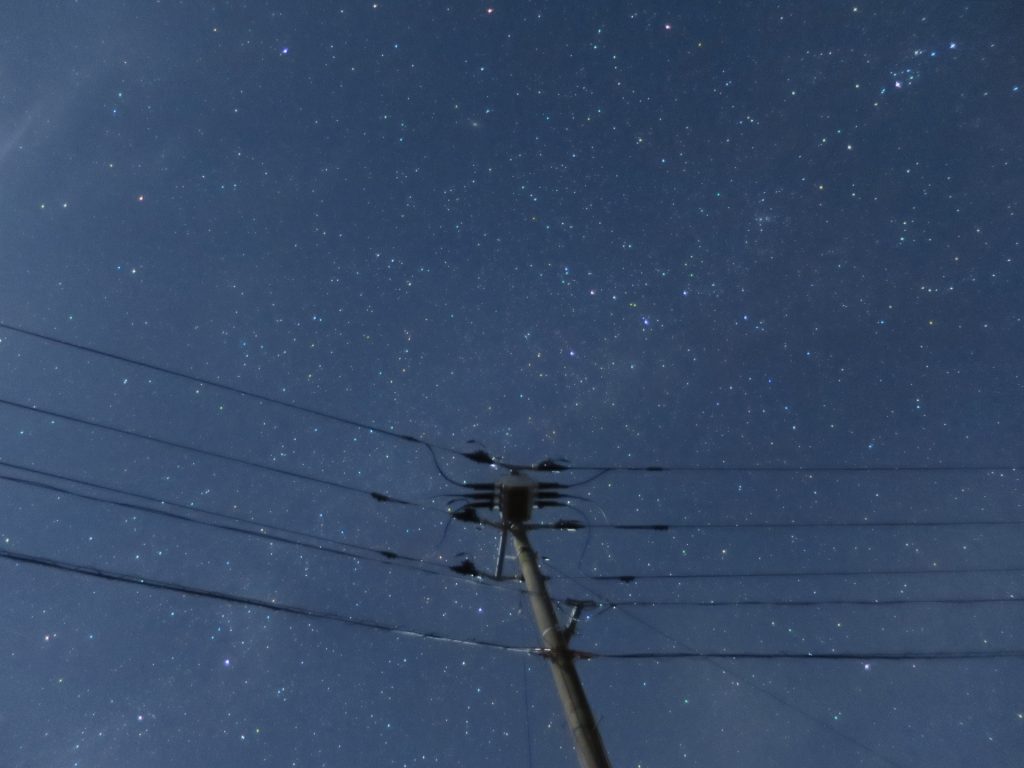
2.子どもの「やりたい!」を引き出すには?
子どもたちの理科に対する気持ちを高めるために、子どもたちの持つ 「不思議」 を引き出してあげることがとても大切だと考えています。興味のあることと無いことでは調べる意欲に差が出てきてしまうのは当然のことです。
子どもたち自らが「解決したい!」「実験して確かめてみたい!」と思わなければ、ただの知識の教え込みや活動で終わってしまうため、単元の計画を作成する際には、なにを導入で扱い、どのように発問を行うかを一番に考えます。導入で子どもたちが「えっ?!」「なんでだろう?」と思う体験をさせてあげることができれば、調べる意義を子どもたちが感じるのではないでしょうか。

