日本を離れ派遣教師として子どもを教えるということ~ドイツ・デュッセルドルフより~
世界には在外教育施設派遣教師として、異国の日本人学校で教壇に立つ先生方が数多くいます。なぜ日本人学校の教師に? 赴任先の教育現場はどんな感じ? 日本の教育事情との違いは? ここでは、現地で活躍している先生の日々の様子をお伝えします。今回登場するのは、ドイツ連邦共和国・デュッセルドルフで子どもたちに指導をしている杉山貴彦先生。海外で教職の研さんを積みたいと考えているあなたへ、先輩教師からのメッセージです。
執筆/デュッセルドルフ日本人学校教諭・杉山貴彦
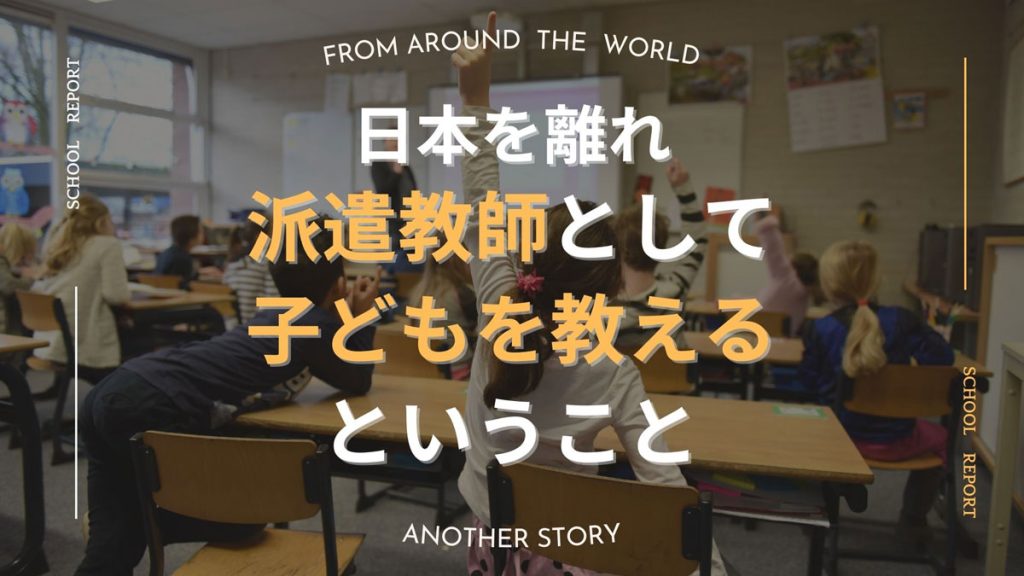
目次
日常が『当たり前』ではないと気づかされたコロナ禍
私が在外教育施設への勤務を志望したのは2022年度でした。それ以前の2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、通常の学校運営が困難となりました。それ以降「ウィズコロナ」「ソーシャルディスタンス」「アフターコロナ」といったテーマが教育現場でも話題になり、変革が求められました。
例えば、学校へ行けない状況が続くなかで、オンライン学習の重要性が高まりました。家庭にいながらも教育活動をどのように進めるか、そして環境整備を進める必要がありました。一方で、タブレット学習そのものが目的化しないよう、対面でのオフライン学習とのバランスを考慮することも大切でした。この時期、三密を避けながら教科ごとの授業の進め方やオンライン学習の進め方、従来の教育活動との調整など、多くの課題がありました。
以上のように2020~2022年度の間に、教育活動は大きく変化しました。私は「当たり前に存在するものは決して当たり前ではなく、変化に対応する力が必要だ」と強く感じるようになりました。社会の大きな変化を目の当たりにし、その変化に対応するためには、現状から飛び出して挑戦することが重要だと考えました。
そこで、長年興味を持っていた日本人学校での勤務を決意しました。海外での勤務は誰にでもできることではありません。まず、所属する学校長の推薦を得て、所属する自治体や文部科学省の面接に合格する必要があります。日々の業務と並行して日本人学校への準備を進めるのは非常に大変でしたが、勤務していた学校の教職員の皆様は応援してくれたり、手助けしてくれたりしたことが大きな支えになりました。
日本との違いを肌で感じる異文化交流と学び
現在、ドイツのデュッセルドルフ日本人学校で勤務しています。先進国の一つであるドイツでは、生活に困ることはほとんどありませんが、言語の壁を感じることは多々あります。ですが、学校職員や近所にはドイツ語と日本語を話せる人たちがいます。その方々に助けてもらいながら、新天地での生活を楽しんでいます。新しい環境での挑戦は、関わる人々の温かさを実感する機会でもあり、人とのつながりの大切さを改めて認識しています。
デュッセルドルフ日本人学校の1日のスケジュールは、日本の学校とほとんど変わりませんが、いくつか異なる点があります。その一つが、現地理解教育の一環として「ドイツ語」と「英語」の学習が小学部1年生から行われることです。日本では小学校3年生から外国語学習が始まりますが、こちらでは2年早く始まります。デュッセルドルフでは英語が広く通じるため、グローバルスタンダードの言語として英語学習にも力を入れています。
また、現地校や姉妹校、地域住民との交流、さらには現地の公共施設での学習なども通じて、学校外で自然と外国語学習ができる点も日本人学校ならではの特徴です。例えば、小学2年生の活動の一例として、デュッセルドルフのサッカーチーム「Fortuna Düsseldorf(フォルトゥナ デュッセルドルフ)」との交流があります。ドイツのサッカーは世界的に人気があり、この「Fortuna Düsseldorf」はとくに地域の方々に絶大な支持を受けているチームです。試合の平均観客数は40,000人に達し、日本代表の田中碧選手(2024年8月イギリスサッカークラブへ移籍)やアペルカンプ真大選手、女子チームの天野実咲選手なども所属しています。日本人選手の在籍という点もまた、子どもたちにとって非常に魅力的な活動となります。
具体的な内容としては、生活科の学習とドイツ文化に触れる機会を兼ねたスタジアム見学や、選手の練習を見学、交流が行われます。スタジアム見学で子どもたちにとって一番印象的だったのは、エキサイトしたサポーターを隔離する独房のような場所があるということでした。ここで気持ちを静めさせたり、最悪の場合、警察に引き渡したりするそうです。サッカーに対する熱い気持ちが、文化の違いを感じさせてくれます。そのほかにも選手の練習の様子を見学したり、サインが書かれた下敷きをもらったりするなど、様々な交流を通じて、「Fortuna Düsseldorf」が多くのサポーターに支えられていることを学べる貴重な機会となります。また、事前にチームのスタッフによる出前授業が行われるので、当日の見学ではさらに意欲も高まります。


もう一つの例として、デュッセルドルフで毎年2月に行われるカーニバルが挙げられます。ドイツのカーニバルは春の訪れを祝うとともに、カトリック教会が定めたイースター前の断食期間を前に、おいしいものを食べたり、歌ったりしながら楽しむお祭りです。毎年11月11日に始まり、灰の水曜日(教会暦でイースター前46日めの水曜日のこと)に終わる「第5の季節」とも呼ばれる特別な行事です。
カーニバルでは豪華な山車(フロート)が市内を練り歩き、カラフルな衣装や仮装をした人々が音楽に合わせて踊りながら、観客にキャンディや小物を投げます。日本文化の発信をテーマに、日本人学校の小学2年生も、保護者の協力を得て法被を着てパレードに参加しました。また、現地校で行われるカーニバルのお祭りにも参加し、全員が仮装して出し物やダンスを楽しみました。子どもたちは英語やドイツ語で現地の子どもたちと交流しますが、「言葉が通じなくてもジェスチャーや表情で伝わる」と活動の振り返りで話す子も多く、異文化交流の貴重な体験を積んでいます。



