<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #8 徳島県石井町立石井小学校5年3組②<後編>

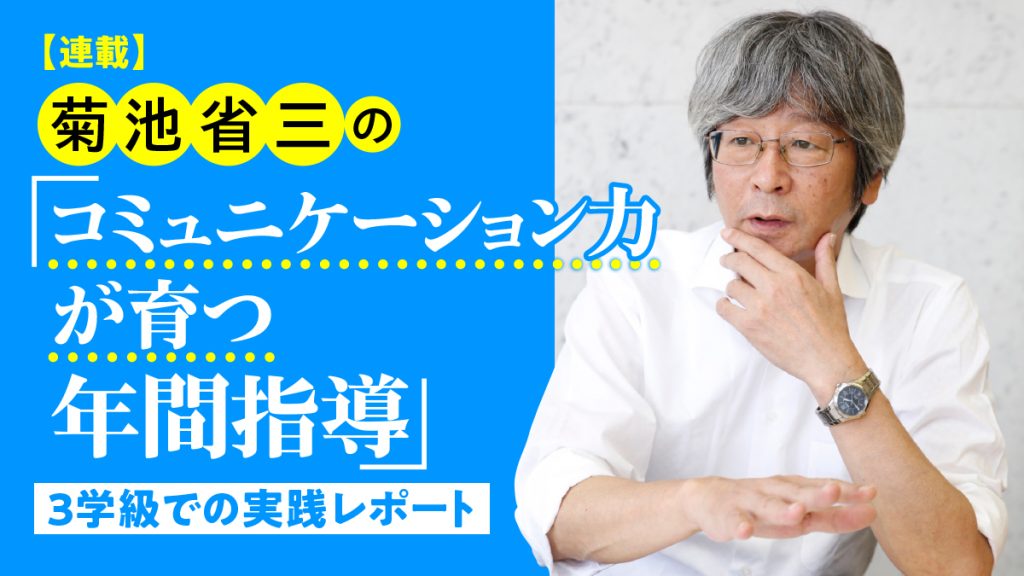
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載です。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。
今回は、徳島の堀井学級(5年生)における、7月上旬の授業レポートの完結編です。

目次
納得解の話し合いで、言葉のキャッチボールを楽しむ
桃太郎にお供するイヌ、キジ、サル。一番活躍したのは誰か。
イヌ派に続いて、キジ派の子供たちが発表した。
●キジは飛ぶから攻撃されにくい
●キジがいなかったら、門を開けられず、弓で撃たれていた
●キジが飛んで上から見なければ鬼の様子もわからない
●キジがくちばしで鬼の手を刺した、と本に書いてあったような気がするので、桃太郎の手助けになったはず
●キジが飛んで敵の周囲をひきつけることができるので、その間に桃太郎が攻撃できる
反論するために1分間の作戦タイム。
<キジ派への反論>
●キジは飛んでいても、活躍したとは限らない
この意見に対して、キジ派の子が黒板に貼られたイラストをもとに反論した。
●鬼が桃太郎に「やめてください」と言っている間に、キジが飛んで爪で引っかけば鬼は全滅する。イヌとサルは、桃太郎の隣に座っているだけで何もしていない
<再びキジ派への反論>
●イヌもジャンプしたら、鬼の目を爪で引っかくことができる
●昨日、○○さんが偶然、風呂から出て桃太郎を読んだが、その本にはサルが崖を登って門を開けたと書いてあったが、どう思うか
「なるほど。昔の話だから、本によって微妙に違うと思ったんですね」と菊池先生が補足した。
●キジは目をひきつけるだけで、攻撃力はイヌより低い。イヌは攻撃手段が2つあるが、キジは1つしかない
<キジ派からの再反論>
●キジの攻撃力は本来、引っかくのではなくつつくことだから、鬼の頭をつつけば一撃で勝てる
●攻撃手段は少なくても、役に立てる。
●イヌの嗅覚は何の役に立つのか
●この質問は「誰が一番活躍したか」なので、キジに一番役割があった
最後の意見を言った男子に対し、菊池先生が、
「例えば?」
と尋ねると、その子が、
「注意を引きつける、目を引っかいて目を見えなくするなどです」
と続けた。菊池先生が、
「攻撃力と作戦力を見たら、キジが一番、という考え方なんだね?」
と確かめると、男子がうなずいた。
●攻撃手段は1つしかないと言うが、まず飛べるのは強いし、引っかくことができるし、つつくこともできるので、攻撃手段は1つではない
イヌ派の女子が思わず、
「イヌも足が速いので、注意を引きつけてその間に桃太郎が攻撃するのもありだと思います」
と反論した。
![]()
納得解の話し合いで盛り上がる教室の子供たちは、絶対解の話し合いでも盛り上がります。
絶対解の話し合いは答えが決まっているので、理由付けも基本は1つです。そのため、話し合いの中では自分らしさが発揮しにくく、やりとりの面白さを楽しむ要素も少なくなります。
一方、納得解の話し合いは、理由付けによって、どちらにも勝機があります。子供たちの議論に重要性、深刻性はありませんが、事実をどう解釈するかによって立場が変わるからです。
納得解の話し合いでは言葉のキャッチボールを楽しむことができるので、話し合いの“平等性”が高いと言えます。お互いに考え合って深め合い、平等性を築きながら、みんなが納得する答えに近付いていくのです。
今回の話し合いの中で、「門を開けたのはキジかサルか」について議論する場面がありました。
確か、本には、サルが門を開けたと記述されていたはずです。
しかし、この場面では、誰が開けたかを問うのではなく、「口承だから、いろいろな伝わり方をしてきたんだね」というコメントに留めました。活発な話し合いを遮断したくなかったからです。
自分なりに考えて理由をひねり出したり、友達と意見を戦わせたり…。話し合いそのものを楽しんだ子供たちは、答えが決まっている絶対解の話し合いでも、自分で考え、相手の意見を聞くことを楽しめるようになります。
的外れな意見も温かい笑いに包まれる
次に、サル派の子供たちが意見を発表した。
●サルは手足が4本使えるので、石を持って鬼にぶつけた
●人間は元々サルだったというし、サルは頭がいい
●サルが門を開けないことには、そもそも鬼退治はできない
一人の男子が、黒板に貼られた桃太郎のイラストを見ながら、
「桃太郎の横で、サルだけが鬼がやられている姿を真顔で見ているので、殺しに慣れている」
と話すと、隣の女子が、
「あれ(イラストの絵)はイメージだから!!」
とツッコミを入れ、みんなが大爆笑。
イヌ派の女子が反論しかけると、菊池先生が、
「イヌ派、もっとこっち(中央)来いっ」
と移動を促した。3グループの距離が近くなったところで、サルへの反論開始。
●サルは登る力と知恵があるだけで、攻撃できない
●本によって(門を開けたという)内容は違うが、それはどうなのか
「本によって記述が違うこともあるので、イヌ、キジ、サルの本来の特徴で見ていかないとだめだということだね」と菊池先生がアドバイスした。
サル派への反論は続く。
●人間も昔はサルだったというが、人間にはその頃の記憶はないし、サルは理性や感情がないので、単に引っかくだけではないか
すると、サル派の男子が、
「サルも怒ればキーキー鳴くから、感情はある」
と反論すると、イヌ派から、
「人間はキーキー言わないし」
と返され、男子が悔しまぎれに、
「(人間の)子供はキーキー言いますぅ」と反論した。
●手が使えるから石を投げられると言うが、キジも石をつかんで投げれば一緒
●サルは頭がいいと言うが、分かっても言葉をしゃべれないから、桃太郎に指示できない
サル派の男子が、
「しゃべれなくてもキャーキャー言うので大丈夫です」
と反論すると、
「それは、イヌもキジも同じ」
とみんなから突っ込まれた。
![]()
話し合いに熱中した結果、定義から外れた意見が出てきました。
「サルは殺しに慣れている」
「サルはキーキー言う」
このような的外れな意見も出てきました。もちろん、この男子はふざけて発言したわけではありません。むしろ、サル派が勝つために、無理矢理にでも理由をひねり出したのです。
そんな男子に対し、「またかよ」という冷たい空気ではなく、「それはイラストのイメージだから」と突っ込みを入れるなどして、温かい笑いが教室にあふれました。
このように、それぞれがどんな意見でも認め合えるような温かい関係性は、話し合いの土台です。このような土台がなければ、話し合いは絶対にうまくいきません。
いい土台の基本は、「どれだけ聞き合えるか」です。
教師は、多様な子供同士をつなぐ視点を常に持つ必要があります。

