<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #7 徳島県石井町立石井小学校5年3組②<前編>

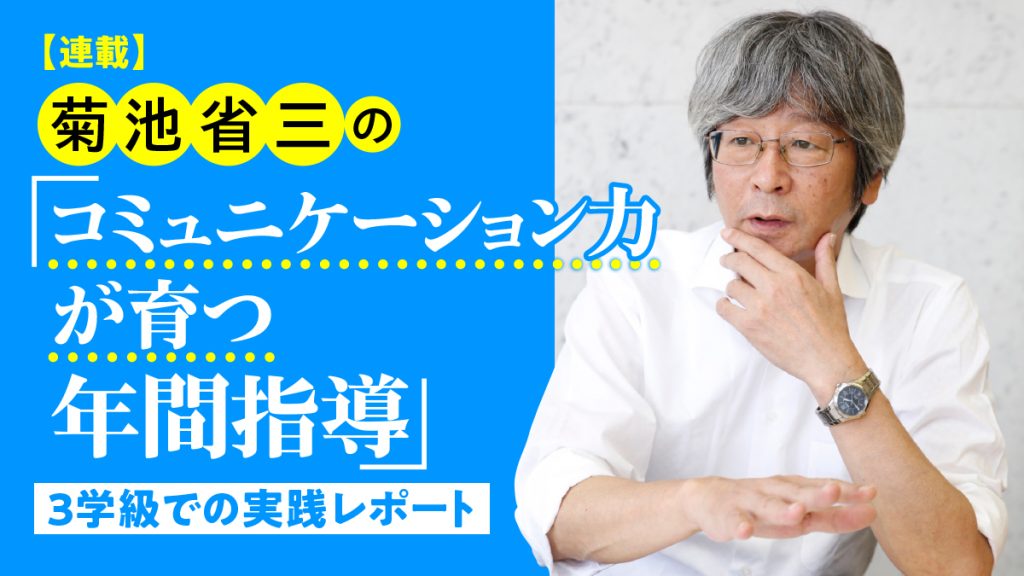
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載です。3学級の担任は、徳島の堀井悠平先生、高知の小笠原由衣先生、千葉の植本京介先生。 今回からは、徳島の堀井学級における、7月上旬の授業レポートです。菊池実践における話し合い指導のステップや、具体的な声かけのあり方が示される必読回です。

目次
担任・堀井悠平先生より、学級の現状報告
4月の菊池先生の授業を通して、「みんなで学び合う」という雰囲気をどうつくっていくか、についてより深く考えるようになりました。
教師が引っぱらないと発言しない、発言しても理由はなかなか話せない子が多かったので、まずは簡単な理由でも発言できるようにしたいと感じました。
同時に、聞き合う雰囲気をつくっていかなければと思いました。子供たちが私の話を聞くとき、なかなか視線が集まらない、話半分で聞き流しているような雰囲気を感じていたからです。
一方、私の指導のあり方も見直しました。1年後のゴールイメージに引っぱられ過ぎて、今の教室の実態からかけ離れ、子供たちがついていけない状況もあったためです。子供をしっかり見ていない証拠だと実感しました。
菊池先生の授業後、毎朝の会で、3人の子供たちのよいところを紹介し、10日間で30人全員をほめるようにしました。
授業では「書いたら発表をセットにする」ことを大切にし、発問→自分の考えを書く→列指名や班指名等での発言を通して全体の前で話す、という機会を確保していきました。
道徳や国語、社会科、学級会で話し合いの授業を取り入れ、基本形を体感させながら、それぞれの話し合いにねらいをもって取り組んでいきました。子供たちは話し合いを楽しむようになり、次第に活発な意見のやりとりができるようになっていきました。
話し合いが軌道に乗ってきたのは、6月中旬頃。社会科の話し合いで第二反駁まで噛み合った話し合いを体験したこと、それらが成立したこと、新しい考えや価値を発見できたことが大きな自信になり、みんなで楽しもうとする雰囲気が教室に広がったように思います。
学級活動では、時期を見計らいながら、フリートークや質問タイム、ほめ言葉のシャワーを取り入れました。お互いを知り、子供同士の関係を築いていくためです。
少しずつ教室の空気が温まってきましたが、一方で、友達の陰口や無視に悩む子からの相談もありました。そこで、いじめの授業を行い、“自分事” として考えることを目指しました。
いじめの授業の後から、少しずつ教室の雰囲気が変わってきました。
●少し負荷をかけるような指導が入るようになった
●授業をしていて呼応している様子を感じるようになった
●子供たちの表情が柔らかくなってきた
タックマンモデル(社会学者・タックマンによる集団の成長段階を示したモデル)に照らし合わせるなら、ようやく「準備期」から「形成期」に入って来たかなと感じています。
菊池先生による飛び込み授業レポート
「2時間目に堀井先生が黒板の左端に書いた2文字を覚えていて言える人?」
菊池先生が尋ねると、何人もが手を挙げ、指名された子が、
「『理由』です」
と答えると、みんなから大きな拍手が送られた。
「そうですね。理由というのは、無理してでもひねり出すもの。それが自己開示です。そして、出し合った意見をお互いに理解し合うから、白熱する教室に変わっていくんですね」
と菊池先生が説明すると、これから始まる授業にみんな期待いっぱいの表情になった。

