児童の評価にぜひ導入したい「形成的評価」。その課題と解決策とは?

「形成的評価」は、学習者の学びをより深く理解し、個々のニーズに合わせた指導を行う上でとても大切な評価方法です。しかし、その実施にあたっては様々な課題がある、ということも知っておきたいですね。ここでは現代的な「形成的評価」の課題を4つに絞ってより深く掘り下げ、具体的な解決策を考えていくことで、「形成的評価」の有効性を最大限に引き出していくことにつなげたいです。
【本記事は3回シリーズの第2回です】
前回の記事はこちら
個別最適な学びのために! あなたも「形成的評価」を指導に導入しませんか?
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
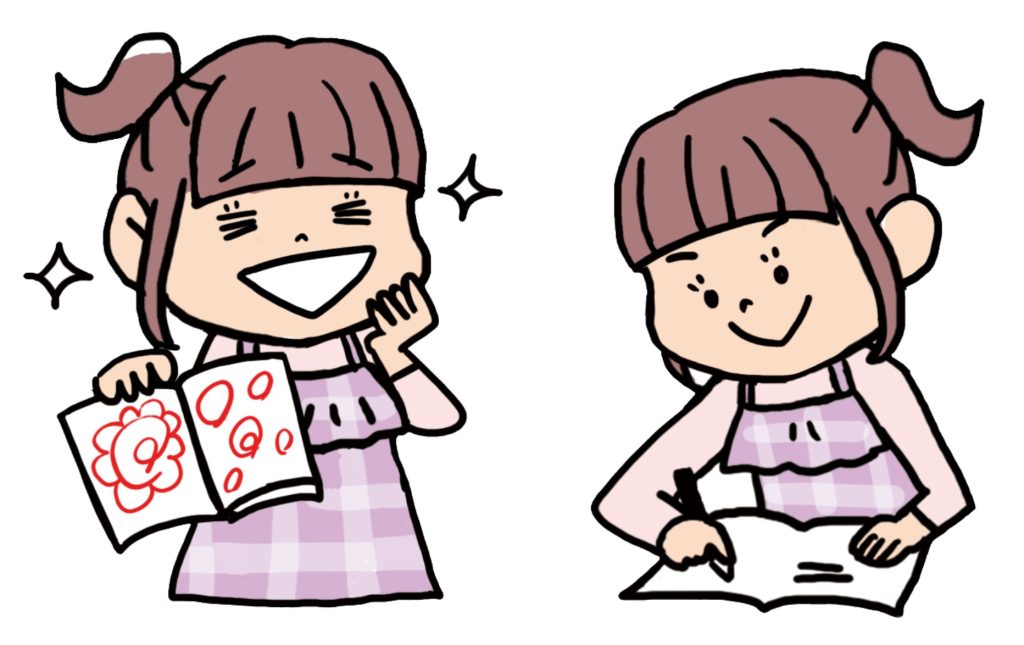
目次
<課題1> 教員の負担が増加する
「形成的評価」は、従来のテスト中心の評価と異なり、授業中の観察、学習過程の記録、個別指導など、多角的な視点からの評価が求められます。これらの活動は、教員の既存の業務に加わるため、時間的、精神的な負担が大きくなることがあります。特に、多様な学習者に対応するためには、個々の学習状況を詳細に把握し、適切なフィードバックを提供する必要があり、教員の負担はさらに増大していきます。
解決策
① 評価ツールの積極的な活用を!
後にも述べますが、形成的評価は児童一人一人の個別最適な学びのための評価であるからこそ、それぞれの児童の評価規準が客観的かつ明確である必要があります。観察シートやチェックリスト、自己評価シート、ルーブリックなどの評価を効率化するためのツールを積極的に活用していきましょう。また、デジタルツールを活用することで、データの収集・分析がかなり楽になります。教員の負担を軽減することも可能です。
② 教員間の協働体制をつくろう!
チームティーチングなどで教員同士が協力し合うことで評価の負担を分散させます。これによって、お互いの学びを深めることができます。また、新任教員へのメンタリングや経験豊富な教員による講座などの研修の実施も有効です。
③ 学校全体でサポートしよう!
学校全体で形成的評価の重要性を共有し、教員が安心して取り組める環境を整備することが大切です。例えば、校内研修を充実させることで、評価に関する情報の共有や教員の働き方改革などを推進していきましょう。
<課題2> 評価基準の明確化が難しい
「形成的評価」では、知識・技能だけでなく、思考力や表現力、協働性などの多様な能力を評価する必要があります。児童一人一人を注意深く見るために、ともすれば授業者の主観が入ってしまうおそれがあります。また、評価するときの基準が曖昧だと、評価の客観性や信頼性が損なわれることがあります。そして、学習者や保護者からの不信感につながる可能性もあります。基準の明確化は避けては通れない課題です。
解決策
① 具体的な評価基準の設定をしよう!
各学習目標に対して、具体的な行動や成果を示す評価基準を設定します。例えば、「問題解決能力の育成」という評価目標に対して、「教室全員で考える問題に対して、複数の解決策を考え、その根拠を説明できる」といった具体的な評価基準を設定していきましょう。
② ルーブリックを活用しよう!
ルーブリックは、評価基準を具体的に示す評価表で、学習者の到達度を視覚的に捉えやすくしていきます。ルーブリックを作成する際には、教員間で十分な議論を行い、共通理解を図ることが重要です。
③ ポートフォリオを活用しよう!
ポートフォリオは、学習者の成長過程を記録するものであり、評価基準の明確化に役立ちます。学習者自身が自分の成長を振り返り、自己評価を行うことも促します。生活科や総合的な学習の時間ではよく取り入れる手法ですが、ほかの教科でもやっていきましょう。

