【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第65回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その6) ─国語科教科書の教材提示論─

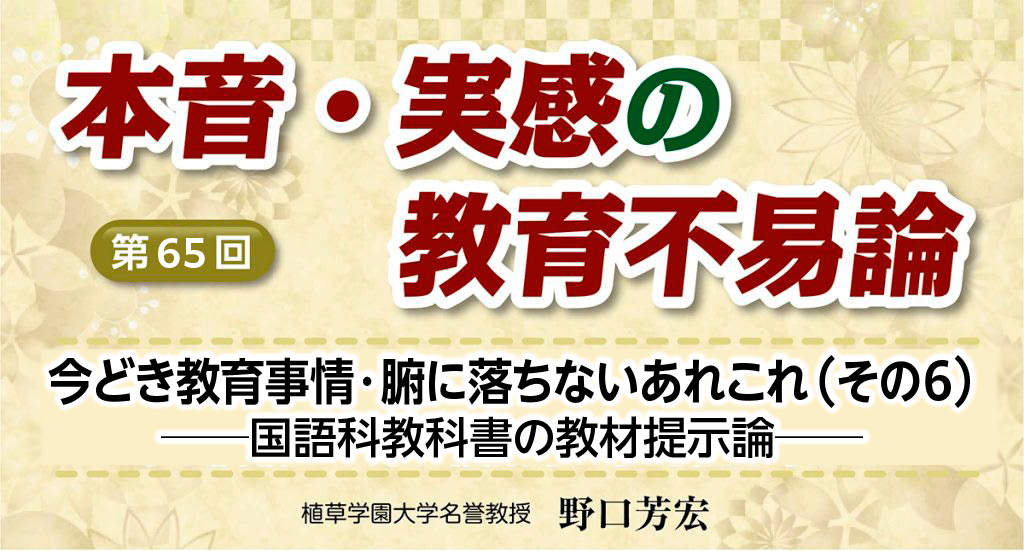
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、60年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る好評連載。今回のテーマは、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その6)─国語科教科書の教材提示論─】です。全ての国語科の先生方、必読です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
8、学年別漢字配当の意義
学年別漢字配当は、やはり必要である。その必要性は、学力の達成度の評価にとって不可欠だからなのだ。三年生の子供の漢字の読み書きの学力の測定、評価上、その指導範囲、習得範囲を定めておかなければ、当然混乱が生ずる。三年生には、これだけは必ず教え、習得させなければならないという範囲は特定されるべきだ。
但し、それはあくまでも、学力の評価上のことであって、それ以上の漢字を教えてはならないということではない。配当表の範囲を越えて、例えば子供の名前や姓を漢字で書いてはいけないということではないのである。つまり、学年別配当漢字の配当はあくまでも「最低限」あるいは、「最小限」を示したものであって、それ以上の学力をつけてはならないという禁止ではないのである。この点の誤解がかなり広範囲に亘って共有されているようだ。
教科書の教材の表記も頑なにこれが守られている。先に私が例示した『言葉と作法』という幼児に広く用いられている教材文は、漢字配当表には全く囚われていない。幼児教育では、学力の評価はないのでその点の束縛は考慮しなくてよいからだ。
幼児教育の世界でこのようにしてかなりの漢字が読めるようにしてやっても、小学校に入ると平仮名ばかりの表記教材になるので、むしろ一部の子供達にとっては、育てられた学力を活かせないという笑えない悲劇が生じることがある。
学年別漢字配当の本来の意義を知れば、一年生の時からかなりの漢字を子供に提示してもよい訳だが、それは当分の間不可能であろう。残念ながら、当分の間漢字の読字力強化は望めまい。
漢字の読字力は、心ある私立の保育園や幼稚園、子ども園などに期待するしかない。子供にとっては十分に学べる事実が実証されているのに、その成果が生かされないのは残念という他はない。
9、古典の振り仮名提示の功罪
次のような事例は、教科書出版社にほぼ共通している(カッコ内はルビ)。
終日(ひねもす)、 菜(な)、 いつぱい(いっぱい)、 づつ(ずつ)、
俳句(はいく)、 山路(やまじ)、 草(ぐさ)、 閑か(しず)、 蟬(せみ)、
このような教材のルビ付き提示は昔から当然のように行われてきたことで、格別の問題は生じてはいない。当然のことのように考えられて疑う者もいない。
しかし、仮にルビがなかったらどういうことになるか。当然子供の大方は読めなかろう。そこで、子供はどうするか。
A、何もしない。
B、親に聞く。
C、友達や先生に聞く。
D、自分で調べる。辞書を引く。
Aは残念ながら論外だが、現実の子供の大方はこの類であろう。こういう子供にはルビが有効かもしれないが、予習もしないだろうから積極的なルビの有効性、生産性はさほど期待できまい。
B、Cの子供は「聞く」「問う」という意味で積極的・意欲的である。「問う」というのは「解」を欲するからであって、当然「解」を期待する。また、この場合のやりとりは勉強に関することであり、望ましいコミュニケーションでもある。そういう生産性のあるやりとりを「ルビなし」が促し、刺激することになる。ここでの「読めない」「分からない」という一時的な「困り感」はマイナスではなく、プラスのそれである。私はこれを常々「分からなさの自覚」と呼んで学習のレディネスとして重視している。Dは最も望ましい。このような「自学」「自力解決」に挑む子供を育てることが教育の理想であり、目的でもある。
このように考えて、私は小学校の国語教科書は原則的に「ルビなし」にすべきだと考えているのだが、いかがか。その実現は程遠いことだろうから、私は自分の子供向け著書ではルビなしにしている。このことについては前回で述べたので参照して貰えれば有難い。ルビなしによって生ずるマイナスや不満は一件もないことも前回稿で述べた。
身近に尋ねるような人がいない場合も多く考えられるので、近頃はルビを振ることも取り入れている。現実的な実状を考えれば、それも一策だと言えようからだ。だが。その場合には「左ルビ」を採用している。一般に縦書きのルビは右側に振るが、これだと縦書きの場合には漢字よりも先にルビが目に入る。それで用が足りれば漢字は軽く見る程度で読み進めることになるだろう。それでは漢字の読字力はつかない。
左ルビにすれば、まず漢字が目に入り、何と読むのかという「分からなさの自覚」に基づいて左に目を移す。そこにはルビがある。短い時間だが、ここには「分かりたい」「知りたい」という「自覚」との出合いがある。
横書きの場合には「下ルビ」にする。分かり方のメカニズムは縦書きの場合と同じである。私の考えに賛同する仲間と共に、幼児向けの絵本や、音読読本を作っているのだが、幸いにして理解者、賛同者が少しずつだが増えているようで、嬉しいことだ。


