宿題の出し方とは【教科担任制 最前線!! 算数専科を楽しもう】⑦
関連タグ
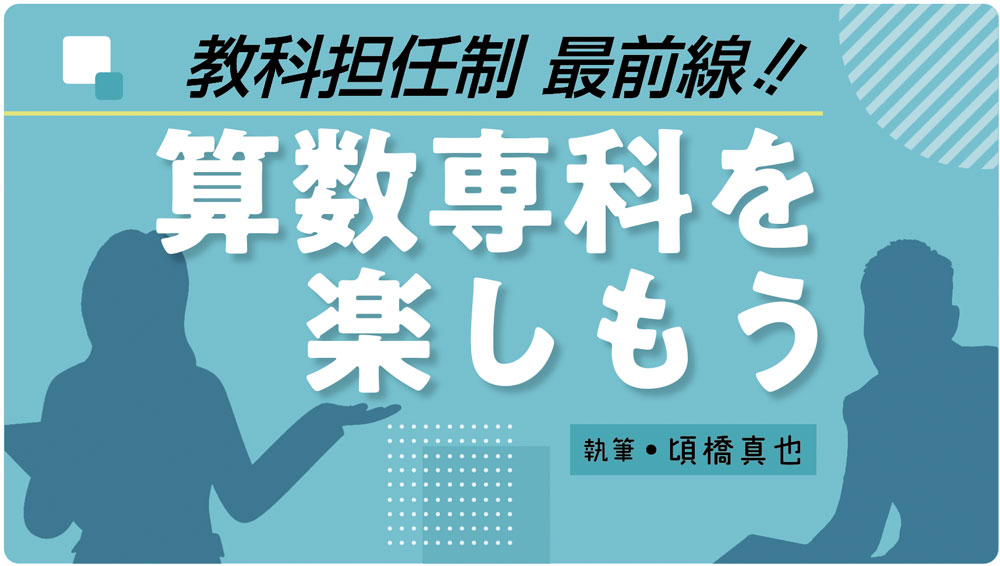
今回は、頃橋先生が様々な方法を試した上で行き着いた、宿題の出し方について紹介します。この方法は算数専科以外でも活用できる方法です。教務主任も兼務しているという点から、働き方改革的な視点の内容もお届けします。特に、オンライン上で連絡帳を共同編集するというのは、1人1台端末があるからこその方法です。ぜひ試してみてください。
執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也
目次
宿題準備も算数専科の仕事の1つ
みなさんの学校では宿題を出していますか? 昨今宿題に関しては、出す必要性も含めて話題になっていますが、私の勤めている学校では、出しています。現在も多くの小学校で宿題を出していると思います。
では、算数の宿題は、どのくらいの頻度で出していますか? おそらく毎日出している学校が多いのではないでしょうか。量に差はあるものの、家庭学習を定着させるという目的で国語や算数などの宿題を毎日出している先生は多いと思います。
私は現在、教科担任制の算数専科として、3~6年生のすべての算数の授業コマ(各学年週5コマ×4学年=全20コマ)を担当しています。つまり、毎日1つ算数の宿題を全学年分準備する必要があるのです。
算数専科として、毎日4つのクラスの宿題の準備をして、各クラスに知らせることの難しさを4月当初の私は気付いていませんでした。


