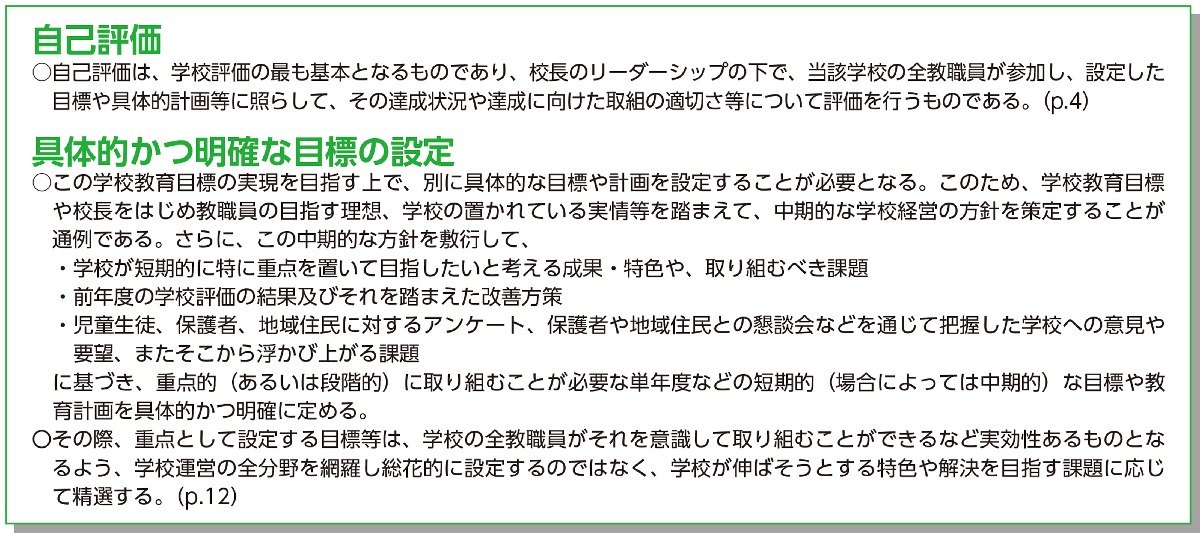なぜ作成するの? 学校経営計画の立案と実施~シリーズ「実践教育法規」~
- 連載
- シリーズ「実践教育法規」


教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第10回は「学校経営計画の立案と実施」について。学校経営計画は、何のために作成するのでしょうか。また、作成するうえでの注意点を、例とともに解説します。
執筆/蛯谷 みさ(大阪体育大学教育学部教授)
監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#10
目次
学校経営計画の作成根拠
学校経営計画とは、学校教育目標と、それを達成するための戦略を示したものです。中期的には3年程度、短期的には当該年度の学校経営方針を校長が明らかにして作成します。
2007年における学校教育法及び学校教育法施行規則の改正(第42条、43条/第66条、67条、68条)により、学校は法令上、次の3つを行うことが必要となりました。
①自己評価の実施・公表
②保護者など学校関係者による評価の実施・公表
③評価結果の設置者への報告
これを受けて2008年度からの学校評価の取り組みに活用できるよう、文部科学省において「学校評価ガイドライン」が改訂されました(2008年1月)。主な改訂点は次の通りです。
①自己評価について、重点化された目標を設定し精選して実施すること
②保護者による評価、学校の積極的な情報提供、それらを通じた学校・家庭・地域の連携協力を促進すること
③学校評価の結果を設置者に報告することにより、設置者が学校に対して適切に人事・予算上の支援・改善策を講じることの重要性が強調されたこと
こうして学校の自己評価が義務づけられたことから、法令ではありませんが、このガイドラインにあるように、学校運営の状況について評価を行う前提として、目標や評価項目等の設定を行う「学校経営計画」を作成することが必要となったのです。PDCAサイクルによる学校改善を推進し、学校が適切に説明責任を果たし、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めるために「学校経営計画」は重要な意義をもちます。