「架け橋期」とは?【知っておきたい教育用語】
文部科学省では、2022年に「幼保小の架け橋プログラム」を推進していくことを決めました。ここでいう「架け橋」とはどのような意味の言葉なのでしょうか。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
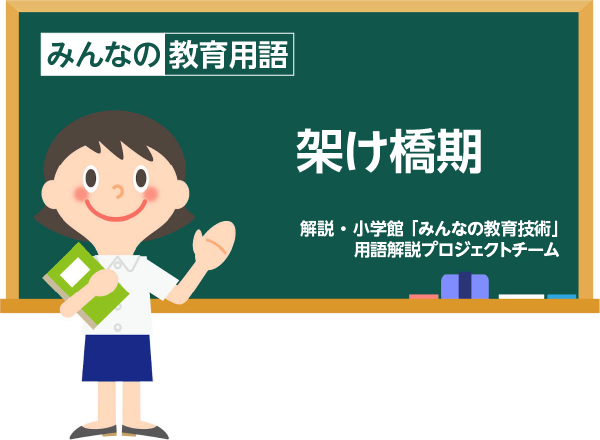
目次
架け橋期は、幼児教育と小学校教育をつなげる重要な時期
【架け橋期】
義務教育開始前後の5歳児~小学1年生の2年間のこと。文部科学省が推進する「幼保小の架け橋プログラム」は、幼児教育と小学校教育の円滑な接続によって、この時期の教育を充実させることを目的としている。
近年の幼児教育においては「幼保小連携」が重視されてきました。幼保小連携とは、幼稚園または保育園から小学校へと子どもたちがスムーズに移行できるよう、互いに連携することです。これによって子どもたちが小学校に入学したときに、授業中におしゃべりをしてしまう、席を立ってしまう、別行動をしてしまうといった「小1プロブレム」と呼ばれる問題の解決を図ります。
幼保小連携の推進で、小学校との連携を図る園が約9割にのぼるなど取組が大きく進展しました。ただ、取組が加速することによって、組織的な連携は常に課題とされてきました。特に、幼保と小でそれぞれの教育観や教育実践における共通認識のずれや理解不足、相互の指導計画の理解に努めても、用語の違いなどによって、十分に読み解くことができないといった問題がありました。
そこで、「幼保小の架け橋プログラム」では、幼保小だけでなく、家庭や地域、関係団体、地方自治体など、子どもに関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働することを目指します。加えて、「10の姿(幼児期の終わりまでに育ってほしい姿)」の正しい理解を促し、架け橋期における教育を充実させることで、子どもたちの生涯にわたる学びや生活の基盤づくりを実現します。
架け橋期の教育を充実させるために
「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」(令和5年2月27日)では、幼児教育施設と小学校の協働において以下の6つの方策を推進しています(主な項目を抜粋して紹介します)。
1.架け橋期の教育の充実
①子供の発達の段階を見通した架け橋期の教育の充実(幼・小)
②架け橋期のカリキュラムの作成及び評価の工夫によるPDCAサイクルの確立(幼・小)
2.幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有
①幼児教育の特性に関する認識の共有(幼・小)
②ICTの活用による教育実践や子供の学びの見える化(幼)
3.特別な配慮を必要とする子供や家庭への支援
①特別な配慮を必要とする子供と家庭のための幼保小の接続(幼・小)
②好事例の収集(幼・小)
4.全ての子供に格差なく学びや生活の基盤を育むための支援
①幼児教育施設の教育機能と場の提供(幼)
②全ての子供のウェルビーイングを保障するカリキュラムの実現(幼・小)
5.教育の質を保障するために必要な体制等
①地方自治体における推進体制の構築(幼・小)
②架け橋期の教育の質保障のために必要な人材育成等(幼・小)
③幼児期の教育の質保障のために必要な人材確保・定着等(幼)
6.教育の質を保障するために必要な調査研究等
①幼保小接続期の教育に関する調査研究(幼・小)
②幼児期の教育に関する調査研究(幼)
以上の6つの方策を実行していくことで、だれ一人取り残さず、すべての子どもたちが質の高い学びへと接続できる環境を整備します。そのためには、文部科学省だけでなく、こども家庭庁などの関係省庁とも、より密接な連携を図ることは欠かせません。

