「見方を変えよう~徹底した個への関心~」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #2

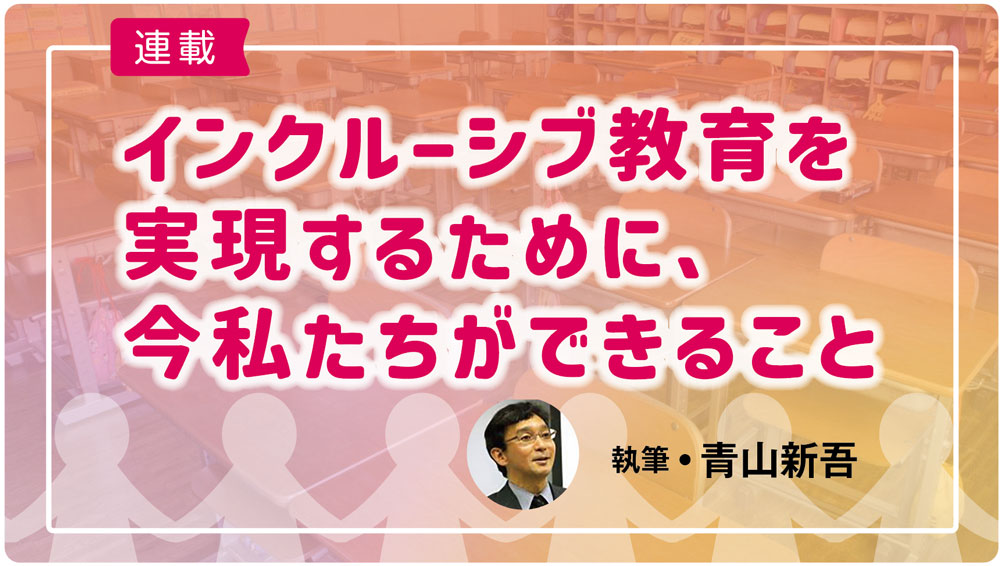
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。第2回のテーマは「見方を変えよう~徹底した個への関心~」です。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
研究室で聞かせてもらった子どもと若い教員のエピソード
連載第1回では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象であると書きました。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立ちました。
また、私たちが4月の最初にインクルーシブ教育を進めるために何ができるのかと考えたとき、僕は、子どものことを知ろうとすること、つまり、徹底した子どもへの関心をもって子どもと一緒に過ごすことが大切だと書きました。
・事前に資料や引き継ぎで子どもについて知っておくこと
・実際のつき合いのイメージをもちながら、子どもとのつき合いを開始すること
・実際のつき合いを通して、子どものことを「実感的把握」していくこと
ここからスタートしてみようと書いた原稿を読んだ若い先生たちが、僕の研究室を訪れてくれました。
教員A「隣のクラスに、ちょっと落ち着かない子どもがいるんです。先生の話が聞けなかったり、集中が続かなくなると動き始めたり、気になったいろいろなモノを教室に持ち込んだり……と、なかなか忙しいんです」

話の流れの中で、そのような話題になりました。
正直に言えば、そういった子どもたちが学校にいるのは当たり前です。ですから、僕の研究室で一緒に学んできた彼女たちにすれば、取り立てて大きな話題ではないはずです。でも、そのときはちょっと違いました。
教員A「隣のクラスの先生が、子どもをしっかり観察することが大切だといつもおっしゃっているんです。だから、本当にそうですね! って話しているんです」
教員B「それって、『徹底した個への関心』ですね!」
と、別の若者が、僕の連載を意識してフォローし、笑いが起きました。
教員A「でも…その子、毎日叱られてばかりになっているんです。よく、外から木の枝とか教室に持ってくるんです。いろいろな木の枝を拾ってくる」
教員C「いるいる、そういう感じの子! おもしろいね~」
と、仲間たちは似たような感じの子どもを思い浮かべながら話し込んでいます。僕はそれを黙って聞いていました。
教員A「でしょ? おもしろいよね。でも、隣からは『木の枝を持ってきたらいけません!』『危ないでしょう!』『捨ててきなさい!』みたいな声がよく聞こえてくる……。きっと、これまでに拾ってきた木の枝を振り回していたこともあったんだと思う。だから、注意したくなる気持ちになるのだろうなって思う。でも……」
そういった注意や叱責は、その子どもには届いていないと思うことを神妙に話す仲間の言葉を頷きながら聞き合うメンバーたち。
教員A「ちょうど、隣の担任がいないときに隣の教室に行くことがあったんです。そうしたら、その子が木の枝を持っていた。そこで、一緒にその枝を見ていたら『……の角度から見たら角になっているんだ。こっちの角度から見たら、カマキリだ』って言うんです。えっ? と思って見てみたら、確かにそのように見えるんですよ。わーってことになって」
教員A「それで、その子に『わー、よく見つけるね。確かにカマキリに見えるね。うん、発想力がいいね。これって図工だね。図工の勉強だね』と話したんです。そうしたら、『図工?』って言うから『そうそう、図工の勉強に、こうやっていろいろな見方をすることがあるんだよ。うん、○○さんは、いろいろなモノを見つめる目があるね!』と言いました」

彼女の穏やかな、そしてとてもリアリティのあるエピソード語りに、仲間も僕も心惹かれていました。それをきっかけに、その子が少しずつ話しかけてくるようになったことを聞きながら、一同納得と共感の言葉を重ねる時間になりました。

