誰一人取り残さない授業とは? 【伸びる教師 伸びない教師 第41回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

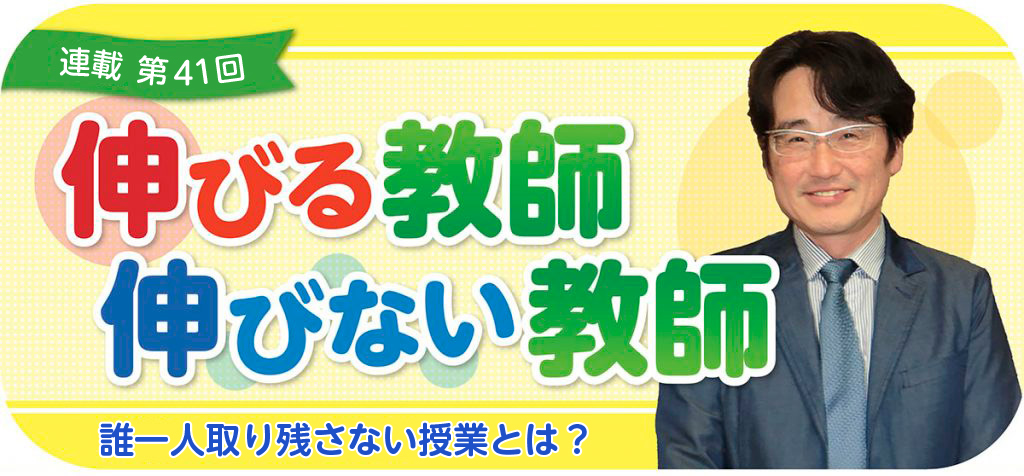
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「誰一人取り残さない授業とは?」です。一見、話し合いが活発になっていても、取り残されている子供がいるかもしれない意識をもち、子供たちの発言によって授業が進む授業例のお話です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
活発に見えていた話し合いが停滞
学級担任をしていたとき、私は子供たちが活発に意見を出し合い問題を解決していく話し合いの授業に憧れていました。
子供たちの意見がたくさん出るよう発問を工夫したりディベートを取り入れたり、本を読んで有名な教師の授業をまねしたり、いろいろな方法を試しました。
話し合い活動に力を入れていくと、発言する子供が増え、授業が活発になってきました。私は、子供たちにもそのことを感じさせようと、「話し合いが活発になってきたよ」「もっとがんばって発言しよう」と声をかけ、励ましました。
しかし、数か月が過ぎた頃、話し合いが停滞してきました。話し合いはしているけれど、授業に活気がなくなってきたのです。実際に授業で発言した子供の数を数えてみると、1時間の授業で多くて学級の半数、大体は3分の1程度の子供しか発言していないことに気付きました。
しかも発言する子供は決まっていて、その他の子供たちは活発に発言する子供たちの意見を聞いているだけでした。
学級全体としては、話し合いで活発に授業が進んでいるように見えるけれど、一人一人を見るとそうではなかったのです。

できない自分を感じる子供たち
子供たちが書いた日記を読むと、「手を挙げたいけれど勇気が出ない」と書いている子供が多くいました。
私はコメントで「がんばって」と書くだけで、手を挙げられない子供たちに対して個別に指導するまでには至りませんでした。
こうした子供の中には発言できない自分を責めたり、自分にはどうせできないと可能性を諦めたりした子供もいたかもしれません。
このように、周りの子供たちができるようになればなるほど、できない自分を感じてしまう子供が出てくることがあります。できない子供へのフォローがない私の指導は、できる子供とできない子供の差を広げてしまう指導だったのだと思います。

