被災地の学校関係者へ|鈴木利典 東日本大震災の経験から 【<能登半島地震>震災経験者からのメッセージ 子供の心を守るために #3】
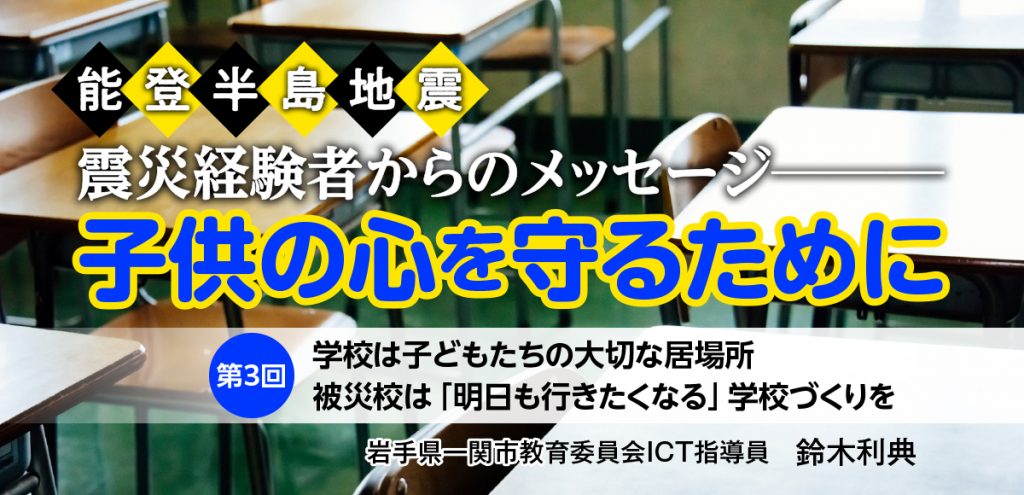
2024年1月1日 16時10分ごろ、石川県の能登半島で震度7の地震が発生しました。まずは被災された皆様に心より御見舞を申し上げます。被災地の状況は時の経過とともに変わっていくと思いますが、学校が大事にしなければならないのは、子供と先生たちの心ではないでしょうか。それらを守るために被災地の学校が何をする必要があるのかを、過去の震災経験者の先生方から聴く3回シリーズの最終回です。今回は東日本大震災から1年後に、最も被害が大きかったとされる地域の中学校の校長となった鈴木利典さんにお話を聴きました。

鈴木利典(すずき・としのり)
1959年岩手県一関市生まれ。岩手大学工学部卒業後に教員となり、陸前高田市立広田中学校、同第一中学校、大槌町立大槌中学校等を経て、大船渡市立越喜中学校教頭、岩手県立総合教育センター情報教育室長、大槌町立大槌中学校・陸前高田市立気仙中学校・一関市立巌美中学校の校長を歴任。2020年に定年退職し、現在は一関市教育委員会ICT指導員として活動しながら、情報モラル×復興教育をテーマに全国で講演活動も行う。著書に『子どもたちは未来の設計者〜東日本大震災「その後」の教訓〜』、『3・11震災を知らない君たちへ』(いずれも、ぱるす出版)がある。
■ 本企画の記事一覧です(全3回予定)
●被災地の学校関係者へ|多賀一郎 阪神・淡路大震災の経験から
●被災地の学校関係者へ|桃﨑剛寿 熊本地震の経験から
●被災地の学校関係者へ|鈴木利典 東日本大震災の経験から(本記事)
目次
Q 能登半島地震を受けて、現在の気持ちを聞かせてください。
東日本大震災のとき、私は花巻市にある岩手県立総合教育センターに勤務しており、家も内陸にありましたので、震災後は支援者という立場で様々な被災地に入りました。そして、地震から1年後に大槌町立大槌中学校、3年後に陸前高田市立気仙中学校の校長となり、今度は支援される立場になりました。
岩手県では大槌町と陸前高田市が最も被害が激しかった場所だとされているのですが、初任から12年、教頭時代の2年と合わせて14年間勤務した場所です。あの日亡くなった教え子、保護者、同僚、知人は数えきれません。
とはいっても、震災で家や家族を失った生徒や保護者、先生方の気持ちを本当の意味で理解できるかというと、それはできないと思います。
ただ、おそらく被災した人たちは自分の経験を話さないと思います。家族を失った多くの人たちは、決して表舞台に出てきません。死ぬまで震災の話をしないで、墓までもっていく人がほとんどなのではないかという気がします。
その点、私は半分だけ被災者で、半分だけ支援者です。被災地の外の皆さんに、中で起きていたことを話すのは、私のような中間にいた人間の務めなのだろうと思っています。
能登半島地震の「今」の状況に対しては、私はコメントできる立場にはないと思っています。しかし、東日本大震災の被災地では震災の「その後」が今も続いています。被災地の中学校に4年間勤務した経験を基に、「その後」、つまり、「被災地のこれから」について何かアドバイスができればと思っています。
Q 東日本大震災の後の二つの中学校の生徒たちの様子を聞かせてください。
震災から1年後に校長として赴任した大槌町立大槌中学校は全校生徒267人中、被災生徒は184人に上り、127人が仮設住宅から通学していました。就学援助制度の対象者は154人に上ります。
2012年4月には、まだ町中のいたるところに震災の爪痕が残っていました。以前、6年ほど大槌中学校で教員をしていたこともあり、かつての教え子や保護者、仮設校舎で過ごす生徒やその保護者のことが気がかりで、不安を抱えての赴任となりました。
ところが、震災のど真ん中と言われる中学校で私を待っていたのは、朝は「おはようございます」、廊下ですれ違うときは「こんにちは」、下校時には「さようなら」と一日に何度も挨拶を交わしてくれる生徒たちでした。先生方が声を荒げるような場面は皆無で、修学旅行を楽しみ、体育祭で汗を流し、合唱も見事でした。部活動では、地区大会で8チームが優勝し、個人戦でも8人が優勝しました。
私はこれまでの教員生活でたくさんの中学生を見てきましたが、そこにいたのは今までに会ったことのないような、真面目で真摯な生徒たちでした。
そんな中で特に印象に残っているのは、仮設校舎の校長室の前の廊下を雑巾がけしてくれた女子生徒の姿です。彼女は震災で母親を亡くしています。毎日、校長室に掃除をしにきてくれたのですが、膝をつき、袖をまくり上げ、いくら磨いても光らない仮設校舎の廊下を雑巾で一心にふき続ける姿は、とても尊く、輝いて見えました。
生徒たちはやる気も思いやりもあり、進路意識も高く、すべてにおいて輝いていました。生徒たちの写真をいつ撮っても元気な笑顔で、被災地で奇跡を見ているような気がしました。学級が荒れることもなく、いじめも皆無です。視察に来る人たちが皆、「なぜこんなに元気なのですか」と驚いて帰っていくほどです。
震災直後に、生徒たちに寄り添った先生方は本当に立派だったと思います。よくぞここまで育ててくださいましたと感謝の気持ちでいっぱいになり、私は校長としてこの生徒たちの笑顔を途絶えさせてはいけないと思っていました。
2014年4月、今度は、陸前高田市立気仙中学校の校長になりました。震災から4年経っても全校生徒の8割近くが市内各地の仮設住宅からスクールバスで通学していましたが、この学校の生徒たちも明るく、みんな笑顔でした。
気仙中学校では夏休みだというのに、毎日、全校生徒がスクールバスで登校していました。登校した生徒たちは朝8時半から9時半まで全校トレーニングに参加し、その後、1、2年生は部活動に参加し、3年生は受験勉強や、体育館のステージで地元の伝統行事「けんか七夕太鼓」を継承するための練習に励みます。そして、昼が近くなると学校の近くにある清流で川遊びを楽しんで帰っていきました。
また、気仙中学校の3年生は英語検定に挑戦し、全員が合格しました。3級以上に8割が合格したのです。
両中学校とも、ほとんどの生徒が家族か知人を亡くしていますが、みんな明るく元気で、何事にも真面目に取り組むのです。最初は「親にも先生にも心配をかけたくないと思って、背伸びしているのではないか」と考えました。
しかし、実際に被災した中学生と4年間関わっていくうちに、背伸びではなくてあれは本心だと思えるようになりました。
なぜこんなに生徒たちが真面目に頑張っていたのかというと、それは学校が楽しかったからだと思います。
多くの生徒たちは仮設住宅で暮らしています。仮説住宅は玄関を入るとすぐに台所があり、その奥にトイレとお風呂がありますが脱衣所はありません。あとは6畳の居間と4畳半の寝室です。家の中で一人になれる場所などありません。中学生でも親と同じ部屋に寝なければならず、それが嫌なら居間に布団を敷かなければいけないわけです。脱衣所のないお風呂なので女子中学生は恥ずかしい思いをしたのではないかと思います。
そして、多くの家にはお金がありませんでした。職場が津波に流されて親が失業したからです。おそらく間食の回数は減ったでしょうし、外食など考えられないでしょう。そういう環境の中で両親のけんかもあったと思うのです。
それでも学校に来ると、友達がいる。給食が食べられる。昼休みは友達と一緒に遊べる。午後になれば部活動で汗を流せる。たとえ仮設校舎であっても、学校は彼らの居場所であり、救いの場所です。だから、あの笑顔だったのではないかと思うのです。
奇跡のような生徒たちに会えたと思っているのは、私だけではありません。 被災地で一緒に働いた先生方と会う機会があると、今でも「あんなに素敵な生徒たちにはもう会えないよね」という話をしています。お世辞ではなくて、本当に輝いていました。

