グローバル化する社会の中での学校教育とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #11

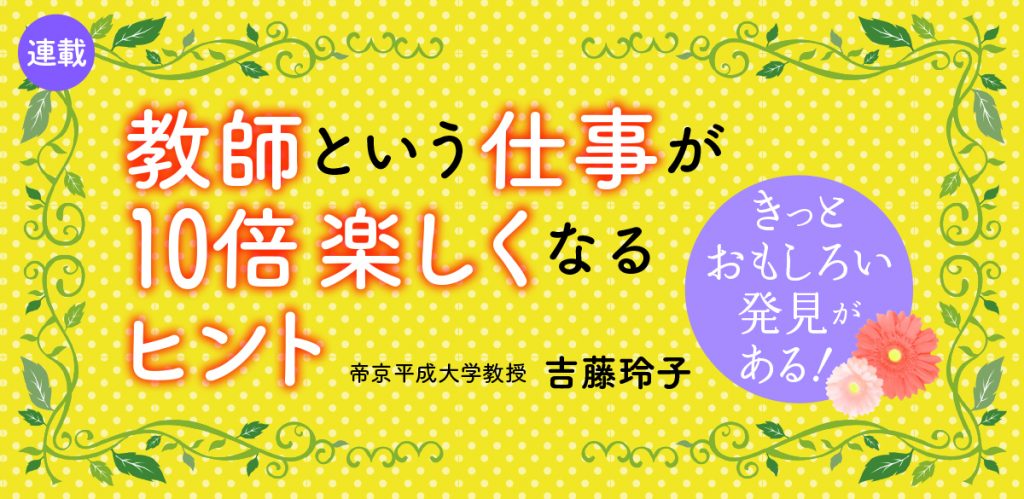
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの11回目のテーマは、「グローバル化する社会の中での学校教育とは?」です。学校現場で確実に増える外国がルーツの子供や保護者との対応、異文化理解の実践の工夫、異文化を理解するためのヒントなどについてお話しします。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
外国籍の子供たちとの関係に悩む
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、海外から大勢の旅行客が日本を訪れています。私は、東京・浅草に近い所に住んでいますが、仲見世などの混雑は、毎日がお正月のようなにぎわいで驚いています。
学校現場にも今、多くの外国籍の子供が学んでいます。日本に来たばかりで日本語が話せない場合には、日本語指導の巡回講師が教える制度が各自治体にあります。また、日本在住の外国人に向けた行政のパンフレットやホームページも多言語化されています。
しかし、実際問題として、外国人の子供がクラスになじまない、保護者と話が通じないなどで困った経験はありませんか。また、教師自身もどのように外国籍の子供たちと関係をつくっていったらよいのかと悩むこともあるでしょう。今回は、確実に増える外国人への対応、その背景の異文化をどのように子供たちや教師が理解していったらよいかについて、私なりの経験を交えてお伝えしたいと思います。
伝えたいことを伝えるには
子供は言葉を覚えるのがとても早いです。外国から子供が転入してきた場合、1学期には日本語がほとんど話せなかったのに、2学期にはもうクラスの友達と楽しく会話をしている場面を見ることがあります。
しかし、教師としては、その子供の保護者に連絡したいことがたくさんあるのに、きちんと伝わったかどうか分からない、何度話しても提出物が揃わないなど、困ることが多くあります。私の経験でも校外学習に必要な持ち物が伝わっていなかった、雨で延期になった行事の日程が分かっていなかったなどの行き違いがありました。事前に学校で出会ったときや電話で、丁寧に口頭で伝えていたつもりでしたが、日本語がよく分からない保護者は、うなずいていたものの実際は理解できていなかったということがよくありました。
学校現場では、毎日たくさんのプリントを子供たちに配付します。昨今、メールでのお知らせが増えたものの、いろいろな団体からの宣伝広告も含めて、まだまだたくさんのプリントを子供たちは家に持ち帰っています。プリントを配付したり、メールで必要事項について配信したりすれば、保護者は分かってくれると教師は思いがちですが、両親が働いている家庭も増え、保護者がすべてのプリント類に目を通すのは大変な作業です。日本人の保護者でも膨大なプリント類をチェックするのが大変なわけですから、教師は、外国人の保護者が必要事項を理解するのは難しいことなのだということを分かっておく必要があります。
ではどうしたらよいかというと、子供に日本語指導をする、またはその国の言語に強い講師の先生の力を借りるとよいでしょう。日本語指導の先生に、重要事項を翻訳してもらい、メモしてもらえば、担任が保護者に伝えることができます。時間がうまく合えば、保護者面談なども日本語講師に通訳してもらうのもよいでしょう。時間的に無理なようであれば、翻訳アプリなどを活用して、やりとりすることも考えられますが、可能な限り、口頭で伝えることができる方法を考えたいものです。私の場合、日本在住が長く日本語が話せる中国人の保護者に、中国から来たばかりの家族への連絡をお願いしたことがありました。
日本語が分からない保護者に配付物を渡すときには、これだけは絶対に重要だという箇所、必要な持ち物などのところにラインマーカーで印を付けることを試してみてはどうでしょうか。私は、赤ペンでプリントの右端に二重丸を付け、「このプリントだけは絶対によく見てください」という合図にしていました。また、「分からなければ学校へ聞いてください」と事前に伝えておきました。
日本語がネイティブではない保護者に対しては、「どうしたら伝わるか」ということを考え、対応することが大切です。


