通知表に替わるものとして、年2回の個人面談を実施【都心の小学校校長にインタビュー! 「宿題、テスト、通知表廃止」の背景と経緯 #03】
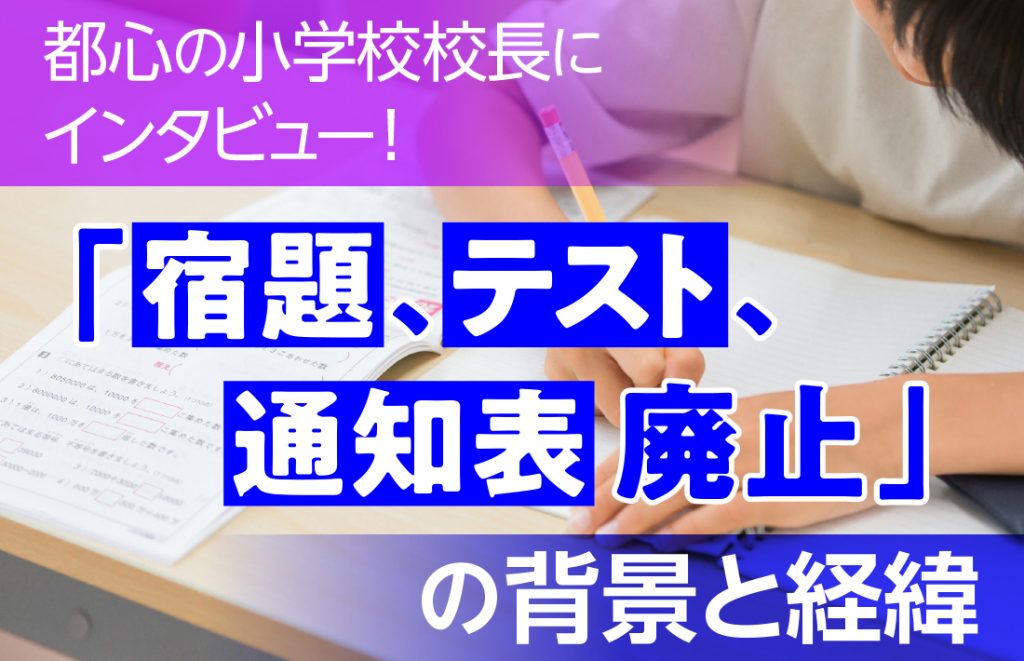
前回、どんなふうに保護者や地域、教員に対して改革の導入を周知し、理解を図ってきたか、長井満敏校長に聞きました。今回はそうした準備の後、2023年度、どのように実施を図り、保護者や教員などからどのような反響があるのかなどについて紹介をしていきます。

目次
肌感として戸惑いを感じているのは保護者よりも教員
与える家庭学習やテスト、通知表の廃止についてどのように実施され、どのような反応があったのでしょうか。長井校長は次のように話します。
「宿題について私から教員に話したのは、『教師が与える家庭宿題はやめて、子供が主体的に学ぶものにしましょう』ということだけです。そのため、特に学校として統一した呼称も設けてはいませんし、学級によって呼称はバラバラですし、それを確認もしていません。ただ、自主学習用のノートを揃えて買っている学年もあり、それは足並みを揃える方向への無言の圧力になる可能性もあるので、出す出さないは子供に任せるようにという話はしています。自主学習といっても量や時間、内容を示されると、めざす本質とは異なるものになってしまいますから。ただ現時点で、あまり細かいことをうるさく言わないようにして任せています。ちなみに保護者から、与えられる家庭学習を再開してほしいという声は特に聞いていません。
単元テストや通知表などの評価の部分に関しても、『それがないから困った』という声は今のところないのです。ただ1学期の学校評価のアンケートを見ると、反対意見として、『学校での学習の様子が分からない』というような声はありましたが、それについては、CDTの実施や年末、年度末の2回の個人面談を通して細やかに伝えていきますし、強い反対は現時点ではありません。
私自身が実践を進めながら十分に説明を尽くしきれていない部分もあると思いますが、肌感として戸惑いを感じているのは保護者よりも教員のほうだと思います。おそらく、本来の意味の『指導と評価の一体化』ではなく、評価と指導が一緒になってしまっていたところがあったのではないでしょうか。宿題を出すとかテストするということによって、子供を学習に向かわせている、つまり宿題やテストを学習への動機付けにしてしまっていた部分があったのではないかと思います。実際に職員と話す中で、『もっと準備してから始めるほうがよかったのでは?』といった声もありましたが、もしそのような評価と指導への意識があるとすれば、おそらく準備に時間をかけていたら、実施できなかったのではないかと感じています。
通知表に関しては、それに替わるものとして、年2回の個人面談を実施し、この12月中に1回目を終えたところですが、今のところ特に問題なく終わりました。CDTを活用しながら面談を行ったわけですが、保護者からは何らかの問題点を指摘する声は聞いていません。教員からは、最終的な指導要録を付けるときに何らかのむずかしさがないか、2023年度が終わったときにはっきりすることもあるので、年度の総括で、改めて課題や改善点について評価していきたいと思っています。ただし、CDTを活用すれば、それほどむずかしくないのではないかと現時点では考えています」
特に問題は生じていないと言いますが、では逆に何らかの良い変化はなかったのでしょうか。長井校長は次のように話します。
「小さな変化ではありますが、テストやテスト直しの時間がなくなったので、先生方の時間的な余裕も生まれましたし、帰宅時刻は早くなってきています。つい先日、副校長と話をしたときに、『通知表を付ける時期(2期制なので、以前は9~10月)に、先生方がどこかカリカリしていた感じは今年はなかった』という話は出ました」


