生活科からつながる、「自然事象への興味・関心」を高める理科学習の手立て 【理科の壺】

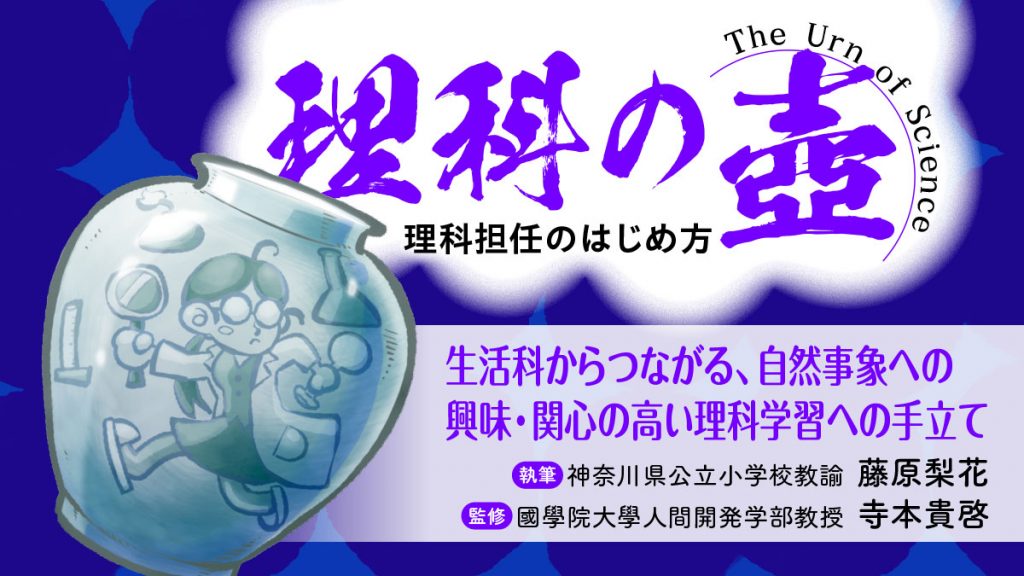
理科の学習では自然の事象と出合い、それをじっくり観察する力が大切ですが、これと生活科の学習は地続きです。生活科では「気づきの質を高める」ことが重視されているからです。そして気づきの質を高めるには、実際に自然事象に対する興味・関心を高める工夫が必要だと言えるでしょう。
では、その手立てはどのようにすればよいのでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・藤原梨花
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
はじめに
理科の学習では、チョウやメダカの成長など生き物をじっくり観察する力が大切になります。その力をつけるためには、生活科で生き物と触れ合ったり観察したりして、愛着をもつ時間が大切になってきます。今回は私が担任をしている、個別支援学級の生活科の学習の手立てから、生き物への愛着をもち、細かく観察したりする力を育む手立てを紹介したいと思います。一般級での学習にも生かせることがあると思います。
1.生き物を身近に感じるICT活用
個別支援学級の生活科「いきものと なかよし」の学習では、ダンゴムシを育て、その成長の変化や世話の仕方を考える学習を行いました。
ダンゴムシのような小さな生き物は、細部まで肉眼で見ることが難しく、集中して観察するのが難しいと感じる子どもも多いのではないかと思います。
そこで活用できるのが、タブレットにつけて使うマクロレンズです。100円ショップなどで手に入れることができます。
(※編集部注 100円ショップなどで売られているスマホ・タブレット用のレンズには、望遠レンズなど近くのものを拡大できないものもあります。「マクロレンズ」または「顕微鏡レンズ」などと書かれている商品を選びましょう)


これをタブレットのカメラ部分につけると、これまでは見えづらかったダンゴムシが食事をする様子など、小さな虫の生き生きとした活動の様子をリアルタイムに細かく観察することができました。「口はここにあるんだね」「手を使ってごはんを食べているよ」など、体の様子にも気付く姿が見られました。さらに、こうした虫の様子を録画することで、振り返りの場面でも、クラスで共有することができました。見えなかったものが見えるようになったことで、観察への意欲が高まりました。



