提言|安宅和人 今の小学生に、知って欲しいことは? 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #08】
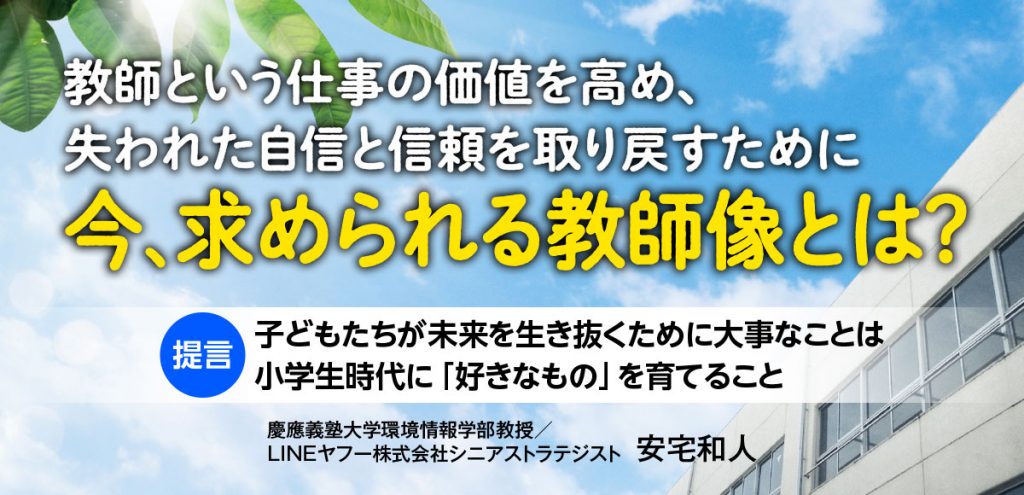
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第8回目、最終回です。今回は、未来の子どもの姿から、教師がすべきことを探ります。これまでに日本が進むべき道を提言してきた慶應義塾大学の安宅和人教授に話を聞きました。
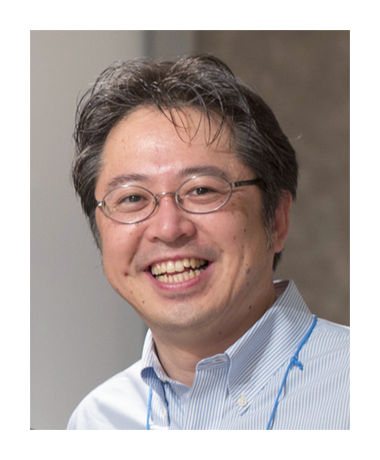
安宅和人(あたか・かずと)
マッキンゼーにて11年間、幅広い商品・事業開発、ブランド再生に携わった後、2008年からヤフー、2012年より10年間CSOを務め、2022年よりZホールディングス(現LINEヤフー株式会社)シニアストラテジスト。2016年より慶應義塾大学SFCで教え、2018年秋より現職。データサイエンティスト協会理事・スキル定義委員長。一般社団法人 残すに値する未来 代表。科学技術及びデータ×AIに関する国の検討に数多く携わる。東京大学理学系研究科修士(生物化学)、イェール大学脳神経科学PhD。著書に『イシューからはじめよ』(英治出版、2010)、『シン・ニホン』(NewsPicks、2020)などがある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている
●提言|前田康裕 ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信
●提言|神内聡(弁護士) 分かり合えない保護者にどう対応するか
●提言|成田奈緒子(小児科医) 発達障害かもしれないと思ったら、教師がすべきこと
●提言|赤坂真二 令和版、尊敬される教師とは?
●提言|岡田治美 理想と現実の狭間で、今、学校で何が起きているのか
●提言|山田洋一 今、学級担任に求められる知識やスキルは?
●提言|安宅和人 今の小学生に、知って欲しいことは?(本記事)
目次
学校で小学生に教えて欲しい4つのこと
今の小学生が大人になるころには、多くの人が意識する、しないに関わらず日々AIを使い倒すのが基本になることはほぼ確定的であって、これは別に、私があえて説明するまでもないことです。ただ、今後、そのような時代になるとしても、小学校の低学年・中学年のレベルでは、読み書きができたほうがいいですし、数字に触れた方がいいです。AIのベースであるデータも数字です。また基本的な社会の仕組みやルールについて学んでおいた方がいいと思います。以下に、学校で育んで欲しいことの項目を挙げていきますが、大事なのは、なぜ学ばないといけないのかを、子どもたちが皮膚感覚で理解することです。
文字を読むことの喜びを知る
小学生のうちに、文字を読むこと、そこから広がる世界に触れる喜びを知った方がいいと思います。学習障害の子どもが人口の5~7%程度はいると言われていますが、残りの人口の9割は文字を読む喜びを得ることができるはずです。文字を読むのが不得意でない人については、最初は絵本からでもいいので、ものを読む喜び、読むことで心を広げる喜びを味わえる機会をつくって欲しいと思います。なぜなら、調べたいテーマができたときに、本があったら、いくらでも深く掘れますし、楽しい物語もいくらでもあり、人が生み出してきた膨大な知識や知恵に触れることができるからです。このことに気付けば、たとえ教室に先生がいなくても、本があれば、ある程度自分で学習を進めていけます。
数字に触れる
数字の概念を質感とともに学ぶ必要があります。数字とは、人間の抽象思考の最も純粋な形であり、数字を扱えないと、この世の現象を表現したり、理解したりできないからです。ここに何匹のアリがいるのか、一か月前よりどれだけ増えたかということを表現するだけでも数が必要です。これからのデータ駆動型の社会は数字で支える世界だということもあります。そういう意味では、読み書きそろばんのベースの部分は、今後も変わらず重要であり、逆に、数字がないと困ること、数字が扱えるとこんなに便利なのだということを皮膚感覚的に理解する価値はとても大きいです。
だからこそ、子どもを算数・数学嫌いにしてはいけないのです。どういうときに使う、どういう道具なのかをセットで伝え、実感してもらうことが大切だと思います。
中学校になると関数が出てきます。関数は世界を表すモデルの基本ですから、自然現象を定量的に扱おうと思うと必要になります。例えば、指数関数的な変化です。コロナの患者数も、口コミも指数関数的で、こういった現象をうまく量的に表現しようと思うと、指数関数が必要になります。このように、この世にあることを表現しようと思ったら、ある種のトリックというか知恵がいるのですが、こうやったらこういう変化が量的に表せて、未来が予測できる、といった道具を我々の先祖はたくさん生み出してきました。先生たちは、そういう便利な道具を教えているのだという意識をもって、子どもたちに伝えていただけたらうれしいです。
社会のルールを知る
小中学生は、社会にはマナーやルールがあること、人付き合いの中で言葉をおおむね的確に使わないと意味が伝わらないことなど、基本的なことを学ぶ必要があります。社会における基本的なマナーとルール、なぜそれが大事なのかを、深い意味で分かる価値は大きいです。それらを軍事教練的に教えるのではなくて、それがないと社会が混乱に陥ることを、身をもって学び、ルールを作っていかないと社会は回らないことを理解しておくべきかと思います。
ただし、ルールはそれに関わるみんなの決め事ですから、自分たちで変えられることも学ぶべきです。クラス、学校、まちや村、県、会社、国、様々な単位でルールを決めています。どうやったら一番調子良く社会が動くのかについて考えることは、いずれ世の中に出る彼ら一人一人にとってとても重要です。
今の社会は変化が激しいですから、新しいことが次から次へと起きてきます。5年ぐらい前からAIを使った、本人でも本物と識別がつかないほど高品質な偽物の写真や動画も生まれてきています。これらの今、起きている問題に対して、現在、大人たちが様々なルールを作っているところです。私もそのルール検討に多少関わっていますが、小中学生だって様々な変化に応じたルールを考えられます。これらの変化に対して、どういうガイドラインがあったらいいと思うのかについて、小学校の高学年以上であれば一緒に考えうるはずです。社会をうまく動かすためにルールはあり、それは日々、改変し、生み出されていることを知ることはとても大切です。昔の校則的なガチガチの世界と本物の社会は真逆です。
ダイバーシティを知る
この他に、小中学校のときに学ばなければいけないと私が思うのは、社会のダイバーシティの基本です。教室の中には、男子と女子がいます。背が高い人も低い人もいます。運動が得意な人、絵を描くのが上手い人、手先が器用な人、動植物に関する造詣が深い人などもいます。この社会がどれほど多様でおもしろいものであって、ダイナミックで力強いか、多様な人がいるから新しい価値が生まれるということを肌身で学べるのは多分、小学校、幼稚園、保育園などの初等教育機関だと思うのです。ですから、この時期にダイバーシティの低い場所で子どもを育てることは、リスクが高いと私は思っています。そういう意味では特に、公立の初等教育機関の役割は重大だと思います。学校という場では、この世の広がりの豊かさ、その大切さを、子どもに理解してもらわねばいけないのですが、口で言うだけでは伝わらないので、様々な活動を通して見せて感じさせることが重要だと思います。むしろ逆に判で押したような人しか認めていない可能性を、常に教師の側はチェックすべきです。
先生たちに育てて欲しいのは、子どもたちの「好き」なこと
また、小中学生時代は、自分はどういうことを楽しいと感じるか、どういうことに興味を持っているのか、そういった人間の一番根っこの部分が育つ時期だと思うのです。先生方にはそれをぜひ育ててもらいたいのです。例えば、それは手を使って何かを作ることなのかもしれないし、歴史やサイエンスなどの特定の分野に興味を持つことなのかもしれないし、野菜や草花など、身近にある物に興味を持つことなのかもしれません。とにかく何か、自分の好きなものの種が見つかるといいと思います。好きの対象は一人一人、違っていいのです。何個あってもかまいません。勉強の科目には関係なく、その人なりの好きや、情熱を注げるものは何かということです。
もしもそれが小学生で見つけられず、中学生になっても見つけられなかったとしたら、その人は一生、しんどくなる可能性があります。自分にやりたいことがある人は、人を呼び寄せることができますが、それがない人は、やりたいことがある人に、使われるだけの人生になってしまいがちだからです。
もちろん、市区町村や県等の窓口の役人の方々のように、人のためにルールに合わせて働く人たちも世の中には必要です。しかし、やがて機械がその人たちの仕事をおおむねやる時代になります。自分の意思をもたずに働くことの価値は、減っていくのです。
だからこそ、やりたいことがある人を育てる必要があるのです。その一番のベースは、好きなものがあること、自分なりに良い悪いを判断できることです。好きの延長に、その人なりの心のベクトルというべきものがあります。そうやって、好きなことをどんどん伸ばしていくと、将来につながっていきます。
反対に、これまでの学校教育のように、苦手なもの、できないものを克服する系の教育ばかりやりすぎると、得意なものがなくなってしまいます。その結果、金太郎飴のように、どこを切っても同じような人ばかりになってしまうと思うのです。

