提言|山田洋一 今、学級担任に求められる知識やスキルは? 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #07】
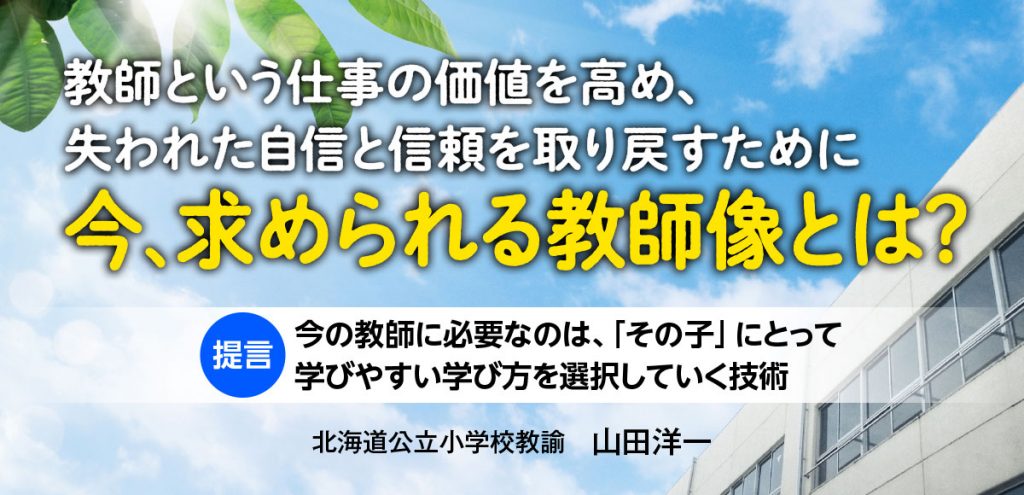
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第7回目です。今回は、現役の小学校教諭の山田洋一さんに、学級担任の立場から語ってもらいました。

山田洋一(やまだ・よういち)
1969年北海道札幌市生まれ。北海道教育大学旭川校卒業。北海道教育大学教職大学院修了(教職修士)。2年間私立幼稚園に勤務した後、公立小学校の教員になる。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。日本学級経営学会理事。公認心理師。『子どもの笑顔を取り戻す!「 むずかしい学級」リカバリーガイド』(明治図書出版、2021)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている
●提言|前田康裕 ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信
●提言|神内聡(弁護士) 分かり合えない保護者にどう対応するか
●提言|成田奈緒子(小児科医) 発達障害かもしれないと思ったら、教師がすべきこと
●提言|赤坂真二 令和版、尊敬される教師とは?
●提言|岡田治美 理想と現実の狭間で、今、学校で何が起きているのか
●提言|山田洋一 今、学級担任に求められる知識やスキルは?(本記事)
目次
教師という仕事の価値について
本来、どの仕事にも価値があってしかるべきだと思うのです。ですから、教師という仕事に価値があるとかないとか、そんなふうに考える必要はないと思います。私は他の職業と比べて、教師という仕事の価値が低いと思ったこともなければ、 高いと思ったこともありません。教師という仕事の価値が下がっていると考えている人は、何と比較してそのように言っているのでしょうか。私にはよくわかりません。少なくとも私は、教師という仕事の価値を、人に決められたくはないです。子どもが今日はたくさん笑顔を見せてくれたから幸せだ、 今日は私が準備した教材を使って子どもたちが最後にできるようになったから幸せだ、これらのことに価値があるかどうかを決めるのは自分自身です。仕事の価値は自分で決めたいです。
もしも、教師という仕事の価値を、社会的にもっと認められたいと考えている教員がいるとしたら、自分の仕事を良くするしかないのではないかと思います。良い仕事をすれば、自分自身でこの仕事には価値があると思えますし、他の業界の人から見ても、教師という仕事は良い仕事だな、と認めてもらえるのではないでしょうか。
教員採用試験の倍率が下がったことを、現場の教員が嘆いても、仕方がないことです。今後、どんな人が教員になったとしても、現場では、その人たちをどのように育てるかが大事なのではないかと思っています。
昔の教師と今の教師の違い
ただ、今の教師に求められるものは、昔から教師が行ってきたこととは違ってきているのは事実です。では、今の教師に求められるものは何かというと、子どものことを知るための知識やスキルだと思います。
例えば、1980年代の教師の関心事は、子どもにいかに上手に教えるかでした。そのために、教育の技術が必要だったのですが、当時の教え方も教育技術も、「教師の側から見て」良いものでした。一般的な子どもという概念があって、こう教えれば子どもはこのようにわかるはずだ、こう教えればこのように熱中するはずだと考えられていたからです。そして、教員が「この教え方は間違いない」と言われている教え方をして、それでもわからない子どもたちがいたら、その子どもたちのせいにできたのです。「こんなに素晴らしい教え方をしているのに、どうして君はわからないんだ。ちゃんと勉強しなきゃダメじゃないか」と言えたのです。
しかし、今の教育現場を見ると、いろいろな子どもたちが教室の中にいますから、一般的に良いと言われている教え方が、 全ての子どもたちに通用するとは言い難いのです。ですから、今は子どもから見た良い教え方、良い教育技術を私たちは採用する必要があります。
もちろん、一般的に知られている教育技術があって、その中に多くの子どもたちが学びやすい学び方がある程度はあると思うのですが、それをやった上で、学べない子どもがいたとしたら、その子どもにとって学びやすい学び方を選択できる、そういう技術が必要なのだと思います。
だからこそ、今の教師は子どもについて知る必要があります。しかも、子ども一般ではなく、「その子」を知るためのスキルや知識が重要になってくるのです。つまり、「子どもに学べる教師」が、 おそらく一番優れた教師なのだと思います。それも子ども全般ではなくて、 この子からも、その子からも、一人一人の子どもから学んで、学びやすい方法は何なのかを対話しながら決めていける教師です。
例えば、「私の教え方が絶対にどの子にも合うとは限らないよ」と、子どもたちにメッセージしておいて、「今日はこの教え方をしたけれど、この教え方で君はうまく学べなかったようだね。どういう環境で、どういう教材で、どんな教え方だったら、学べそうかな」と子どもと対話しながら決めていくのです。
ただし、この対応を一人の担任が、クラスの複数の子どもたちに対して行うとなると、状況によっては難しい場合もあります。それを助けてくれるツールの一つが、1人1台の端末なのだと思うのです。以前から、 一人一人に対応した教育をやりたいと願う教員はいたわけで、その人たちは、プリントを何種類も用意するなどして、子どもたちに提供していたのです。その指導観は、教員の労力によって、成立していたわけです。
それが今は、1人1台の端末を使えば、データベースにレベル別の練習問題が入っていたり、AIがその子どもに必要な問題を提供してくれたりします。
例えば、算数の問題を1題出します。その問題が簡単だと感じる子がいます。今までだったら、「待っていなさい」と言われて、他の子どもたちができるまで待たされていましたが、これからは待っていなくても、1人1台の端末を使ってその子に合った教材へと進んでいけるのです。その一方で、難しいと感じる子も当然いるわけです。そうした子には、もっと前の段階から学び直しができるような教材を提供することが可能な時代になってきています。

