子供の対話 【わかる!教育ニュース#35】
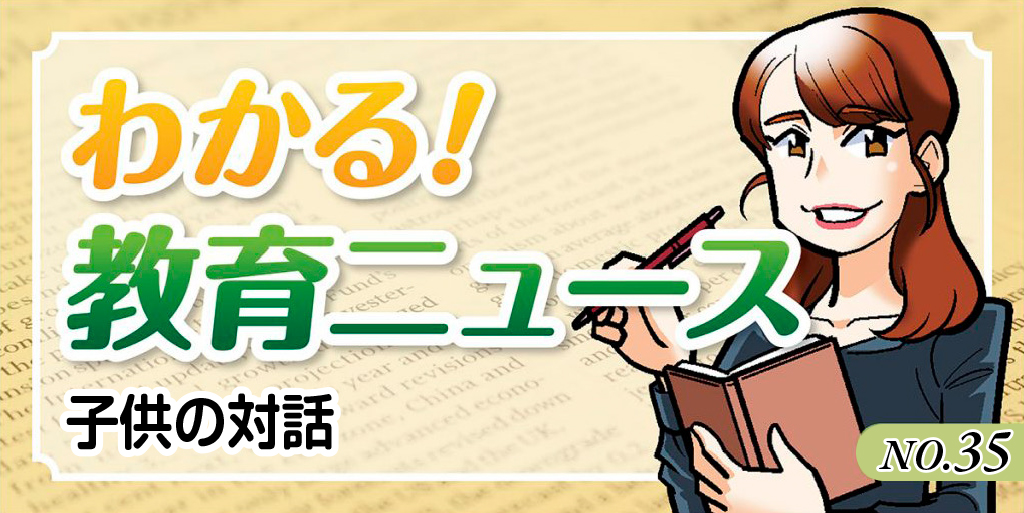
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第35回のテーマは「子供の対話」です。
目次
子供たちによる「対話」を政策形成過程に反映する?
学校で学ぶ意義って、何だろう。子供が秘めている力を伸ばすには? 「いい学校」とは? その答えを探すとき、当の「子供」の目線は入っていますか。
子供たちによる「対話」を政策形成過程に反映する方法に関する調査研究。文部科学省がこのほど、そんな長い名称の研究結果を公表しました(参照データ)。要は、子供の視点を教育政策に反映する際、校内での対話を生かせないか、という試みです。
調査には小中学校1校ずつ計約130人が参加。子供たちだけで1つのテーマにつき、2回協議しました。小学生のテーマは委員会活動、宿泊学習、学園祭。1回目はそれぞれの問題点を協議し、2回目はどういう状態が理想か、実現の壁は何かを考えました。
宿泊学習では、まず困ったことを語ってもらいました。「温泉の場所や入る時間が分からない」「宿の部屋を間違えた」「ベッドより布団」などのほか、自分たちで宿の手配や部屋の選択をしたい、という声もありました。
理想の状態を考える際は、「下級生に残したい○○な宿泊学習」という切り口を設定。○○には、「自分たちでルールを決める」「嫌な思いをする人がいない」などが挙がりました。意見を深掘りすると、「自分たちで計画できる」「スマホを持参できる」「持ち物が指定されない」など、管理を考えがちな大人と違う視点が表れました。そこからスマホ、人間関係、お金など課題を細分化し、なぜ実現できないか、どう解決するかを探りました。

