「データ駆動型教育」とは?【知っておきたい教育用語】
2021年6月、教育再生実行会議は、第十二次提言として「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について」を発表しました。これからの社会の創り手の育成に欠かせない学習者主体の教育への転換の一つの視点として教育のデジタル化とそれに伴うデータ駆動型の教育体制の整備が強調されています。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
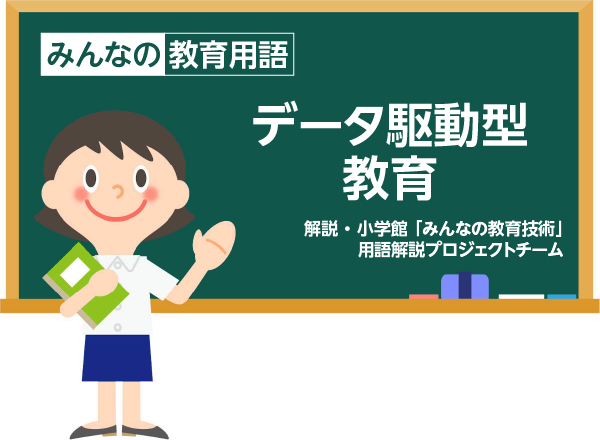
目次
データ駆動型社会の進展
スマートフォンで買い物をする経験は一般的なことですが、それを可能にしているのは、現実世界のあらゆるモノに関するデータがデジタル化され、サイバー空間でそれらがインターネットによって流通する仕組みによるものです。
これらは目に見えないことなので、具体的な仕組みや、そこで動いているデータの種類および量などを実感することは難しいですし、利用者はそのようなことを考えて利用していません。しかし、商品を選択し、代金を支払い、ものを受け取ることができるデータ活用の仕組みは、様々な場面で生活のありようを大きく変えています。
1990年代後半以降のインターネットの急速な普及と、2010年代からの現実社会のあらゆるモノがネットワークでつながるIoTの進展により、これまでデジタル化されることのなかったデータが大量にインターネットに流通する社会となりました。その結果、社会全体に流通するデータの量が加速度的に増え、あらゆる分野でこのビッグデータを利用し、そもそものデータに付加価値を付けて、サービスや生産性などを向上する仕組みが整備されています。このような社会を「データ駆動型社会」と呼びます。
データ駆動型教育とは
教育界においても、上記のような社会の変化に伴って情報のデジタル化とビッグデータの活用による変革が起きています。教育や児童生徒の学習に関わる情報をデジタル化して収集し、分析したものを蓄積して、教育内容や方法を修正し、改善していく「データ駆動型教育」が提唱され、国による施策として進められているのです。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、急ピッチで進められてきたGIGAスクール構想は、その具体施策の最たるものです。当初は、2019年から2023年の5年間で児童生徒1人1台のタブレット端末を配置する計画でした。しかし、コロナ禍が追い風となって施策実施を前倒しし、2020年度には児童生徒1人1台の学習端末と通信ネットワークの整備が始まりました。
これによって、理論的には児童生徒の学習履歴をデータとして収集・蓄積、分析し、個々の学習指導に活かす環境が整いつつあります。つまり、GIGAスクール構想はデータ駆動型教育を実現する第一歩の取組と言えるのです。

