提言|成田奈緒子(小児科医) 発達障害かもしれないと思ったら、教師がすべきこと 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #04】
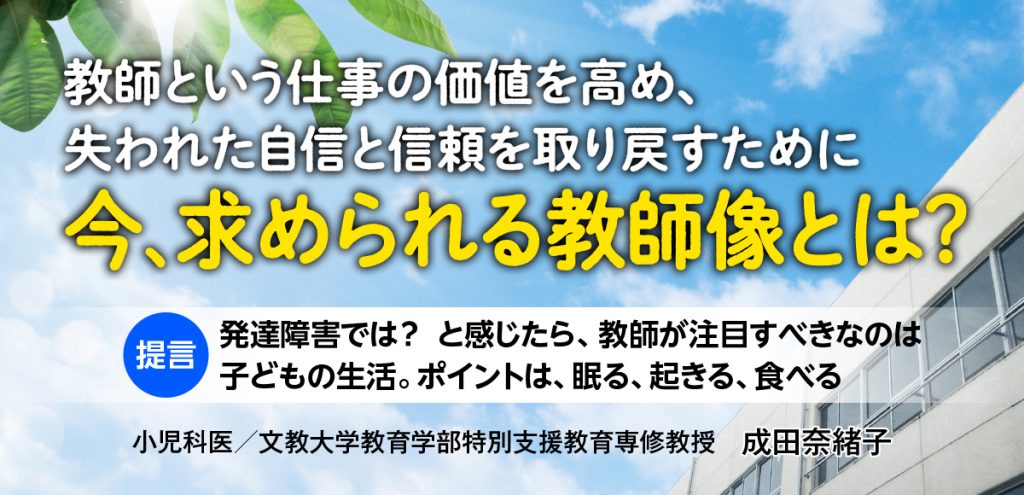
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第4回目です。今回は、発達障害の可能性のある子どもやその保護者への対応に注目します。教師に求められるのはどんな対応でしょうか。小児科医として長年、発達障害の親子に向き合ってきた、文教大学教育学部の教授でもある成田奈緒子さんに話を聞きました。

成田奈緒子(なりた・なおこ)
小児科医、医学博士。神戸大学卒業後、米国セントルイスワシントン大学医学部、獨協医科大学、筑波大学基礎医学系を経て2005年より文教大学教育学部特別支援教育専修准教授、2009年より同教授。2014年より発達障害、不登校、引きこもりなど、様々な不安や悩みを抱える親子・当事者の支援事業「子育て科学アクシス」を主宰。『「発達障害」と間違われる子どもたち』(青春新書、2023)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている
●提言|前田康裕 ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信
●提言|神内聡(弁護士) 分かり合えない保護者にどう対応するか
●提言|成田奈緒子(小児科医) 発達障害かもしれないと思ったら、教師がすべきこと(本記事)
目次
発達障害と「発達障害もどき」
近年、発達障害と呼ばれる子どもが急増しています。文部科学省の「通級による指導実施状況調査結果」を見てみますと、小中高校を合わせた、自閉症(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の子どもの数は、2006年の時点では、全国で約7000人でした。しかし、15年後の2021年には10万人を超えました。
私は小児科医として長年、発達障害をはじめとする子どもの脳の発達による問題に向き合ってきました。また、子どもの発達について研究する科学者でもあります。これまでにたくさんの臨床現場を見てきた私からすると、10万人の子どもたちのすべてが発達障害児だとはどうしても思えないのです。この中に少なくない数で「発達障害もどき」の子どもがいると確信しています。発達障害もどきとは、造語であり、医学的診断名ではありません。「発達障害の診断がつかないのに、発達障害と見分けがつかない症候を示している状態」のことです。つまり、10万人の中には、周りからは発達障害を疑われているけれども、実は発達障害ではないケースの子どもも含まれています。
では、なぜ元々発達障害ではない子どもが、発達障害もどきになってしまうのかというと、その原因は生活にあります。
子どもが一見、普通に学校に来て、授業を受けて、給食を食べて帰っているように見えても、その中身、生活は全然違っていたりします。
例えば、こんな子どもはいないでしょうか。その子は夜、十分に眠っていないのに、朝、無理やり起こされ、脳はまだ眠っている間に学校に来て、1時間目から机に突っ伏して寝ています。それを見た先生が「起きなさい」と注意すると、素直に言うことを聞くどころか、怒り出すのです。特に、低学年の子どもは社会性がないですから、反抗的になって「もういい!」と言って教室から逃げ出したり、「うるさい!」と言い返したりするわけです。そうすると、今は「発達障害かもしれない」と先生から思われてしまいます。しかし、冷静に考えてみれば、大人でも、睡眠不足で眠くてしょうがなくて寝ているときに、いきなり起こされたら、イライラして怒るのではないでしょうか。もしもこのような子どもがいたとしたら、発達障害の可能性もあれば、発達障害もどきの可能性もあるということです。
私は2005年から発達障害者支援センターで嘱託医をしています。そこに来る子どもたちが、薬を出さなくても、生活を改善してもらうことで、変わってくるケースがたくさんあり、その当時から、生活を変えることの必要性をずっと言い続けてきました。
先生方にまず、お伝えしておきたいのは、発達障害と診断がついている子どもも、発達障害もどきの子どもも、その様相は変わりうることです。今のこの子の状態が、一生涯続くわけではない、ということをまずは織り込んでおいてほしいのです。
もちろん、発達障害の特性としては治りません。生まれつきの遺伝的な要因は変わらないのですが、子どもたちは必ず発達します。発達障害の診断がある子どもも発達しますし、診断のない子どもも発達します。つまり、どちらの子どもであっても、今の問題行動と言われるものや、情緒の問題などがずっと続くのではなく、これが変わるような生活にしてあげれば、変わるのです。大事なことは、眠ること、起きること、食べること、これらを絶対に崩さないことです。これが基本になります。
眠ることで症状が改善されたAくん
私が主宰する「子育て科学アクシス」では、発達障害や不登校など様々な不安を抱える親子・当事者に対する支援事業を2014年から続けてきました。ここでは子どもの脳をよい方向に発達させていくにはどういう関わりをしたらいいかを親御さんに学んでいただいて、私たちも子どもと信頼関係を築きながら、長期間にわたって、一人一人の子どもの成長を見守っていきます。
例えば、Aくんは小さいときから周りの人とうまくいかず、いろいろなトラブルを起こしていました。お母さんの話によると、5歳ぐらいのときはADHDの特性が目立ち、手のかかるお子さんだったそうです。私が出会ったのは小学5年生のときですが、このときは、学力は高いけれども、他の子に比べて不安が高く、他の子が気にしないことも気にする面があり、ASDの特性にあてはまりました。しかし、私はその診断を本人には告げませんでした。その後も支援していく中で、Aくんは中学生になったころ、「自分は不安が高い。この不安は睡眠不足になると高まる」ことを自覚し、とにかく眠ることだけは絶対に崩さないように心掛けたのです。その結果、どんどん症状が改善されていきました。高校生になると、同級生が午前2時まで勉強していても、Aくんだけは夜9時には寝る生活を崩さず、十分な睡眠を取るようにしたため、非常に落ち着いて、今は国立大学に通っています。Aくんは大学生になって初めて、私に診断名を聞きにきました。私が丁寧に説明すると、自分の考えていたことと同じだと納得していました(※個人情報保護のため、多くの事例をもとに創作した架空ケースです)。
子どもを「発達障害」と診断することにあまり意味はないと私は思っています。子どもたちは発達中なのです。その集団の中でうまく適合しない行動があるときには、その行動を少しずつ発達の過程の中でよい方向に向けていくために、大人たちが何をしたらいいかを考えることが大切なのです。

