「創造性を民主化する」STEAM教育の本質は「つくる」ことにある【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #07】
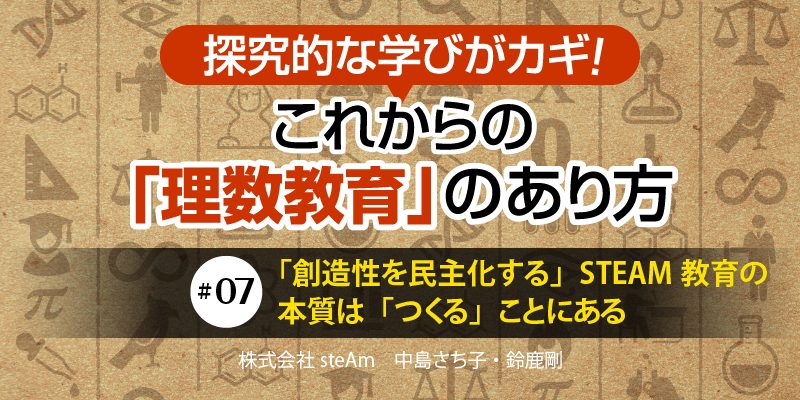
STEAM教育を通じて、「さまざまな境界を超えた心躍る共創(協奏)」や「多様な人や自然やAIとの豊かな共存」にあふれた、だれもがワクワクできるプレイフルな未来社会の構築をめざす株式会社steAm。代表取締役である中島さち子氏は、STEAM教育者であると共に音楽家・数学研究者など多岐のジャンルにわたって活躍している。今回は中島氏と、中島氏の思いに共感しともに活動する(株)steAmのメンバーである鈴鹿剛氏の両名に、日本の理数教育の現状や課題からSTEAM教育の可能性および実践のポイントまで話を聞いた。

中島さち子
音楽家・数学研究者・STEAM教育者。(株)steAm代表取締役、(一社)steAm BAND代表理事、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー、内閣府STEM Girls Ambassador、東京大学大学院数理科学研究科特任研究員。国際数学オリンピック金メダリスト。音楽数学教育とともにアート&テクノロジーの研究も進める。

鈴鹿剛
四国大学 経営情報学部 経営情報学科 准教授。(株)steAmでは、Earth School Architectを担当。2021年3月まで徳島県で高等学校教員も経験。PBLやSTEAM教育の実践に努め、ともに取り組む学校のネットワークを構築した。中島氏とは徳島県立徳島商業高校で教員をしていた際に、顧問を務めていたビジネス部との共同プロジェクトを通じて出会った。
この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の7回目です。記事一覧はこちら
目次
自分の手で作ってみることで、子どもたちの「やってみたい」を刺激する
はじめにお話しいただいたのは、steAm社のメンバーとして実際にSTEAM教育の実践にあたる鈴鹿氏。鈴鹿氏には、これまでsteAm社が行ってきたSTEAM教育の実践事例や、STEAM教育における指導のポイント、子どもとの向き合い方などについて語っていただいた。
鈴鹿氏によると、STEAM教育は子どもたち自身の「やってみたい」と思える気持ちが原点にあるという。
「STEAM教育は子どもたちの『やってみたい』を見つけ出し、その目標に向け、実現するためにはどうしたらよいのか、課題にあたったらどう解決するのかといったところからスタートします。自ら問いを立て探究することで、子どもたちの学ぶ姿勢はぐっと前のめりになります」
また、「やってみたい」という気持ちと併せて引き出したいのが「作ってみたい」という気持ち。調べ学習だけに止まるのではなく、その先にある「自分の手で作ってみる」という「主体性」および「創造性」を引き出せる仕掛けが重要であると語る。
「STEAM教育の“E”の部分、つまり『Engineering(工学・ものづくり)』につながる学習です。『SPACEBLOCK』というSTEAM教育に対応したマイコンボードや、『レゴ®マインドストーム® EV3』という動くレゴを活用した授業を通じて、作る楽しさや喜びを体験してもらいます」
●SPACEBLOCK
「自分で学び、自分で理解していく」というSTEAM教育に対応したマイコンボード。ブロックを組み立てるように、子どもたちの考えるイメージをもとに直感的なプログラミングが可能。
※マイコンボード:プログラム開発するために最低限必要なハードウェアをあらかじめボードに組み込んだもの。
●レゴ®マインドストーム ®EV3
マサチューセッツ工科大学と共同開発された教育版レゴ®。プログラミングおよびSTEMの授業に対応したリソースや指導案など教員をサポートするコンテンツも充実。
子どもたちは、これらのプログラミング教材を用いた授業および学習活動に夢中になって取り組むという。そして、長時間席に座って熱中する子どもたちの様子に、保護者や教員たちからも驚きの声があがるとのこと。
「通常の座学の授業だと、どうしても子どもたちが受動的になってしまいがちですが、実際にプログラミングを体験し、頭の中で想像していたことが形になると、『次はここを動かしたい』『この部分を光らせたい』という子どもたちの創作に対する意欲を引き出せます。そうすることで、子どもたちが自ずと問いを見つけ、課題の解決を図るようになります」
学ぶこと・作ることを循環させていくことで創造性を引き出す
STEAM教育をより具体的に知るために、steAm社がこれまで小学校などで取り組んできたSTEAM教育に関わる事例をいくつか紹介していただいた。
3Dプリンターや専門的な工具を使って、自分たちが使う椅子を制作(新渡戸文化小学校)
新渡戸文化小学校の5年生と高知県佐川町のデザイナーが協力して椅子をつくったプロジェクト。欲しい椅子のアイデアを一人ずつ形にするところからはじまり、工作用紙でのプロトタイプ作り→10分の1サイズのミニチュア模型を作成。専門家と相談しながら、子どもたち自身で仕様書も作成した。ものづくりはもちろん、社会の授業で林業分野を学んだり、高知県の林業やものづくりについてインタビューするために国語の授業でその手法を学んだりと、教科等横断的な学びを実現。
「p5.js」を活用して、ハンドベルの音楽を映像に翻訳する(玉川学園中学校・高等学校 ハンドベル部)
玉川学園中学校・高等学校のハンドベル部のみなさんが部活の中で行ったプロジェクト。葛飾ろう学校の小学生たちにハンドベルの美しさを楽しんでもらうために、初めてのプログラミングに挑戦。雪だるまやホタルなどの音楽にあわせて、雪だるまが飛んだりホタルが出てくる映像表現に取り組み、五感の演奏会を行った。一方、葛飾ろう学校の子どもたちも、音の特徴を振動と光で伝える「Ontenna(富士通)」とプログラミング言語「Scratch」を使い、音楽を双方向に視覚や触覚で楽しんだ。
※p5.js:アートやデザインの分野で広く使われているプログラミング言語。
鈴鹿氏によると、STEAM教育の実践では「学ぶこと・作ることを循環させていく」ことがポイントだという。
「子どもたちにとって、机の上だけでの勉強はどうしても飽きてしまいますし、試験のためだけの勉強だと実践したり応用したりといった、学習のその先にある力が身につきません。理論などを学び、実際のモノを試行錯誤しながら作る過程の中で創造力は育まれていきます」

