提言|前田康裕 ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #02】
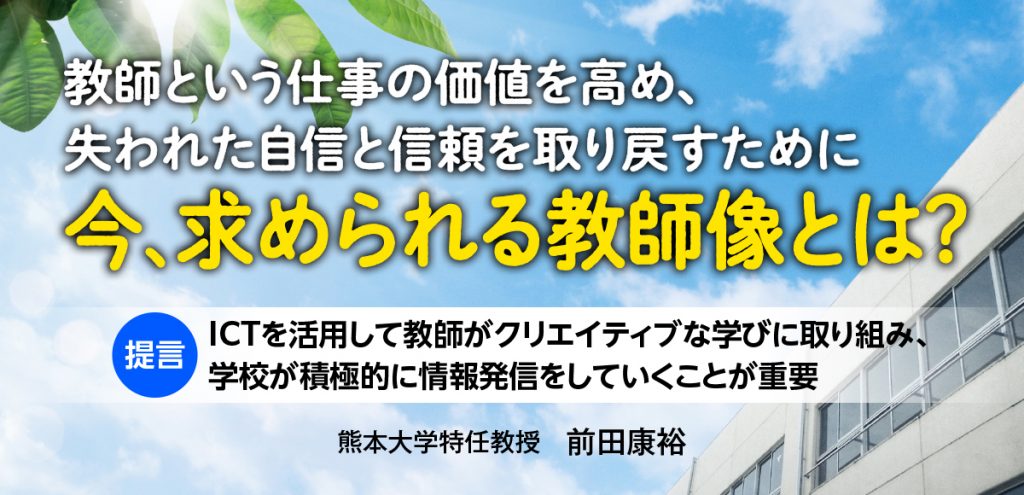
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第2回目です。今回は、1人1台端末時代に求められる教師の姿を明らかにします。『まんがで知る デジタルの学び』シリーズをはじめ、漫画家としても活動している熊本大学特任教授の前田康裕さんに話を聞きました。
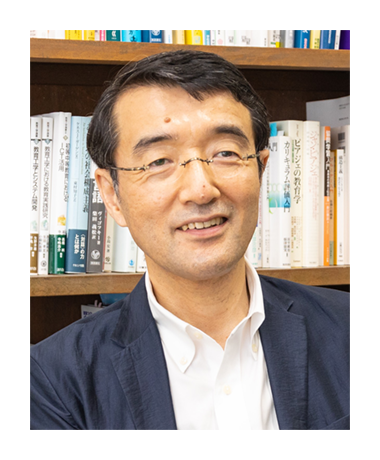
前田康裕(まえだ・やすひろ)
1962年、熊本県生まれ。熊本大学教育学部美術科を卒業後、教師となり、小中学校に25年間勤務。その間に、岐阜大学教育学部大学院教育学研究科を終了。熊本大学教育学部附属小学校教諭、熊本市教育センター指導主事、熊本市立小学校教頭、熊本大学教職大学院准教授、熊本市教育センター主任指導主事等を経て、2022年4月より現職。『まんがで知る 教師の学び』、『まんがで知る 未来への学び』、『まんがで知る デジタルの学び』シリーズ(さくら社)など、著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている
●提言|ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信(本記事)
目次
クリエイティブな学びにチャレンジする
基本的に教師の仕事は非常に自由度が高く、それぞれの先生方が自分の強みを活かしたクリエイティブな授業に取り組むことができると思っています。クリエイティブな授業と聞くと、何かの作品を作るような活動を想像しますが、子どもたちが持っているものを引き出すような授業だと考えれば良いでしょう。
例えば、国語の授業で詩を作るとします。多くの場合、子どもが教科書に書いてある詩を真似して書いているのではないでしょうか。そうすると、能力の高い子どもはとてもいい詩を作りますが、そうでない子どもはあまりいい詩が作れなくて、結局、「詩っておもしろくないな」と思って終わってしまいます。
本来、授業で行うべきことは、頭の中で詩を作ることではなく、実体験から得た感動を言葉にすることだと思うのです。私が教諭時代に行った授業は、詩を作るために子どもたちと一緒に、デジタルカメラ持って外に出かけるというものでした。子どもたちは葉っぱ、つらら、スズメなど、自然の中でいろいろなものを見つけ、触れたり、音を聞いたりしました。そうすると、子どもの中からいろいろな言葉が出てくるのです。子どもたちは興味を感じたものを写真に撮り、そのときに感じた、ガザガザ、ツルツル、ヌルヌルなどの言葉をメモに書いていきます。そして、教室に戻り、写真を見ながら、体感したことを思い出して詩を作るのです。できた詩は、写真とセットで発表し合います。

また、敬語の勉強をするときも、教科書に書いてある敬語や尊敬語、謙譲語をただ覚えてもあまりおもしろくありません。そこで、班ごとに敬語を教える番組の動画を作ってみることにしました。番組を作るには、どういう状況でどういう言葉を使うといいのか、どういう言葉が間違いやすいのか、といったことを子どもたちが考える必要があります。クラスに10班あれば、10通りの番組ができますので、それらをみんなで見て学び合えるのです。つまり、作りながら学ぶことができ、さらに、作ったもので学ぶことができるわけです。

もちろん、このような授業には賛否が分かれます。過去には、「国語の本質から外れている」と批判されたこともあります。しかし、時代は変化しています。今、子どもたちには1人1台の端末があり、テクノロジーを使ってクリエイティブに学ぶ環境が整っています。私たち教師も子どもたちと一緒に変化に対応し、学びを豊かにする学習にチャレンジしていくことが大事だと思っています。教師も子どもも楽しい、おもしろいと思える新しい授業を自由に考えていけることは、教師の仕事の魅力ではないでしょうか。
おもしろい授業で学力を向上させるコツ
一方では、「楽しい、おもしろい授業は結構だが、それで学力がつくのか」という心配の声を聞くこともあります。確かに、子どもがデジタルカメラを持って外に出かける授業では子どもたちは楽しんでやっていましたし、勉強しているようには見えなかったかもしれません。ただ、私が国語の専科教員をしていたとき、このような授業をしていたのですが、全国学力・学習状況調査での学力は向上したのです。
それはなぜかというと、対話を行いながら振り返り(リフレクション)を重視したからです。子どもたちは様々な活動をして、分かったことを振り返って言葉にまとめます。この「経験を言葉にする」という活動を毎日続けていくと、それが知識として蓄積されていくのです。
例えば、 詩を作ってみて分かったこととして、「手で触ると言葉が出てくることがわかりました」と子どもが振り返りの時間に書いたときに、子どもの中には「いろんなものを感覚で感じ取って言葉にすることが大事なんだな」ということが知識として蓄えられていくわけです。
逆に、きちんと活動を振り返らせることをしないと、ただ「今日は楽しかったです」という感想で終わってしまい、知識にはなりません。
つまり、対話を繰り返しながら経験を振り返って学び、知識にすることで、子どもは学び方を身につけていくのです。このポイントを押さえていれば、楽しい、おもしろい授業が学力向上につながると考えています。
もちろん、子どもの中には自分で何かに「気づける子ども」と「気づけない子ども」がいます。だからこそ、学びを共有するのです。「気づける子ども」の考えをデジタルで共有したりすることで、「そうか、こういうふうに気づけばいいんだ」と他の子どもたちもわかっていきます。このように学びを共有することで、クラス全員の子どもの気づきの質が高まることになり、結果として学力が向上すると考えています。

教師の仕事は、本来、創造的な仕事だと思っています。子どもにしっかりとした学力がつけば、授業の内容をどうするかは、それぞれの教師が自由に考えていいからです。それぞれの教師が得意とすることを生かし、おもしろい授業、クリエイティブな授業にどんどん取り組んでいくと、自分の強みをどんどん伸ばしていくことができるのではないでしょうか。私にとっての強みは漫画やイラストだったので、それを生かした授業をしたり、教材をつくったりしてきました。それが現在の漫画家としての活動につながっているように感じています。
先生方が、自分が考えた教育実践や教材などを積極的にアウトプットすることで、自分自身の成長も実感できると思います。自分が何かを創り出し、それが周囲の役に立つことで自己肯定感が高まり、教師の仕事の魅力をさらに実感できるでしょう。それは、クリエイティブ・コンフィデンス(創造力に対する自信)と呼ばれ、「自分には周囲を変える力がある」という信念を意味します。多くの力ある教師がクリエイティブな授業を通じて、子どもたちと共に成長し、豊かな学びの場を提供していけることを願っています。

