「神無月と『スビバセンおじさん』」全校朝会【校長講話】文例集 #6

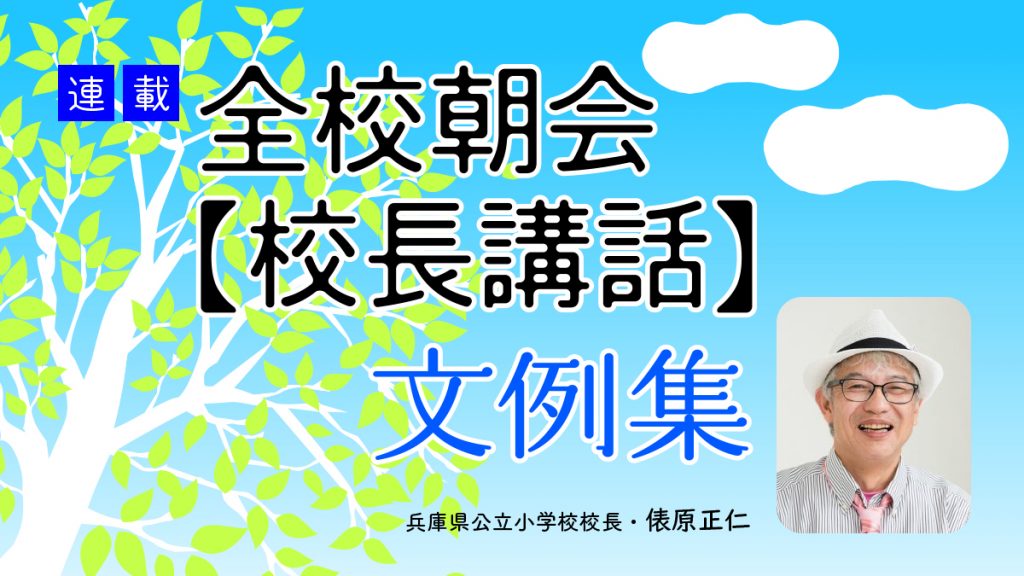
全校朝会での校長講話といえば、校長先生にとって腕の見せどころです。とはいえ、毎月、子供たちの知的好奇心を掻き立てたり、子供たちの心を整えたりする内容を考えるのは苦労するもの。そこで、本連載(月1回公開、全11回)では、学級経営や学校経営に関する多数の著書をもつ俵原正仁先生が、実際に使用したスピーチの全文を公開します。10月は講話「神無月と『スビバセンおじさん』」を取り上げます。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
10月のテーマはこう選ぼう
学級崩壊が起こりやすい月の1つに、11月があります。ただ、これは、11月になって突然学級が崩れるということではありません。実は、前月である10月にじわじわと学級が崩れ始め、崩れが大きくなった11月に初めて気付くのです。
学級を崩壊させるその兆しを、私は「崩壊フラグ」と呼んでいます。学級崩壊を起こさないためには、その崩壊フラグを見付けて対処するか、崩壊フラグそのものが立たないようにしなければいけません。崩壊フラグが起こる理由の1つに、物事を悪く捉えてしまうマイナス思考があります。
そこで、10月の全校朝会は、プラス思考のもち方についてお話をします。今回のキーワードは「立ち位置」です。
10月の講話「神無月と『スビバセンおじさん』」全文
いきなりですが、クイズです。(映画『となりのトトロ』に出てくる姉妹のイラストを見せながら)この子たちの名前を知っていますか?
(子供たちから「サツキちゃん」「メイちゃん」などの声が上がる)(※1)
正解! よく知っていますね。サツキちゃんとメイちゃんです。二人がトトロのいる家に引っ越してきたのは5月だそうです。
5月のことを英語で「メイ」といいます。メイちゃんの「メイ」です。さらに、サツキちゃんの「サツキ」という言葉も、実は5月のことを表しています。サツキ(皐月)というのは、和風月名(※2) と呼ばれる、日本風の月の呼び名です。「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「皐月」…聞いたことがある人もいるんじゃないかな。サツキちゃんとメイちゃんは、5月生まれなのかもしれませんね。

ちなみに、10月は「神無月」と言います。
昔は「な」が今でいう「の」の意味だったので、「神の月」という意味で「神な月」と言われていたという説があります。
でも、次のような説もあります。「10月には、日本中の神様が島根県の出雲大社に集合するので、日本の多くの地域で神様がいなくなるから」というものです。神様がいなくなるから「神の無い月」で「神無月」ということです。
ここで校長先生は、あることが気になりました。それは島根県です。日本中の神様がやってくる島根県では、10月のことを何と呼ぶんだろうと思ったのです。島根県には、日本中の神様がいるんですから、神無月ではおかしいですよね。
そこで、調べてみました(※3)。 島根県では、神様がやってくるので、神様がいるという意味で「神在月(かみありづき)」と言うそうです。同じ、10月でも、その人がいる場所によって呼び方が違ってくるということです。おもしろいですね。
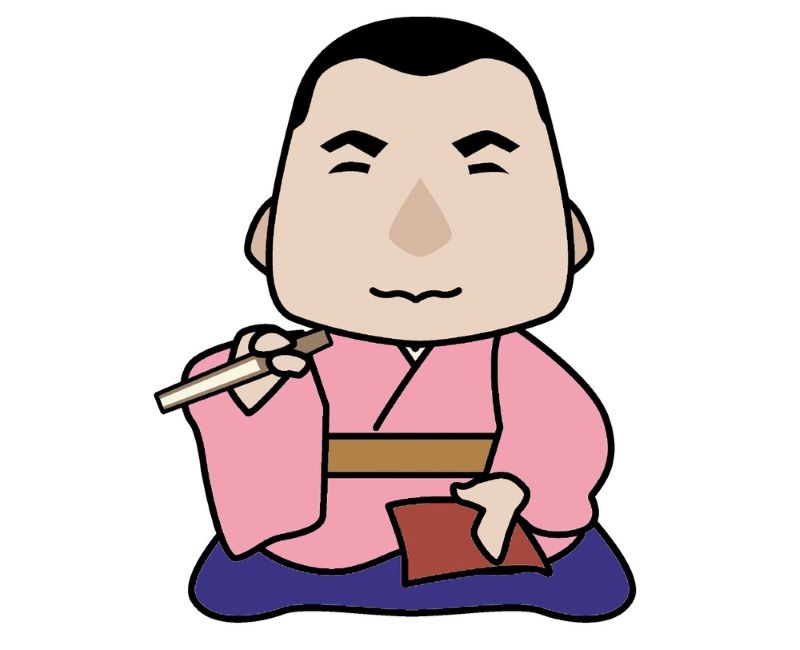
今日は、もう一つお話をします。
落語家の桂枝雀さんの持ちネタの1つに「スビバセンおじさん」という小話があるのですが、そこに「山のあなた」という詩を話題にしたものがあります。次のような詩です。
山のあなたの 空遠く 「幸い」住むと 人のいう
噫(ああ)われひとと 尋(と)めゆきて 涙さしぐみ かえりきぬ
山のあなたに なお遠く 「幸い」住むと 人のいう
作/カール・ブッセ 訳/上田敏
昔の言葉の詩なので、ちょっと難しいですね。「山の向こうの遠い空の彼方まで行けば、『幸福』があるのだと誰かが言っている。ああ、私も人と一緒に山の向こうまで行ったけれど、『幸福』が見つからずに涙ぐんで帰ってきた。でも、山の向こうのもっともっと遠い空の彼方まで行けば、『幸福』があるのだと誰かが言っている」という意味です。
この詩を聞いて、ある男の子がスビバセンおじさんに質問をします。
男の子「おじさん、『山のあなたの空遠く 幸い住むと人のいう』と言いますね(※4)」
おじさん「うん」
男の子「山のあなたまで行かないと、幸いはありませんか?」
おじさん「いや、ここにもあるよ。山のあなたの空遠くから見たら、ここが山のあなたの空遠くだから」
桂枝雀「スビバセンおじさん」より
「山のあなたの空遠く 幸い住むと人のいう」という言葉を聞いて、山を越えて遠く離れた場所まで行かないと幸せはないと思う人もいれば、スビバセンおじさんのように、山の向こうの人から見れば、今自分のいるところが山を越えて遠く離れた場所なので、ここに幸せがあるはずだと考えることができる人もいるということです。
桂枝雀さんは、幸せについて次のように考えています。
「幸福な人間がいるのではない、幸福とは服を着て歩き、向こうからやってくるものではない、今ここにいて、自分を幸福だと思える人間と、思えない人間がいるだけだ」
スビバセンおじさんのような考え方って、すてきだと思いませんか? 同じ言葉を聞いてもその人の考え方によって感じ方が違ってくる。幸せは自分の心の中にあるのかもしれません。
今日は、「神無月と神在月」と「スビバセンおじさん」の2つの話をさせてもらいました。見方や立場を変えることで、言葉や意味が変わってくるというお話です(※5)。
これで校長先生の話を終わります。

