授業づくりと学級づくりは表裏一体 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第21回】
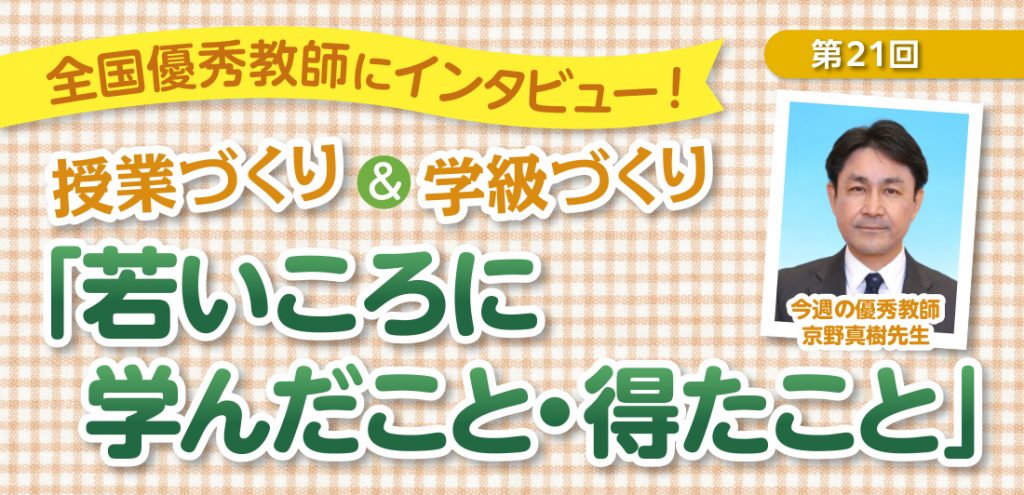
前回、京野真樹先生が、初任校や附属小学校勤務時代に、その後の教職人生に大きな影響を与えてくれた上司から学んだことを紹介しました。最終回となる今回は、秋田県の教育専門監(小学校·国語)から指導主事、そして附属小の副校長として取り組んでいることなどを通して、全国の若い先生に伝えたいことを紹介していきます。

目次
どのような子供や学級に対しても通用する手法を追究した教育専門監時代
附属小学校での勤務後、平成20年度に秋田県の教育専門監に任命されました。教育専門監という制度は、各教科等における児童及び教員への指導支援を通して、子供の学力向上及び指導力向上に資することをねらいとしています。その仕事につくにあたり、附属小学校時代までに学んだことを再整理し、再構成して周囲の先生方に伝えていこうと考えました。ただ、「過去の経験ばかり語っている」と思われるのはよくないので、新しい学習方法を取り入れ、挑戦することで、実践者としての懐を広げる努力も継続しました。
例えば「動作化」や「劇化」によって、子供たちの心に潜在的に眠っている解釈を引き出す手法を取り入れることについては、この時期、特に力を注ぎました。斎藤喜博先生が島小学校時代に体系化した組織学習にも挑戦しました。これは、子供一人一人が問いを設定し、個別の課題追究を経て、課題別のグループや学級全体での課題追究、そして再びグループや個人に還していくという手法です。附属小時代にも何度か試みたのですが、これを機会にしっかり学び直した上で取り組みました。
こうした挑戦に向かったのは、一斉指導以外の指導力を磨かなくては、子供たちそれぞれに合った学習スタイルに向き合うことができないという危機感をもったことも大きな要因でした。その背景には、発達障害などに起因する困り感を抱えた子供が、どこの学校でも増加傾向だったという状況があります。多様な困り感を抱えた子供たちも巻き込んで授業をするにはどうすればよいか、が当時の自分の問題意識となっていました。どのような実態をもつ子供や学級に対しても通用する手法を追究することが、当時の私にとって急務だったのです。
私は、若手の頃から少しはみ出した子供たちを大事にしてきました。その子たちも、困り感を抱えるというほどではなかったものの、いわゆる学力の高い子供とは異なる感じ方や考え方をすることで、私と出会う以前は教室の中心に置かれたことのない子供たちでした。そんな若手時代の取組を、よりいっそう自覚的にし、全ての子供たちの個性を生かした授業づくりをしていくにはどうすればよいかを考えました。この10数年前のことが、今言われている「個別最適な学び」ということにも通じるように思います。
例えば、4年生の教科書教材「一つの花」で、お母さんが幼いゆみ子を連れて、出征するお父さんを駅まで見送りに行く場面を取り上げた学習では、「劇化」の手法を取り入れました。ゆみ子役の子供が「おじぎり、一つだけちょうだい」と言っておにぎりをねだるのですが、大概の子供は一度しかその演技をしません。一方で「『みんな食べてしまいました』って書いてあるから、1個じゃないでしょ」と気付く子たちも現れます。そこで子供たちの間に、「結局、ゆみ子はおにぎりをいくつ食べたの?」という問いが生じるのですが、「1個でしょ」と答える子供たちが多いので、「どうして?」と問い返すと、「だって、大事なお米でおにぎりをいくつも作れるわけないじゃない」という反応が返ってきます。「戦争に行くお父さんには、1個じゃ足りないよ」と理由を述べる子もいますが、「お父さんのために作ったおにぎりじゃないでしょ。おにぎりはお母さんのかばんに入っていたって書いてるよ」と捉え方は様々です。こうした学習過程で、子供たちは改めて文章を読み直すようになり、お母さんのかばんにおにぎりと一緒に入っている包帯やお薬、配給のきっぷの意味に気付き、どうやらお父さんのためというよりは、空襲などの緊急時に備えたものであることや、お米で作ったおにぎりだけは、家族で食べる最後の食事になる可能性をもつことなどが明らかになっていきます。そして、お母さんがいったいどんな思いでおにぎりを作ったか、という物語の深層部分について言及し始める子供たちが増えていきます。
「おにぎりはいくつ?」という視覚的で具体的な問いは、どのような子供にとっても参加しやすく、考えることができるものです。入り口は浅いけれども、奥行きのある問いを引き出す仕掛けとしての「劇化」、その過程で自覚される物語の「設定」や「人物描写」などの「言葉による見方・考え方」。教科内容と教材内容の両面から、全ての子供が、それぞれの学び方で資質・能力を身に付けていくきっかけを生み出すことができます。こうした授業づくりを心がけていくうちに、問いが視覚的かつ具体的であればあるほど、困り感をもった子供たちのほうが活躍するということが分かってきました。そして、私が追究してきたこのような授業スタイルは、ユニバーサルデザインの条件を満たしていたことに気付いたのです。そこから、さらに特別支援教育の視点を意識して授業づくりをすることで、子供たちが、多様な言語活動を通して教材のより深い部分に気付くことができるようになっていきました。
本来、国語の授業づくりでは中核的な位置付けをされてこなかった「劇化」や「アニマシオン」など、即興性や遊びの要素のある手法によって、様々な特性や個性をもつ全ての子供たちが楽しく学びに向かえるような授業を追究したことが、自分の授業の根幹を太く、豊かなものにしてくれたと思っています。

授業のスタンダードの背景には、教育に対する理念や哲学がある
教育専門監としての4年間を終え、私は県教育庁中央教育事務所の指導主事になりました。実際に授業をする機会は減ってしまいましたが、学校現場の先生方が日々、どんな意識をもって仕事をしているのかをつぶさに見る経験は、得がたい学びの機会となりました。
少し距離を置いて授業や学級·学校を見るようになって改めて感じたのは、「やはり授業が学級づくりの根本だ」ということです。初回で話したように、初任の頃は、学級経営を改善することがよい授業づくりの基盤だと教えられ、自分もそれを信じていました。ところが様々な学級で様々な先生方が日々の授業づくりに取り組む姿を拝見するうちに、子供たちが授業の中で満足できず自己実現の機会がもてなければ、一人一人の居場所づくりも学級の人間関係もうまく機能しないという当たり前のことに気付きました。
今でも、生徒指導という言葉を、問題を起こした子供への早期対応や放課後の教育相談のような、授業以外の要素として考えている先生は少なくないと感じます。しかし、そもそも生徒指導は授業で機能させ実現するものです。学校生活の8割以上を占める授業の中に「自己決定·自己存在感·共感的人間関係」などの機能をもたせることが、問題行動や不登校などを未然に防ぐことにつながるため、私は指導主事の頃から「授業づくりと学級づくりは表裏一体」という言葉で伝えてきました。
この視点から改めて自分自身の取組を見直してみると、学級からはみ出してしまう子供や普通とは異なる発想をしている子供たちを大事にしてきた自分の授業づくりの姿勢が、なぜ学級経営としても機能していたのかが改めてよく分かってきました。初任時に学級経営に苦労したと言いながら、学級崩壊のような大崩れをすることがなかったのも、学生時代に授業づくりの基本となる足腰を、大内善一先生や斎藤喜博先生、武田常夫先生から学ぶことで鍛えてもらっていたからでしょう。そこから、特別な困り感をもっている子供たちとの出会いや、そういう子供たちに肩入れしたくなる私の好みがうまく機能して、多くの子供たちが楽しめる国語の授業を目指していたことが大きかったのだと思います。
実際に自分自身、そんな工夫をし、手応えを感じた授業の記録を見直してみると、生徒指導が機能していたと感じられる実践がありました。子供が授業の中でそれぞれ目的をもち、役割を自覚して学び、手応えが得られる授業を目指していれば、子供たちが安心できる居場所や人間関係に支えられた学級づくりにつながっていくのだと思いました。
こうした姿勢は例えば、秋田県で国語授業のスタンダードとしている「授業のめあてを書く」といったこともあまりしない自分の授業スタイルによく表れていました。私の授業を参観されたある先生に、「なぜ、めあてを板書しないんですか?」と尋ねられたことがあります。このときに、私がお話ししたのは、重要なのは子供が授業者のねらいを自覚し、そのねらいを納得して学びに向かっていたかどうかであって、めあてを板書するという表層的な約束事が大切なわけではないということです。先生が「めあて」を板書したとしても、子供の中に意識されていなければ、それは単なる「先生のめあて」にすぎません。
一般に授業のスタンダードとして広く周知されている手立ては、その背景にどのような教育に対する理念や哲学があるのかを考えて授業に取り入れたいものです。「学びにくさを抱えた子も学びたいし、分かりたい。そんな子供たちも学びたくなる、学べる授業をつくるために、ここをこう工夫する」という考え方が、スタンダードと言われている手立ての背景には必ずあります。私はそのような教育に対する理念を、導いてくださった先生方から知らず知らずのうちに学び吸収していたのではなかったかと、今さらながらありがたく感じています。
大学時代の大内善一先生、初任校の頃の石井憲輔校長、そして、附属小の副校長だった濱田純先生から、学級経営や授業づくりの手立てを通して、子供をどう見とり、可能性を引き出すかについて学んでいきました。このような出会いのおかげで、教員になってからの17~8年間で、今の私の教育に対する考え方の基盤が形づくられてきたと思います。

