自然災害に負けない小学校になるため、考えよう、防災教育

9月1日は防災の日で、防災について考える日です。皆さんは、防災教育をどのように進めていますか? 恐らく、様々な災害を想定した避難訓練を年間指導計画に沿って進めていると思います。
しかし、避難訓練だけで、果たして十分と言えるでしょうか?
近年、毎夏の猛暑や大雨洪水はもちろんのこと、さまざまな自然災害が頻発しています。いつ子どもたちに災害がふりかかるか分からない状況です。
そこで、今回は、「子どもたちの命を自然災害からどう守るか」をテーマに考えてみましょう。
【連載】タバティのLet’sスマイル(レッツスマイル) 学校づくり #07
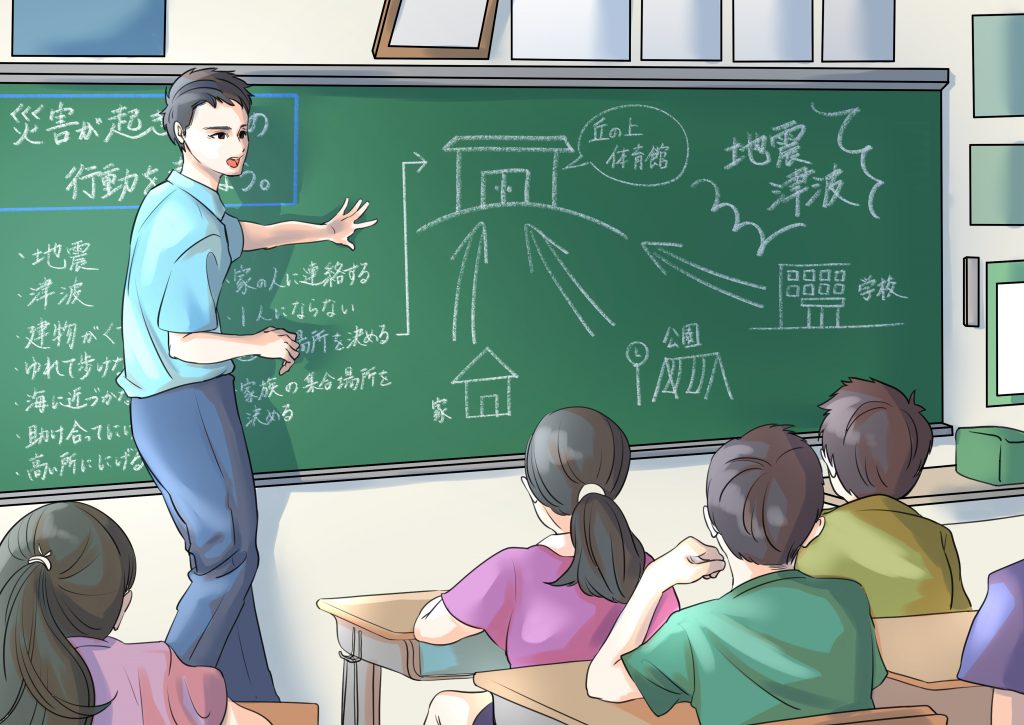
目次
被災地に立って
私の防災教育を考える機軸は、2011年に起きた東日本大震災で、多くの犠牲者を出した宮城県石巻市立大川小学校です。この大川小学校には、今までに夏休みを利用して3度、足を運んでいます。
「もし自分がこの大川小学校の校長なら…。もし亡くなった子どもたちが自分の学校の子どもたちなら…」
そう考えたことがきっかけでした。
そして、
「地震や自然災害が起きたとき、最終判断者の校長として、自分ならどう決断するだろうか?」
という、自分に対する問いかけへの答えを見つけるため、実際に大川小学校のグランドに立って考えたかったのです。
訪問を重ねるごとに、残された建物の劣化が緩やかに進み、その一方で犠牲になった子どもや住人の名前が刻まれた慰霊碑が新たに建つなど、景色の変化に時間の経過を感じます。
しかし、いくら時が過ぎようとも、
「やはり、あのとき、校舎の裏山に逃げれば助かったかもしれない」
「しかし、小さな子どもたちや地域のお年寄りもいた中で、その判断が果たしてできただろうか?」
と、変わらぬ痛恨の念を抱きます。
私は、やりどころのない悲しみと無念さを覚えながらも、この場ではただ、静かに手を合わせることしか出来ません。
二度と同じことを繰り返さないために。教職員一人ひとりの当事者意識を育て、子供たちに自然災害等についての予防教育を進めていくことが、残された者たちにできる、犠牲者へのせめてもの手向けだと考えるしかありません。そして、自分にできることをするしかありません。
「学校はどんなことがあっても、なんとしてでも子どもの命を守らねばならない」
と決意を新たにして、私は帰路につくのです。
「正常性バイアス」の罠にはまらないために
人間には「正常性バイアス」という認知特性があります。非日常的な事態が起こったとき、「何かの間違いだ」「自分だけは大丈夫だ」などと考えてしまいがちで、決定的な行動の遅れを生じさせてしまうことが往々にしてあるのです。だからこそ、大人も子どもも、日頃から災害に対する想像力を育てる訓練が必要です。災害時に自分で状況を判断し、どのように避難し、どう命を守るか? このように考えられる力のことを「災害イマジネーション力」と言います。
この力を育成するために、「目黒巻」と呼ばれる、東京大学教授・目黒公郎氏開発の防災思考ツールを活用することを強くお勧めします。

