提言|田中博之 授業に関する業務をスリム化するには? 【緊急検証! 教員のなり手不足問題、私はこう考える! #4】
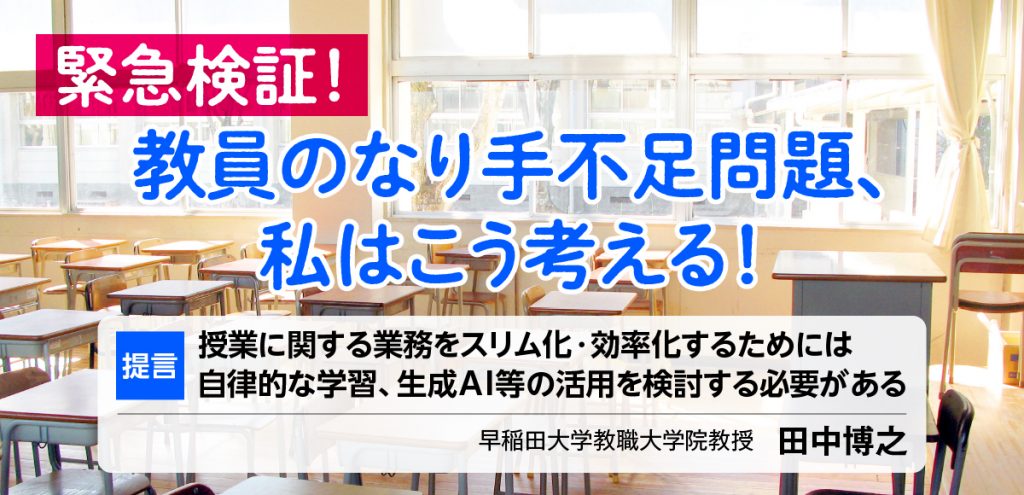
教員のなり手不足問題は深刻であり、日本の学校にとってその解決が目下の急務です。現在、文部科学省が進めている働き方改革や給特法に関する議論は確かに重要ではありますが、果たしてそれだけで解決となるでしょうか。教育関係者がその他にできること、するべきことは何かを考える7回シリーズの第4回目です。今回は、授業に関する業務をスリム化する方法を探ります。これまでに全国のたくさんの学校の授業開発に関わってきた早稲田大学の田中博之教授に話を聞きました。

田中博之(たなか・ひろゆき)
1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。2007~2018年度、文部科学省の全国的な学力調査に関する専門家会議委員。現在、21世紀の学校に求められる新しい教育を作り出すための先進的な研究に取り組んでいる。『NEW学級力向上プロジェクト』(共編著、金子書房、2021)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは?
●提言|川上康則 学校や教員が、今すぐ考えたい5つのこと
●提言|赤坂真二 大学と学校は今、何を変える必要があるのか
●提言|田中博之 授業に関する業務をスリム化するには?(本記事)
目次
なぜ学習内容を減らせないのか
文部科学省が進める業務改善や「働き方改革」は大事なことですが、授業に関係する業務もスリム化・効率化しないと、教員の負担は軽減されず、学校のブラック状態は続き、教員のなり手不足は改善されないように思います。
授業に関係する業務をスリム化しようとすれば、「学習内容を減らせないのか」という話が出てくるでしょう。私は個人的には、育成すべき資質・能力が明確であれば学習内容を減らしてもいいのではないかと考えますが、過去の流れからいって、それは簡単にできることではないのです。
忘れてしまった方も多いかもしれませんが、今から40年前、1980年ごろにも、「カリキュラムの内容をスリム化しないと、子どもにも教員にも負担が大きい」と、同様の議論が起こりました。その結果、いわゆる「ゆとり教育」が行われることになり、小学校、中学校、高等学校の学習内容を減らし、一方で総合的な学習の時間など、生きる力を育む工夫を取り入れた教育を行ったのです。しかし、2010年ごろ、減らした学習内容は、元に戻されました。その後は探究的な学習や「主体的・対話的で深い学び」など、より高度な学習方法で教えることになり、プログラミング教育も始まりました。補助教材の内容が増え、教科書は以前に比べて厚くなり、結局、学習内容は年々増えているのが現状です。
世界的な「カリキュラムのオーバーロード問題」の議論を受けて、2023年2月には中央教育審議会の部会が「学習内容の重点化」を検討課題に上げました。文部科学省はこの問題を認識しています。それならなぜ、学習内容を減らせないのかというと、「ゆとり教育」をやめるという決断には、政治が関わっていたからです。政治家たちが議論をして決めたことですので、そう簡単に方針を変更できないのです。しかも、「子どもにもっと勉強させ、学力を向上させよ」という要望は、優秀な人材を確保したいと願う経済界からも出ています。
2018年に実施されたOECD生徒の学習到達度調査(PISA)の結果を見てみますと、調査の対象は高校1年生ですが、参加した79の国・地域の中で、日本は「読解力」で15位、「数学リテラシー」で6位、「科学リテラシー」で5位となり、いずれも前回の2015年調査よりも順位・スコアが後退しました。諸外国と比較すると、「学力が高い」とは言えない状況なのです。
こういった様々な事情があり、「学習内容は減らせない」という政治の世界、経済界からのプレッシャーがあるのです。それでも変えようと思ったら、両方の団体の人たちをまずは説得しなければならないので、次の2030年の学習指導要領の改定には到底間に合いません。
ですから、学習内容は当分、減らないでしょう。それならば、教員の数を増やしてもらいたいところですが、現状ではそれも難しいわけです。そうなると、教員のなり手不足問題を解決するには、今の学習内容はそのままでも、教員の負担を軽減するために、学校は授業に関係する部分で何ができるのかを、改めて考える必要があります。
今後注目したい2つの授業スタイル
まず、どんな授業をするのかについて、私は2つの提案をします。1つ目は、自律的な学習(Autonomous Learning:オートノマス・ラーニング)です。これは、自分の学習を学習者自身が管理するタイプの学習方法です。
以前、アメリカのシリコンバレーの近くの小学校で行われている様子を参観したことがあります。その学校では、朝8時半ごろ、子どもが教室に入ると、黒板にその日、何を学ぶのかが書いてありました。例えば、社会科は教科書の何ページから何ページの〇〇について、音楽は教科書の何ページの△△という歌を歌う……など、大きな項目が5つぐらい、挙げてあったのです。音楽と体育、理科の実験などは、どこでもできるわけではないので、授業の時間が決められていますが、それ以外の教科は、子ども自身が、いつ、どこで、誰と、どんな教材や道具を使って学ぶのかを決めます。子どもが朝、自分の1日の学習計画を立て、ノートに書き込み、実行していくのです。もちろん、すべての子どもがその計画通りに1日を過ごせるわけではなく、ソファーで寝ている子どももいましたし、先生が時々しか教室に回ってこないので、悩んでぼーっとしている子どももいました。この学習方法は個人差が出ますし、教科書が最後まで終わらない可能性もあります。
それでも、自律的な学習が重視されているのは、自己マネジメント力や計画力、自律的に学習に取り組む態度、計画通り学習ができたかを自己評価する力を育み、自己管理、自己調整ができる人間を育てることが重要だと、この地域の学校では考えているからです。
自律的な学習は、単に教科書を使って自分で予習や復習をする、というレベルではなく、主体性、自律性、自己マネジメント力が求められます。これらは非常に高度な能力ですので、中にはついていけない子どもも出てきます。そのため、シリコンバレーでも全ての学校で自律的な学習が行われているわけではありません。ですから、この学習のシステムを日本の全ての小中高等学校に導入するのは無理な話ですが、例えば、週3回、午後の2時間だけなど、部分的に導入することは可能なのではないかと思います。ただし、グループディスカッションで合意形成をする方法などは、自律的な学習で学ぶことはできませんから、やはり協働的な学びが授業の中心となります。
学校で自律的な学習を進めるためには、教員が最初に、そのための教材やガイドブックをつくる必要がありますし、やり方を教えなくてはなりません。ただ、一回システムを作り、ある程度、子どもが慣れてくると、後は自律的に動けるようになります。そうなると、教員の仕事は、個別対応が必要な子どもへのアドバイスや振り返りの支援などとなります。もちろん、自律的な学習を進めていく子どもたちを放置するのではなく、放課後にノートや、タブレットでの学習データの履歴をチェックする必要はありますが、それでも、自律的な学習を部分的にでも取り入れると、教員は一日中ずっと授業をし続けることから解放されます。その時間は非常勤の講師や教育実習生などに教室にいてもらい、担任は職員室で教材研究などができるのです。
提案したい授業スタイルの2つ目は、1人1台のタブレットと生成AIを活用して自律的な学習をすることです。そもそも生成AIとは、学習データから文章、画像、音声などのコンテンツをアウトプットしてくれる人工知能のことです。子どもたちは、すでにタブレットでAIドリルに取り組んできていますが、生成AIを使えば、児童生徒が「問題を作って」と指示すれば、問題を出してくれますので、もっと高度なことができるようになります。
これについてはまだ研究段階ですが、今後タブレットで生成AIを使って、個別最適な学びを自律化することが可能になるかもしれません。その際、大事なのは個別最適な学びをするために、自律的な学習をどのように生成AIが支援していくのかです。先ほど申し上げたように、計画力、自己評価力、自己マネジメント力などの育成を組み込んだものを自律的な学習と呼びますので、現在一部の学校で行われている自由進度学習とは区別して考える必要があります。結果的には自由進度学習に近い形になりますが、自由進度になるのは結果論であり、学習の様子の一側面ではありますが、それが目的ではないからです。
近い将来、AIを用いた応用問題のアプリ、AI英会話トレーニングのソフトウエアなども出てくると言われていますので、その場合の教員の役割はそういったアプリやソフトウエアの使い方をマスターし、うまく使いこなせない子どもに対してアドバイスをすることです。
これも、例えば、週2回、午後の1時間だけなど、部分的に導入することは可能なのではないかと思います。タブレットと生成AIを使って、自律的な学習を行うことで、どのような面で教員の負担軽減につながるかは、今後、検証していく必要があると考えています。

