知らない地域で特色ある教育活動をつくるには?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #5

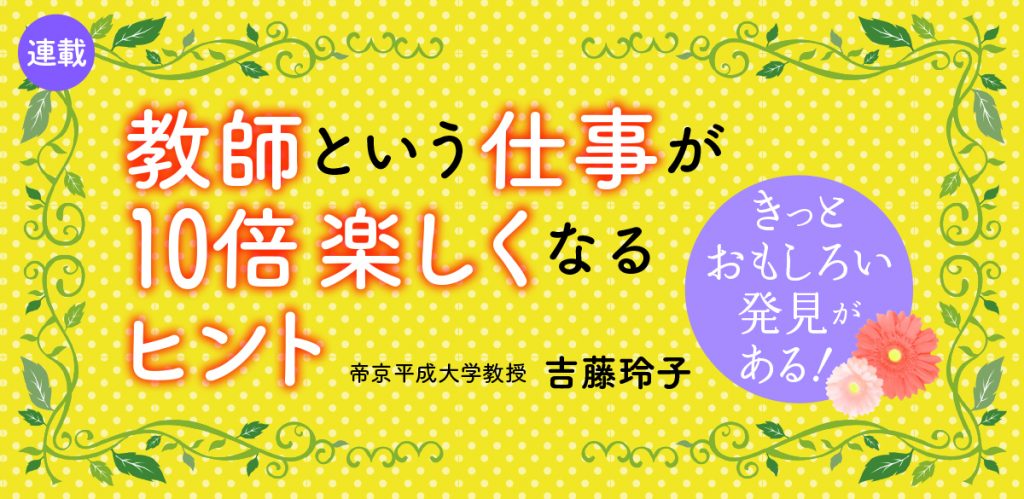
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの5回目のテーマは、「知らない地域で特色ある教育活動をつくるには?」です。地域行事も多く、生活指導も大変だという噂も入ってくる地域に異動になったときはどうするか? 地域の特色を生かした教育活動につなげるコツが分かる話です。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
知らない地域で人々と関わるために
公立小学校の教員にとって異動はつきものだということは前回で述べました。私たちは、異動先の勤務校が決まった所でどのようにその地域に関わっていけばよいのでしょうか。
副校長で知らない地域に勤務することになった私は、次はできれば経験がある地域で仕事をしたいと願っていたのですが、校長に昇任し、さらに遠い学校へ異動となりました。空港に近い学校です。異動が決まったとき、空港近くの学校だと、騒音はうるさくないのか、通勤の電車は旅行客でいっぱいではないのか、しかも創立110周年で初の女性校長、地域行事も多く、生活指導も大変だという噂も入ってきていて、不安でいっぱいな気持ちになりました。
校長としての昇任への喜びよりも不安のほうが増していたのです。地域の会合では、役所の方から「女性が配置されるとは驚きました」と言われました。春休みに学校に来ていた6年生が、下駄箱の私の名札を見て、「今度の校長は女か」と言って、職員から注意されたというエピソードもありました。それぐらいその地域に女性の校長が着任するというのは話題になっていたのです。
しかし、着任してすぐに、とてもおもしろい地域であることが分かりました。とかく私たちは、噂に惑わされやすいのですが、どんな地域も実際に行ってみなくては分かりません。着任して、私はすぐに学校の課題を整理しました。なんと言っても、まず生活指導、次に学力向上でした。その課題に取り組んだ後、この地域でも“Think Globally, Act Locally” の精神で地域と関わり、学校の特色を生かした学校経営を行いました。

まずは落ち着いた雰囲気づくりから
公立小学校でありながら、学校名を伝えると、「名門校ですね」と言われたり、「大変ですね、問題ありませんか」と言われたりすることがあります。全国どこでも税金で運営されているのが公立小学校です。本来であればそこに格差が生じるのはおかしいのですが、一律にいかないのが現状です。
山の手の地域にある、歴代有名な校長が勤務している、長い歴史があるなど、「よい学校」と言われる背景には、様々な要素があります。でも、一番口コミで大切にされるのは、「落ち着いた学校」であるかどうかです。児童数が少なくてもざわついている学校はたくさんあります。一方、学年4クラス、5クラスでも落ち着いた学校もあります。校長のリーダーシップのもと、教職員が一団となって、規律ある学校生活を子供たちに教え、日々、しっかりと授業をすることができれば、おおかたの場合、学校は落ち着いてきます。1クラスだけ落ち着いていても、全体ではあまり変わりません。学校としての取組が大切になります。管理職の考え方も大事ですが、皆さんが生活指導担当になった場合、教員の先生方からのアイデアや取組も学校を変えていく大きな力となります。
徹底した挨拶指導、時間厳守を行う
着任して、まず取り組んだことは、職員の朝の打ち合わせをやめて夕会にしました。朝登校した子供たちを教員は教室で迎え、子供たちの朝自習には必ず教師が立ち会うようにしました。先生の目がないと子供がふざけてしまう実態があったのです。休み時間も含め、常に教員が子供を見守る体制をつくりました。
次に徹底した挨拶指導を行いました。朝の挨拶当番をつくり、毎朝元気な声で挨拶すること、廊下で教員や来客とすれ違った際に必ず「こんにちは」の挨拶をすること、この徹底を行いました。外国人が気軽に「Hello!」というような感覚で「こんにちは」の声かけをしました。これは予想以上に大きな成果がありました。
そして、時間を子供も教員もしっかり守ることを徹底しました。休み時間が終了したらすぐに次の授業の用意をする、教員も授業や帰りの会をだらだらやらない、限られた時間の中でしっかりと指導することを心がけました。
子供同士のトラブルが起きたときは、教員が必ず複数で対応し、情報収集、保護者対応を行いました。「やったらやり返す」のような風潮があったので、相手を許すこと、やってよいことと悪いことを、場面ごとにしっかり指導していきました。
全校朝会のミニ授業で学力向上を目指す
生活指導と学力向上は車の両輪です。まず落ち着いた雰囲気の土台ができたら、学力を向上させ、子供たちに自信を付けさせたいと切に思いました。
私は社会科が専門でしたので、毎週月曜日の全校朝会はミニ授業を行いました。大きなビニール製の全国の白地図を用意し、朝礼のときに朝礼台の上に掲げ、「今日は、秋田県について学習します」と秋田県の位置を覚えさせ、特色などについて図解をした後、秋田県出身の先生が秋田の方言で話をしてくれ、方言当てクイズをします。
このようなことを繰り返し行っていくと、都道府県名を覚えるのが苦手な子供たちもだんだんと県名や特色を覚えていきます。学力テストに向けて似たような形式で学校独自の問題ドリルを作成しました。塾に通っている子供たちも少なく、問題用紙と解答用紙の扱い方がよく分からない実態がありました。なんでも練習です。練習を重ねていけば、だんだんコツも分かってきます。
何よりも去年よりよい結果が出れば、子供も保護者も喜び、子供は自信が付きます。何かイベントを実施した後に感想を書かせると、はじめは面倒くさがっていた子供も徐々に書けるようになりました。校内で落ち着いた態度が取れるようになると、区の連合行事や校外学習などでもきちんとした態度で参加できるようになります。そして、ほめられるとさらにがんばろうという思いになります。

