部活動改革や校務分掌の再編で教員の負担を軽減【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #04】
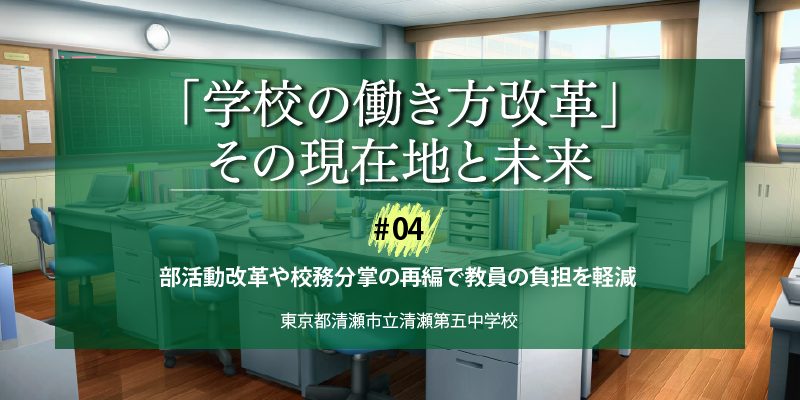
清瀬市立清瀬第五中学校(生徒数290名)は、2022年度、清瀬市教育委員会の校務改善推進モデル校として、1年間校務改善に取り組んだ。部活動や校務分掌の改革などを中心とした取組は高く評価され、東京都教育委員会から令和4年度校務改善表彰も受けた。2018年から同校に赴任し、働き方改革においてもリーダーシップをとってきた堀内雅之校長に、取組の内容と成果について聞いた。

東京都清瀬市立清瀬第五中学校
清瀬第五中学校の堀内雅之校長。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の4回目です。記事一覧はこちら
目次
部活動は複数顧問や外部人材で対応
埼玉県との県境にあり、のどかな畑と住宅街に囲まれた清瀬第五中学校。ただ、周辺環境から想像される有閑な雰囲気とは異なり、教員の過剰勤務は古くから同校でも課題となっていた。2021年度の時間外在校時間の平均は46.9時間、教職員のうち3分の1以上が45時間を超えていた。堀内校長は、2022年度の清瀬市教育委員会の校務改善推進モデル校として、時間外在校時間を40時間以下、1か月あたり5日以上休日出勤している教職員をゼロにすることを暫定的な目標とし、動き出すことにした。特に、長時間勤務の大きな原因になっている部活動に関しては、重点的に改善を進めたかったという。
「他校でもそうかもしれませんが、本校には勤務時間が長い教員が多かった。その大きな要因になっているのが部活動です。土日曜に大会があれば、一日中拘束されることになってしまいます。通常の勤務日に振替で休めればいいのですが、難しいケースも多く、時間外の勤務時間が40、60、80時間……といった具合に増えてしまっていました。部活動をなんとかしなければという思いは強かったです」
清瀬第五中学校では、現在スポーツ系の部活動が6(男子バスケットボール、女子バスケットボール、サッカー、バドミントン、硬式テニス、水泳)、文科系の部活動が4(吹奏楽、ハンドメイド、イラスト美術、パソコン)ある。昔はもっとたくさんの部があり、活動も盛んだった。特に野球部とサッカー部は、どちらも東京都大会で優勝した実績を持つほどの強豪だったという。ただ、野球部は顧問の離任に伴い廃部、サッカー部は現在も存続しているが、3年生を含めて18名で、近隣校との合同チームを作らなければ試合ができない状態になってしまうという。
一方で、生徒や保護者から新しい部活動をつくってほしいという要望が出ることもあるが、生徒数の減少やこれ以上の教員の負担増加を防ぐため、10年ほど前から部の数は制限し、新規にはつくらないという方針を続けている。
「生徒数が300名弱なので、10というクラブの総数は適正だと考えています。ただ、現在ある部に関しては、1つの部に対して2名または3名の顧問をつける、また予算が許す限り、部活動指導員や外部指導員をつけるようにし、教員の負担を軽減するとともに顧問が離任した場合でもクラブが存続できるようにしました」
こうした取組は、顧問業務の負担軽減につながっているという。日常の練習や週末の試合の帯同を交代制にでき、教員が苦手な分野の部活動に割り当てられた場合も、指導部分は指導員に任せればいいためだ。現在、教育委員会が任命する部活動指導員が男女バスケットボール、バドミントン、硬式テニス部に、校長が任命する外部指導員が水泳と吹奏楽部にそれぞれ各1名配置され、技術的な部分の指導を行っている。ただ、指導員に関しては、どちらも部活動に帯同している時間のみ謝金が支払われる仕組みのため、この仕事だけで生計を立てることは事実上不可能だ。なり手は地域の愛好家や現役引退した高齢者などに限られ、常に人材不足に悩まされているという。
総合型地域スポーツクラブも設立
部活動とは別に総合型地域スポーツクラブ「きよすぽサークル」も立ち上げた。こちらも堀内校長が赴任直後から動き出した。
「以前、練馬区立三原台中学校でバレーボール部の顧問をしていたのですが、彼らの一部はもっと長い時間プレーしたいということで、部活後や部活のない日に、総合型地域スポーツクラブであるSSC谷原アルファのバレーボール教室に参加していました。同じ仕組みを本校でも作れないかということで、SSCの代表の方に協力を依頼し、将来的な地域移行も視野に入れて、清瀬市教育委員会の生涯学習スポーツ課とともに2020年、『きよすぽサークル』を立ち上げました」
現在の種目はバドミントンのみ。毎月2回、子どもから大人までが、同校の体育館に集まり、市バドミントン連盟の講師による指導のもと汗を流している。将来的に、スポーツをしたい生徒すべてをこのクラブに移行できれば、教職員の負担は大きく減り、生徒も専門の指導員から適切な技術を学べるWIN-WINの関係が構築できるはず。しかし、実際は「参加者が多すぎて、プレー時間が少ない」「月2000円、1回に換算すると2時間で1000円の参加費用が高い」などの理由から、同校生徒の入会は現在まで実現していないという。
「野球などを真剣にやりたい生徒は、近隣にプロを目指せるようなチームがあり、そこに通っています。ただ、スポーツを純粋に楽しみとしてやりたいという子にとっては、総合型地域スポーツクラブはよい受け皿になれるはず。バスケットボールやテニスなどの競技を追加できないか、現在構想しています。将来的には、地域移行や地域連携部活動など地域総合型クラブへの移行が必要だと思います」
現役生徒の参加はゼロ(近隣中学校からの参加者はいる)とはいえ、すでにバドミントンで仕組みはできているため、場所や費用などの工夫次第で移行が進む可能性はある。今後の動きに注目したい。

