学年で歩調を合わせることを求める、ベテラン先生への働きかけは? 後編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#16】

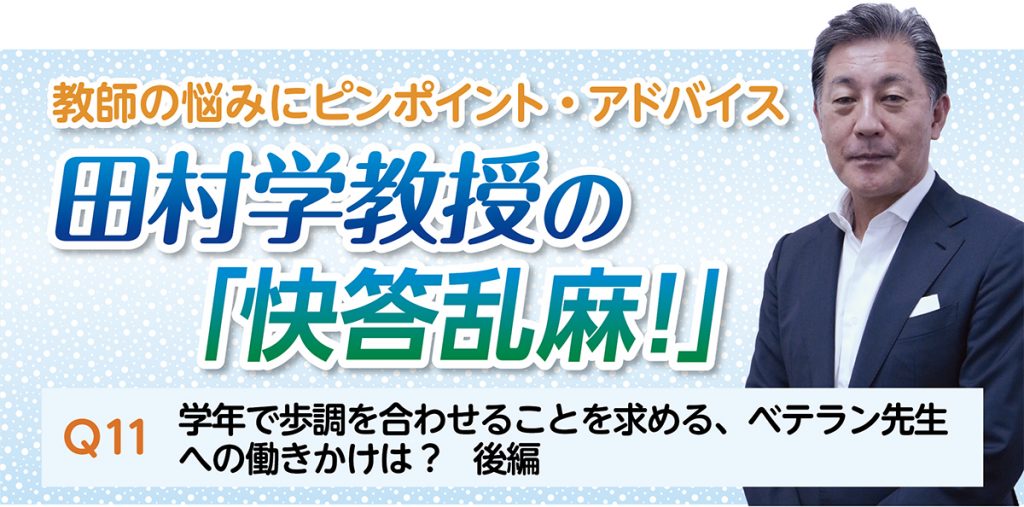
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、先輩の先生との考え方の違いを感じている先生に対し、世代間の価値観や教育観のギャップを越えていくための、具体的な方法を説明していただきます。
Q11 経験を重ね、自分のやりたい学級経営や方針が見えてきましたが、中学校ということもあり、ベテランの先生に学年で歩調を合わせるよう求められます。めざす子供の姿を共有しないまま、指導内容や方法を同一に(それも旧来型に)揃えることを求められるので、より苦しさがあります。学年の中心になっている先生方にどのように働きかければよいのでしょうか。(中学校、30代)
目次
子供の姿を中心に置くことで、世代による価値観や教育観のズレを埋める
A 前回、「世代による価値観や教育観のズレや溝を埋めるための方法は何だと思いますか?」という問いを、先生方に投げてみました。その問いに対して考えられた方法の一つ一つは、それぞれの先生方が置かれた環境における問題解決のための方法の一つなのだと思います。ただ、どんな環境においても学校という職場、教師という仕事を選んだ先生方に共通する一つの解決方法があるのではないかと私は思っています。それは子供の姿を中心に置くということです。
今回、質問をされた先生もベテランの先生方も、子供たちがより良く育ってくれたり、今までになかったような表情を見せてくれたり、想像もしないような発言をしてくれたり…つまり資質・能力が育ってくれれば、納得できるし、「いいね」ということになると思うのです。もちろん、教師として「ああしたい」「こうしたい」という思いもあるとは思いますが、自分の授業や自分のクラスの中で、中学校の生徒一人一人が確かに成長し、確実な変容を実現できることが、多くの先生方を納得させる近道ではないかと思います。
特に教科研究がベースになる中学校のことですから、それぞれ専門教科の授業の中での工夫は自由にできるはずです。ですから、その授業を通し、「生徒がこんなに積極的に発言するのか」とか、「こんなに活発にディスカッションができるのか」とか、「授業をふり返って、こんなに論理的かつ長い文章を書くのか」とか、「多数の生徒が『先生の授業は楽しいよ』と言うのか」などといったことを実現し、その子供たちの姿を他の先生方に見ていただく場をつくっていけばよいのだと思います。そうすると、「なるほど、あの先生の考え方や教材研究や単元構成の仕方、授業の進め方はとても今の子供たちにフィットしていて、子供たちが伸び伸びと力を発揮しているな」という、他の先生方のコンセンサスを得ることにつながるのではないでしょうか。これが、教師という職業を選んだ人を納得させるために、最も力強い方法だと思います。
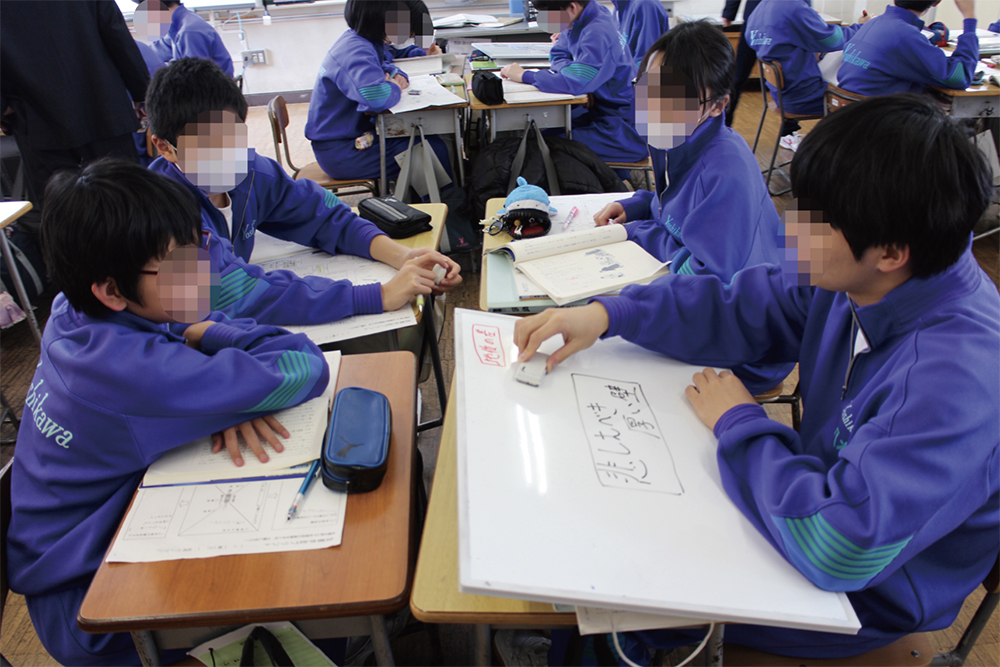
おそらく、どんなに「国の資料にはこう書かれています」と説明をしても、「あの有名な研究者がこう言っています」と説明をしても、経験や考え方の異なる先生を簡単に納得させることはできないでしょう。しかし、「あの学年の生徒がこんなに授業中に本気になっているのか」とか、「あの生徒たちがこんなに力を付けてきているのか」と、子供たちの姿を見せるほうが説得力が高いのだと思います。
ご自身のやりたいことが見えてきて、旧来型以外の多様なアプローチが見えているということですから、おそらく、そんな授業力や単元デザイン力をもち始めているのでしょう。ですから、そこに力を傾注することが結果的には全体を変えていくことにつながると思います。いきなり全体に働きかけて変えようとすると難しいのですが、全体は部分の集合体であり、部分の中に全体が凝縮されているわけですから、その部分である自分が受けもつ1時間の授業を、より良くしていこうとするエネルギーが全体を変えていくのではないかと思います。
学年部と教科部があり、それが縦横に編み込まれているのが中学校の組織ですから、「学年部で統一しよう」ということも一定程度あるとは思いますが、同時に教科ごとにそれぞれの先生が自身の固有性を発揮しながら授業づくりをしているところもあるでしょう。それが理科なら理科という個別の教科内だけでなく、数学や国語など教科を超えて広がっていくと、学校のパワーを高めることになると思います。例えば、「グループディスカッションを入れていこう。そのときにはICTを入れよう」ということになっていくと、1人が取り組むよりも、教科全体でやったほうが良いし、個別の教科だけでなく教科を超えて行ったほうが、子供の変容という意味でも効果が大きいでしょう。そのように子供を真ん中に置いて、効果、成果を通して語り、共有することだ大事だと思います。


