各教科等の学びはその根幹がつながっていることを意識する【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第11回】
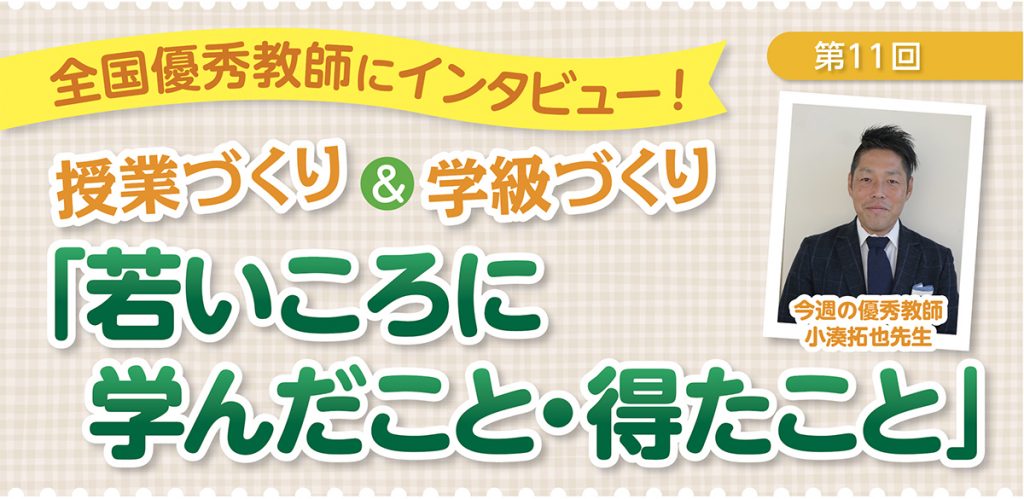
全国の優秀な先生は、若手の頃から何をどのように学んで身に付けてきたのかを紹介するこの企画。今回は、兵庫県神戸市の授業マイスター(小学校・理科)である同市立小学校の小湊拓也教諭が、若手時代に理科に力を入れつつも、多様な教科の授業づくりを学んでいった経緯を紹介していきます。

目次
学びが子供たちの生活とつながるようにする、理科の授業づくり
前回お話ししたように、初年度には自ら指導主事の先生にお願いをして週2回指導を受けることで、授業づくりの根幹について学んでいきましたが、2年目からは専門教科に選んだ理科についても力を入れていきました。
市の理科研究会には初年度から入ってはいたのですが、1年目は初任者研修などで忙しく、ほとんど参加できずにいました。そこで、2年目から本格的に参加し始めたのですが、最初は専門的な話にあまりついていけず、「どうしようか」と思っていたくらいです。しかし、参加しながら他の先生方の話をしっかり聞いていくうちに、少しずつ分かるようになっていきましたし、「研究会でこれを学ぼう」というよりも、「何でもどんどんチャレンジして経験を積んでいくしかない」と思っていました。そこで、研究会内で担当になった領域のグループ(研究会内は理科の領域ごとに分かれている)で、どんな仕事があっても率先して受けるようにしていました。それは例えば、研究授業を行うとか、授業を紙面にまとめて発表するといったことで、とにかくどんどん取り組みました。
ちなみに、私が教員に採用された年度は採用者があまりいない年で、同年代で理科研究会に入る人も少なかったのです。そのため若手の頃から、他教科が専門の先生向けに実験講習会の講師をするようなお仕事を任せてもらう機会も多くいただきました。実際に講師の立場で話をするためには、その単元の学習のポイントは何か、その単元の中でその実験はどういう位置付けにあるのかといったことを一生懸命勉強しますから、間接的に自分の理科の授業づくりに生きてきたと思います。
そうした授業公開の機会は理科研究会だけでなく、校内研修でもありますから、自ら手を挙げてどんどん授業を行い、毎年、最低でも年1回、多い年には3回くらい授業公開をしてきました。そうやって積極的に授業を公開しようと思ったのは、一つには身内に教職者がいなかったことや、採用される前にも違う仕事をしていたということ、さらに1年目に苦労したことなどがあって、何とかしないといけないという思いが強かったからです。
研究授業を率先して始めた当初は本当につたない授業でしたが、授業自体はうまくいかなくても、産みの苦しみの過程で苦労したことによって学べることもたくさんありますし、それなりの達成感はありました。もちろん、授業前後に他の先生方からいただく多種多様なアドバイスを通して学べることがたくさんあるわけです。そうやって積極的に授業公開をする上で力になったのは、新任当初から教えていただいていた指導主事の先生の言葉です。「授業で失敗することはよくあることです。それが一般企業で、取り返しのつかないような金銭的(あるいは信用的)な影響がある場合は別かもしれないけれども、授業は1回2回失敗したとしても、その後、必ず取り返すことができます」とおっしゃってくださったのですが、それは大きな心の支えになりました。
そうした授業公開を繰り返しながら学んできたことで、特に理科の授業づくりを行うときに意識しているのは、学びが子供たちの生活とつながるようにすることです。例えば、生活上経験していることや、経験しているけれども気付いていなかったことを入り口(導入)にして学習を始めると、「これを学ぶことが自分に必要なんだ」「それを学ぶと便利なんだ」と思い、主体的に学びに向かうことができます。また、その思いをもって学習を進めていくと、学習後も学んだことを生活に生かしていこう、つなげていこうと意識することができます。そういう学びをつくっていくことが大事だと思うのです。

実は以前、理科の研修で、「研修には多様な方法がある」ということを教えていただいたときに、そうした方法の一つとして、単元の導入部分だけを考える研修を受けたことがありました。そのとき、一つの単元の導入で、「こんな導入も、こんな導入も、さらにこんな導入もある」と教えていただいたのですが、そのように導入を工夫しながら、目の前の子供たちが、自らめざす学びに向かっていけるようにすることが大事だなと強く感じたのです。
ちなみに現任校は一昨年度、小学校理科の全国大会を行った学校で、生活を入り口にして理科の学習に入り、理科の学習での予想や実験や考察というステップがあり、再び生活に戻るという単元づくりをしてきています。そうした学びをデザインしていくときには、当然、めざす資質・能力を育むための学習過程を丹念に設計していくのですが、子供たちがいざ問題解決を始め、対話を通して「こんなふうに解決していこう」と決定し、解決していく過程では、あまり教師が手を出さずに任せていけるほうがよいと感じます。そう考えれば考えるほど、やはり子供たちがめざす学びを進めていけるような、導入(事象との出合い)を考えていくことが重要だと思います。もちろん、その前提として、子供たちが問題解決のステップを踏むことを身に付けた上での話ではあるのですが。

