GIGAスクール構想の現在地と教育DXに向けた取組【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント #04】
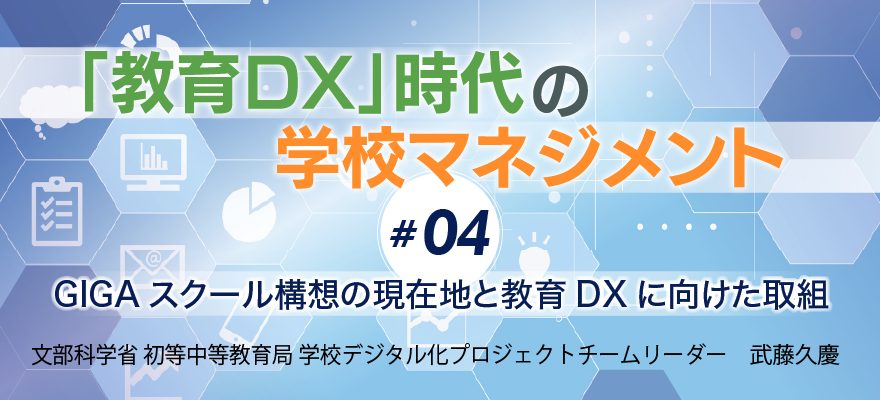
GIGAスクール構想の取組によって、1人1台端末の整備が急速に進み、従来の一斉授業による教育現場から大きく変化した。DXによる教育の変革について、文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチームリーダーである武藤久慶氏に語ってもらった。

文部科学省 初等中等教育局 学校デジタル化プロジェクトチームリーダー(併)修学支援・教材課長
武藤 久慶
2000年に文部省(現文部科学省)に入省。教育課程課や大臣官房総務課、在外研究(ハーバード大学教育大学院)などを経て、2010年に北海道教育委員会に出向。2014年教育制度改革室、2016年に外務省への出向、2019年に高等教育局企画官、2020年に大学入試改革実行プロジェクトチーム企画官、2021年に大臣官房総務課副長、2022年に初等中等教育局企画官などを経て、2022年6月から現職。2023年4月から修学支援・教材課長を兼務。
この記事は、連続企画「「教育DX」時代の学校マネジメント」の4回目です。記事一覧はこちら
目次
GIGAスクール構想の現況と成果
文部科学省(以下、文科省)は、2019年を「GIGAスクール元年」とし、教育現場に1人1台端末を整備する「GIGAスクール構想」に取り組んできました。ただ、実際に多くの自治体で端末が頻繁に利活用され変化が訪れたのは、2022年度からが多いと感じています。
特に大きく変わってきた点は、教員の働き方です。学習者用の端末と指導者用の端末には、様々なクラウドツールが搭載されています。例えば、各種アンケートなどはすべて電子的に実施することで準備から回収、取りまとめまで一瞬のうちに終わらせることが可能です。
また、職員会議もクラウド上で行い、共同編集の機能やホワイトボードソフトのデジタル付箋を活用すれば、管理職だけでなく職員全体で意見を出し合い、議論を深めて結論を得ることができます。分掌の意思決定などは、クラウド上の共同編集機能を使って、ペーパーレスかつ非同期で、それぞれの空き時間に修正したりコメントしたりすることも可能です。効率的な校務処理が可能になった分、今まで校務に割かれていた時間を子供たちの指導やその準備に充てられるようになったことは非常に大きいと思います。
GIGAによって実現された複線的な授業展開
先行して取り組んでいる学校では、授業デザインも大きく転換されてきています。従来の一斉授業は、45分から50分の間、教員が教科書に基づいて子供たちに一方向に教え、すべての子供が同じ内容を同じペースで学んでいくという「単線型」の授業でした。しかし、ICTを活用することで自由進度学習のような考え方の「複線型」の授業や学習を展開している学校が徐々に出始めてきています。
「複線型」の授業は、教員の指導を受ける子もいれば、友達同士で学び合う子、あるいは個人で学習を進める子もいるといったように、同じ教室で複数の学びのスタイルが同時に展開される授業です。こうした学校では、子供たちが主体的に学べるよう本時や単元の構成、様々な教材や学習方法などがクラウド上で共有できるようになっています。

