日本の学校教育が抱える最大の課題【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #6】

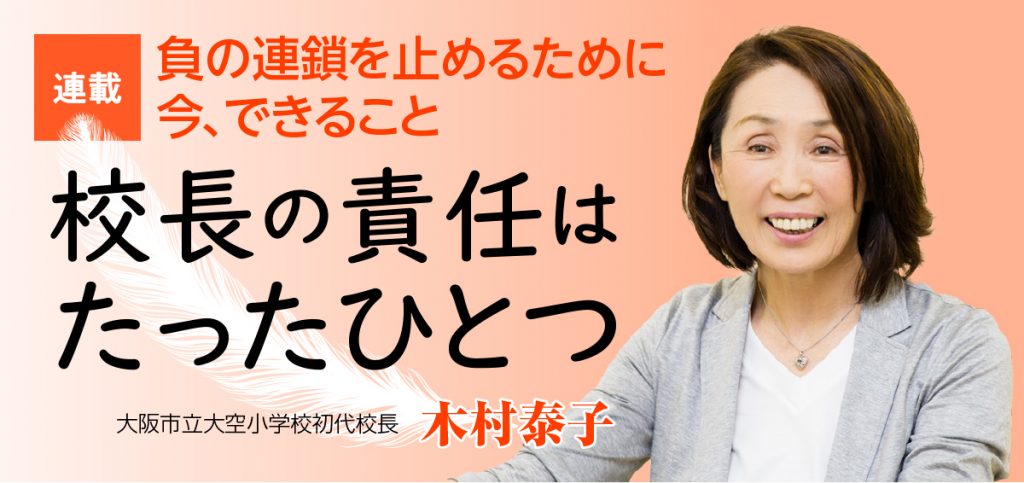
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第6回は、<日本の学校教育が抱える最大の課題>です。
12年間の学校教育の結果、日本の若者は…?
2019年に行われた18歳の若者の「国や社会に対する意識調査」の結果は、世界9か国の中で、日本の若者の現状に大きな差異が見られました。特に、「あなたは自分で国や社会を変えられると思うか」の質問には、「思う」と答えた若者が18.3%で、諸外国とはかけ離れた結果が出ました。18歳と言えば、義務教育9年間と高校教育の3年間を終えた若者の調査結果です。これは、12年間の日本の学校教育の結果だともいえるでしょう。この調査から明らかになったのは、子どもや生徒が自分事として自分から学校での学びを獲得していないと言うことです。つまり、日本の学校教育が抱える最大の課題は「当事者意識の欠如」だと言えるでしょう。
昨年、ある県の高校教員の初任者研修に行きました。そこで、初任者にこの質問をしたのです。「自分で日本社会を変えられると思う」に手をあげた人は残念ながらいませんでした。次に、「自分は変えられないと思う人?」と質問したのですが、そこでもみなさん困ったようにもじもじされていた印象があります。
この初任者の方々の事実を批判するのではなく、これまでの学校教育がそうさせてきたことに対して、謙虚に問い直しをする必要があると思っています。「イエス」か「ノー」かの質問には手をあげず、どちらでもない「△」に手を上げれば可もなく不可もなく安心だと言った学校の風土があるのです。つまり、自分の言葉で自分を表現することにチャレンジしてこなかった結果で、これこそ学びに対する当事者意識の欠如そのものだと思っています。
「パス」と言う権利
大空小では、問いに対して「イエス」か「ノー」、「△はなし」をすべての子どもと大人が合意していました。このことを初めて子どもたちと共有したとき、一人の子どもが「おれ、真ん中やからどうしたらいい?」とつぶやきました。そのとき、「もう一人の自分が今の自分をみて、1ミリでもイエスに近いかノーに近いか自分で決めたら」と話したのを覚えています。
ここで、すべての子どもが安心して自分を表現するために不可欠なのは「パス」の権利です。その時その時、それぞれの子どもも大人も、言いたくないときや言えないときがあるのがあたりまえです。そんな時は「パス」を選択します。パスは大事な権利であることをみんなで確かめ合ってからは、質問する側も応える側も安心して自分を表現できるようになりました。
教員の問いに対して望ましい答えを求められている空気の中では、自分の考えに真摯に向き合うチャンスを見失ってしまいます。子どもが自分の考えではなく、先生の持つ正解を見つけようとしてしまいます。

