正解のない課題を探究する「PBL」でさらなる学びの充実を【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画 #06】
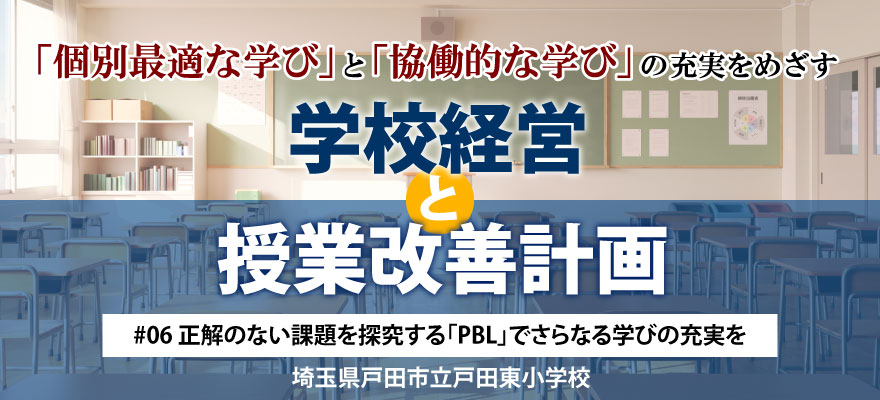
2019年度から「戸田型PBL(プロジェクト型学習)」に取り組み、子どもたちの課題解決力や探究心などを育んできた戸田市立戸田東小学校(児童数1,091人/2023年4月現在)。その内容と成果、取組について、研修主任の中山真美教諭、副主任の下山優茉教諭に伺った。
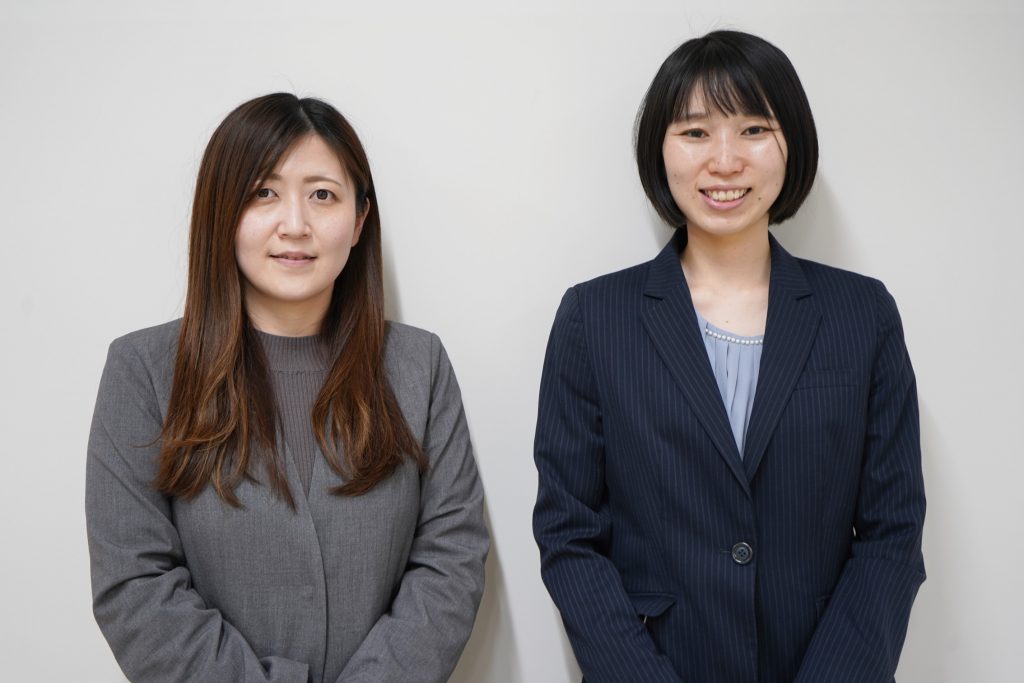
埼玉県戸田市立戸田東小学校
写真左から、下山優茉教諭(副主任)と中山真美教諭(研修主任)。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の6回目です。記事一覧はこちら
目次
特例校を活用してPBLの時間を充分に確保
埼玉県戸田市教育委員会では、主体的・対話的で深い学びの実現をめざして、2019年度から「戸田型PBL(プロジェクト型学習)」を推進。戸田東小学校でも4年前からこのPBLに取り組み、PBLの中で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実を図っている。
PBL(Project Based Learning)は「課題解決型学習」とも呼ばれ、学習者が自ら課題を見つけ解決していく中で、課題解決力や創造力、探究心など、様々な能力や資質を育てる学習手法。「こちらが一方的に教えるのではなく、子どもたちが自分から学びたいという意欲を持って仲間と協力しながらプロジェクトを解決していく、というものです」と研修主任の中山真美教諭は説明する。アクティブ・ラーニングの一つとして2000年代初頭に大学の研究者から注目され、今も全国の学校で盛んに導入が進んでいる。
戸田東小で行われているPBLは、1年生から6年生まで学年ごとにテーマを設定。そこから課題を見つけ、「情報収集→整理・分析→実験・制作・改善→まとめ・表現……」などをくり返しながら解決策を探る、という活動を年間で展開する。このPBLが行われる「しののめタイム」という同校独自の時間について中山教諭はこう説明する。
「『生活科』や『総合的な学習の時間』にあたるものです。本校は教育課程特例校に認定されており、学習指導要領の標準時数よりも多くの時数を設けているので、PBLで活動する時間が増えています」
「市民を幸せにする」ための6年生の取組
PBLの具体例を挙げると、6年生は「戸田市に幸せの花を咲かせよう」というテーマのもと「自分の困りごと」から始めて、その困りごとを解決し、よりよくするためにはどうすればいいかという課題を設定。
「『自分の課題を探究し、解決策として何か成果物をつくったり、提案をしたりする』というのを第一サイクルとしてやっています」(下山教諭)
続く第二サイクルでは、その経験をもとに「戸田市の皆がもっと幸せになるために、自分たちの力をどのように役立てることができるか」についてチームで取り組む。1チームは4~5人程度。クラスの枠を越えて、子どもたちは取り組みたい課題ごとに集まってチームをつくる。今回の6学年は50チームほどになったそうだ。
あるチームは、「習字に使った筆を洗うのは大変で、親も洗面台が汚れてしまって困っている。市内の他の親子も困っているだろう」と考え、「浸けておくだけで墨が落ちる方法はないか」という課題に取り組んだ。そして、墨を落とすにはどんな成分がいいのか考え、外部(実社会)の専門家にも話を聞きながら、実験と改善をくり返したという。

「最終的にできあがりまで達しないこともありますが、学年全体への活動報告会ではなく、聞き手の共感や協力を得られるようなプレゼンテ―ションをしていく流れでPBLに取り組んでいます」(下山教諭)
つまり、第一サイクルが「個別最適な学び」にあたり、それが第二サイクルの「協働的な学び」に活かされることになる。

