学校を取り巻く環境の変化とこれからの子どもに必要な学び方【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画#05】
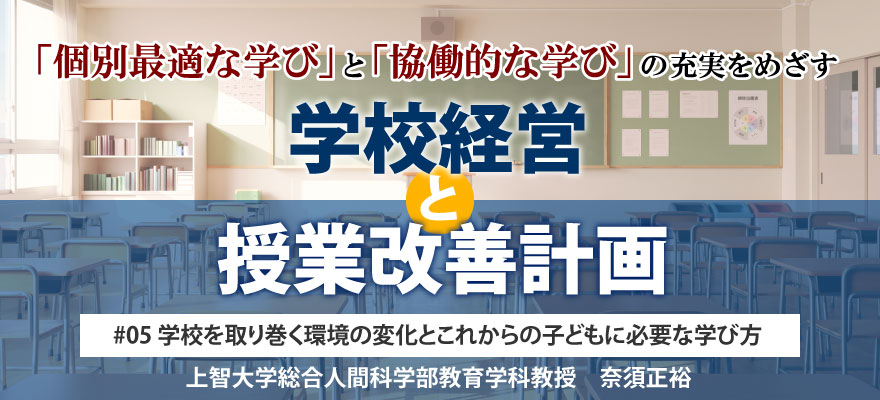
中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」で、その充実が求められた「個別最適な学び」と「協働的な学び」。この2つのテーマは、差異はあるものの過去の答申でも謳われた経緯がある。なぜ改めてこれらの充実が求められているのか。その意図と背景およびその具体的な充実プランと子どもたちが身につけるべき資質・能力について、中教審委員として答申の議論に関わった奈須正裕教授に伺った。

上智大学総合人間科学部教育学科教授
奈須正裕(なす・まさひろ)
1961年徳島県生まれ。徳島大学教育学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了。東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得退学。博士(教育学)。神奈川大学助教授、国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。専門は、教育方法学、教育心理学、カリキュラム論。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会委員。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の5回目です。記事一覧はこちら
目次
正解主義と同調圧力をやめなければ国際社会から取り残される
このたびの中教審答申で求められた「個別最適な学び」と「協働的な学び」は、何も目新しいテーマではありません。表現は違えど、遡ると昭和20年代からずっと言われてきたテーマです。昭和59年の中曽根臨教審でも出ましたし、平成元年の学習指導要領にも盛り込まれています。
それから30年ほどが経っていますが、いまだに強調されているのは実現できていないからです。これまで行われてきた日本型学校教育には、いい面もたくさんある。でもいくつか問題もあります。なかでも「正解主義」と「同調圧力」。この2つは早々に止めなければなりません。
「正解主義」は先生が正解を出すので、子どもは答えが出るのを待ってしまう。「同調圧力」は言い方を変えると「空気を読む」ということです。日本人の美徳とされますが、外国の人からすると日本人が信用できないという理由になる。私の勤務する大学には留学生が多いのですが、彼ら彼女らが異口同音に言うのは、日本は本当にいい国で、日本人はいい人たちだけど、最後の最後で信用できない。自分の意思で動いてる感じがしない。本音で関わってる感じがしないと。自分の意見を言うのではなく、周りの顔を見て、自分以外の正解を待っいてると思われているのです。
いま国際社会ではダイバーシティとインクルージョン、つまり多様性と包摂性がテーマとなっています。正解を待っているのではなく、自分で考え、同調圧力に屈せずに自分で判断して答えを出す「自立した学習者」を育てていく。そうしなければ日本は国際社会のなかで確実に取り残されてしまう。そういう危機感があります。
不登校、貧困、タレンティッド……。変化に対応しきれていない学校
加えて国内事情をみると、従来の伝統的学校制度では学ぶことが難しい子どもが増えてきている現状があります。1つは不登校です。不登校児童生徒の割合は小学校で1.3%、中学校で5%になりました(令和3年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)。それに加えて不登校気味の子どもや、特別な支援を要する子ども、さらに海外にルーツを持つ子ども、貧困で学ぶ環境が整っていない子どももいます。
また、これらとは違って、特定の領域に特異な才能を持つ子どもたちが1クラスに2~3%いると言われています。ギフテッドあるいはタレンティッドと呼ばれていますが、こうした子どもの中には発達障害を持っている子もおり、欧米は昔からこうした子どもたちに手厚かったのですが、日本は遅れていました。
他方で「学校がおかしい」という保護者も増えてきています。かつては学校や授業についていけないのは、「学校に合わない“うちの子がおかしい”」と考える保護者が多かったのですが、今は「この子には学校に居場所がない」と認識するようになった。そういった子どもの学びの場としてフリースクールや広域通信高校なども整備されてきたので、従来型の学校に通わなくても、子どもたちが自分に合ったスタイルで学んで大学に行くこともできるようになっています。
学校を取り巻く環境がこうした状況ですから、従来の学校制度のままでよいわけがありません。これだけ多様な子どもたちが増えている以上、その多様性に対応し、多様性を包摂していかなければ子どもたちが幸せになっていかない。そこに危機感を抱いて打ち出されたのが「個別最適な学び」と「協働的な学び」なのです。
「個別最適な学び」については、これまでも習熟度別・少人数指導といった形で取り組まれてきましたが、それが十分でなかったのは、一つ誤解があったためと考えています。これまでは、教師が子どもたち一人一人に指導を準備して「あてがう」ものと思われていた。つまり先生が思う個別指導が行われていて、子どもが自立して判断して学んでいなかったのです。

