Q1 良い教師になるために、日々の仕事のなかで何を優先すべきか?(後編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#2】

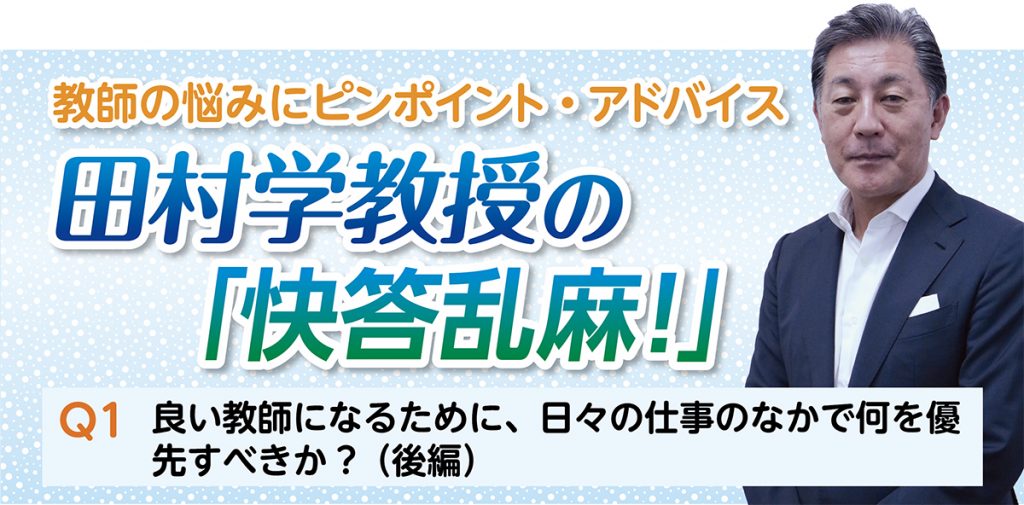
國學院大學の田村学教授に、先生方の疑問や悩みに答えていただくこの連載。今回は、子供理解の側面から、若い先生に取り組んでみてほしいことについてお話しいただきます。
※
Q1 「私は昨年、教師になったばかりなのですが、日々やるべきことが本当に多くて、何をやったらよいか指導の先生の指示を受け、それをこなしているばかりです。ただ、早く成長して良い教師になりたいと思うのですが、まず何から取り組めばよいのでしょうか?」(小学校・20代)
子供理解のために、1日の出来事を書き出していく
A 前回、まず若手の先生に取り組んでほしい2つのことのうち、1つめの授業の導入の工夫についてお話をしました。今回は、もう1つのことについてお話をしていきたいと思います。
そのもう1つとは、子供理解のための工夫をしていくことです。やはり、子供たちが共に学ぶ場であり、一日を過ごす生活の場である学級を子供たちと共につくっていくには、何よりも子供を理解することが重要です。ちなみにその子供理解は、前回お話しした授業づくりにも大きく関わるのですが、それについてもお話をしていきます。
さて、子供理解をしていくためには本当に多様な方法があると思います。例えば、「若いうちはできるだけ子供たちと一緒に遊びましょう」と言われるのもその1つです。それは、子供たちとより長い時間を共有することを通して、「子供たちは一日、こんなふうに生活しているんだ」とか、「子供たち一人一人にはこんな特徴があるのか」とか、「(大人である自分とは異なり)こんな考え方をしているのが子供なんだな」といったことを、よりよく理解するための方法の1つです。
私自身がそのような子供理解のために若手の頃にやっていたのは、放課後、座席表を記した紙に、その日にあったことを思い起こして書き出していくことでした。子供たちが帰った後、静かになった教室で、15~30分程度の時間、メモをしていくわけです。「1時間目にAさんがこんな発言をしていた」とか、「2時間目には日頃体育の苦手なBさんが跳び箱でこんな活躍した」とか、「昼休みにCさんとDさんが喧嘩をしてしまった」といったことを座席表に書き出していくのです。これを、ぜひ若い先生方にお勧めしたいと思います。
短時間ではあっても、このように書き出していくと、一日を意識的にふり返ることになるため、子供たちの様子がどうであったかを冷静に見直すことができます。それともう1つ大事なことは、このふり返りを毎日行い、積み重ねていくと偏りが出てくるので、自分が見えている子と見えていない子が分かってきます。端的に言ってしまえば、特徴的な子は毎日出てくる一方で、ほとんど書けない子供も出てくるということです。そういう偏りに気付いたら、日頃見えていなかった子供に対し、意図的に声をかけるとか、関わってみるといった工夫をしていくことができます。
当然、子供の記録が積み重なっていくわけですから、子供たち一人一人にどんな特徴があるのかということも客観的に見えてくるわけです。しかし、それ以上に私が大事だと思っていたことは、やはり先にお話ししたように自分の子供との関わりに偏りがあるとか、子供たちとどう接しているかといった、自分自身のありようを見直すことができることだと思います。
学校という場は、子供たち主体に動いていくものだと思います。そのため、他の職種とは異なり、なかなか自分自身の都合でスケジューリングすることが難しく、あれこれ受け身で対応しているうちに、あっという間に一日が過ぎ、気が付いたら夕方になっていたということが少なくないはずです。しかし仕事というのは、何から何まで他者から仕事内容を指定されると負担感が増加していきます。逆に自分でコントロールできていると、少々忙しくても負担感が少ないものです。
その意味でも、先のような方法を通して自分の行為を見つめて客観視し、自分でコントロールできるようになっていくことが大事だと思います。

