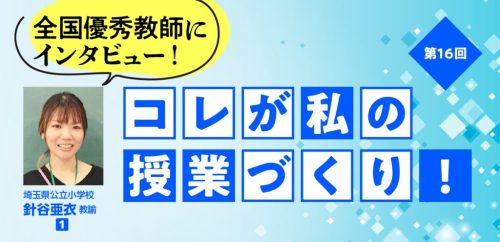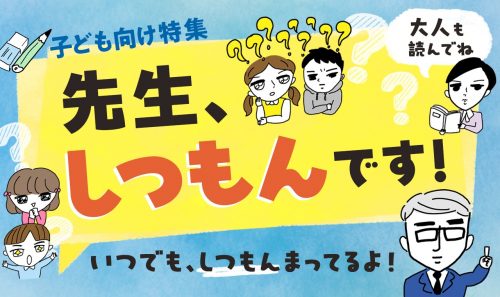子供から学ぶとは?【伸びる教師 伸びない教師 第27回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師
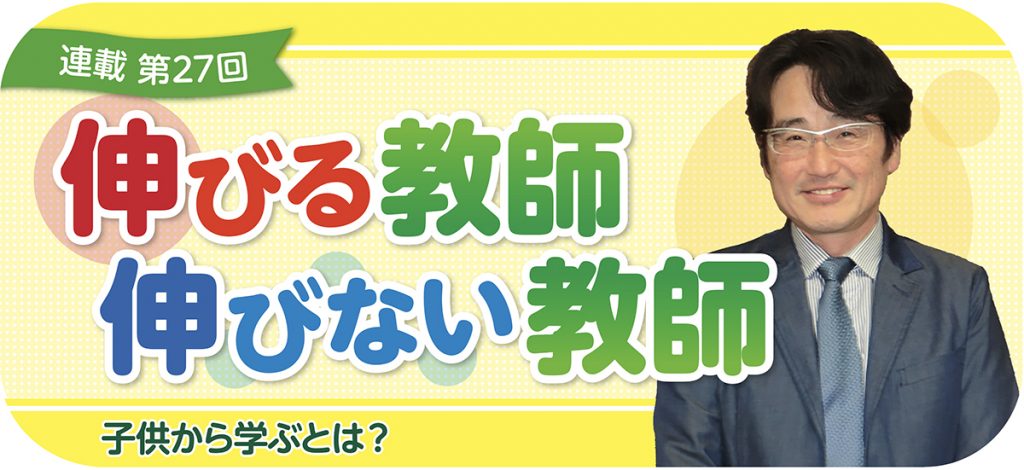
今回のテーマは、「子供から学ぶとは?」です。いつもおとなしいAさんが、あえて、けんかに巻き込まれ、ひとりになった女の子に寄り添った出来事を通して、子供から学ぶ大切さを実感したという話です。豊富な経験で培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県上三川町立明治小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を歴任。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
伸びる教師は、子供から学ぶ姿勢をもち続け、伸びない教師は、教えることに精いっぱいで子供から学ぶ視点をもたない。
目次
子供から学ぶって?
「教師は、子供から学ぶ姿勢が大切です」
初任者研修のときに指導主事から聞いた言葉です。
当時、教壇に立って間もない私には、この言葉の意味が分からず、「教師は教える側なのに子供から学ぶってどんなことだろう」と疑問に思っていました。
その頃の私は、子供を教えることに精いっぱいで子供から学ぶという視点はありませんでした。
それから数年経った頃、この言葉の意味が分かる出来事がありました。
Aさんに待望の親友
4年生を担任したときのことでした。
とても素直でまじめなAさんという女の子がいました。教室にごみが落ちていると、さりげなく拾ってごみ箱へ捨てる。そんな子でした。
でもちょっとおとなしくて自分から友達に「遊ぼう!」って気軽に声をかけられませんでした。周りの子も「Aちゃんは、まじめなんだよね」って思っているのか、誘いにくいようでした。
休み時間になると、Aさんは本を読んだり、校庭を歩いたり、みんなが遊んでいるのを眺めていたり、ひとりで時間をつぶしていました。
5年生になってついにAさんに友達ができました。ずっとあこがれていた「親友」です。
Aさんと同じタイプのおとなしい女の子です。
どこに行くにもいっしょでした。おそろいのノートを買ったり、休みに遊ぶ約束をしたり、毎日がとても楽しそうでした。
「ひとりになったら助けてあげよう」と思っていた
あるとき、同じ学級の活発な女の子たちがけんかを始めました。
4人組のグループでしたが、3人対ひとりに分かれました。
ほかの女の子たちは、そのけんかに巻き込まれないよう遠目に見ていました。
グループの中でひとりになってしまった女の子は、休み時間ひとりぼっちで窓の外を眺めていました。そんな女の子に、Aさんと親友が話しかけました。
そして、けんかは3人対3人に……。
Aさんは自分からけんかの輪に入るような子ではなかったので、正直、意外でした。
高学年の女の子に多い、「にらむ」「かげで悪口を言う」「嫌みを言う」、そんなことが繰り返されました。Aさんは自分から相手を攻撃するようなことはできないので、いつもやられてばかりでした。それでも、Aさんは、その子から離れようとしません。
あるとき、Aさんに聞きました。
「ねえ、どうして、わざわざけんかに入ったの?」
Aさんは急にぼろぼろ泣き出しました。
「あの子がひとりぼっちになったら助けてあげようと思っていたの。私が4年生のとき、ひとりでいたら『いっしょに遊ぼう!』って声をかけてくれたの、あの子だけだったから……」
「つらくないの。にらまれたり悪口言われたり……」
「つらい……」
Aさんはそういうと泣き崩れました。

Aさんの姿勢に女の子たちが泣き出す
それから数日後、私はけんかをしていた6人の女の子を集め、話し合いの場をつくりました。
お互いに言い分があって、なかなか話が進みません。
私は、グループの中でひとりになってしまった女の子に言いました。
「どうして、Aさんがあなたといっしょにいてくれているか分かる? 自分からけんかするような子じゃないってこと知っているよね。4年生のとき、ひとりぼっちのAさんに『遊ぼう』って言ってくれたのあなただけだったんだって。そのとき、あなたがひとりになったら助けてあげるってずっと思っていたんだよ。でも、Aさん、今とってもつらいみたい……」
そのことを聞いた女の子は、「ごめん。ごめんね、Aちゃん……」と大粒の涙をこぼしました。Aさんたちも、そして、けんかをしていた全員がぼろぼろ泣き出しました。
その日の給食の時間、みんなの前で
「私たちのけんかでみんなに迷惑をかけてごめんなさい」
泣きながらあやまる6人の女の子の姿がありました。
ひとりの人間として
小学生の頃、自分が今回と似たような状況に立たされたとしてもAさんと同じ行動は取れなかったと思います。大人になった今、職員室でそのようなことが起きても同じです。
そんなAさんの行動にひとりの人間として心を動かされました。
「子供から学ぶ」という言葉には多くの意味が含まれています。
授業中、教師が考えもつかなかった意見を発言した子供から学ぶこともあります。逆に、子供の反応が悪く自分の指導方法を振り返ることもあります。
また、今回のように、ひとりの人間として心が動かされるような子供の行動に出合うこともあります。
人に教える立場の教師だからこそ、たとえ相手が子供であってもすばらしいことはすばらしいと、常に学ぶ姿勢をもち続けていきたいと思っています。
構成/浅原孝子 イラスト/いさやまようこ
※第16回以前は、『教育技術小五小六』に掲載されていました。