意欲的に書く子を育てる秘訣とは【小1国語 京女式書くことの指導】16
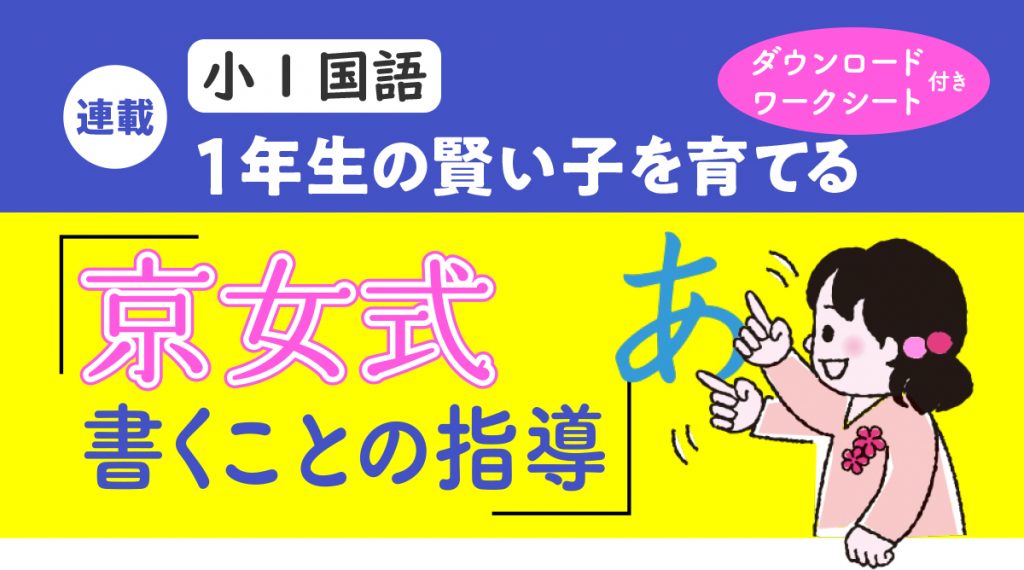
今回は、書くことの指導の総点検です。意欲的に書く子を育てるためにどのようにすればよいのかについての留意点を紹介します。単行本『はじめてのひらがな、カタカナ 1年生担任の京女式国語の教育技術』(小社)を再編集して、1年生の国語の指導ポイントをわかりやすく紹介するシリーズです。
執筆/京都女子大学附属小学校特命副校長・吉永幸司
目次
書くことの指導は考える力を育てる
1年生の書くことの始まりは「絵」をかくことです。何からかき始めるかということに注目して見守っていると、一番かきたいことがよくわかります。大きくかく、中心にかく、得意なことを言葉で伝えるなど、表現方法は多様です。その段階で、何をかいてもいいということを覚えていきます。
次は、文字にして表現することです。「絵をかくより文字のほうがいいな」と思えてくるようになります。そして、文字を使って文が書けるようになって、1年生の後期を迎えるのです。絵をかく段階と文字で表現する段階の違いは、文字で書くことは「考える」ことにつながっているということです。
考える要素として、何を書くか、何から書こうか、漢字にするかひらがなにするか、文字は間違っていないかなど、1文を書くにも、考える要素が多様にあります。
文が書けないという子を書ける子にするには
1年生にとって書くことは、次のような活動から成り立ちます。
●何を書こうかと考える。
●何をしたかを思い出す。
●書いた文を読み返す。
●句読点や間違った文字や漢字を見つけ、直す。
これらのことは、2年生以上の子には当たり前のことです。しかし、1年生には、どれも初めての経験です。それぞれが考える力の育成と結び付いているので、大事にしたいことばかりです。また、1年生にとって、書くことは、覚えたばかりの文字や漢字を使って表現する経験ができる、大切な学習の機会です。子供には、それは、宝物を手に入れたような喜びです。
このような大事な学習活動ですが、時間が経つと、「面倒だ」とか「書けない」と言って、嫌いになる子も出てきます。その原因は、語句や語彙を知らない、文字が思うように書けない、ということです。また、「詳しく書く」「わかりやすく書く」と条件を付けている教師の指示が、負担になることもあります。書くという新しい経験をするために鉛筆を持って机に向かっていることがすばらしいことだ、と思う気持ちが1年担任には必要です。
かつて、1年生を担任した時のことです。文章が書けないという子がいました。その子に、「昨日のことを思い出してみよう。何かお話が聞きたいな」と働きかけました。「ない」と言いましたが、しばらくして、「きのう、お兄ちゃんの誕生日」と答えました。「それで?」と聞き出すと、「ケーキを食べた」と答えました。さらに、「それで?」と続け、聞き出した通り書き写しました。しばらくすると、「自分で書く」と鉛筆を取り上げ、長い文を書きました。書くことのきっかけがあれば、書きたい気持ちがふくらんでくるという手応えを感じた出来事でした。
書けないのではないのです。書くことの指導に対しての丁寧さの有無が、書く活動につながるのです。

