読書指導のアイデア ③紙芝居・大型絵本

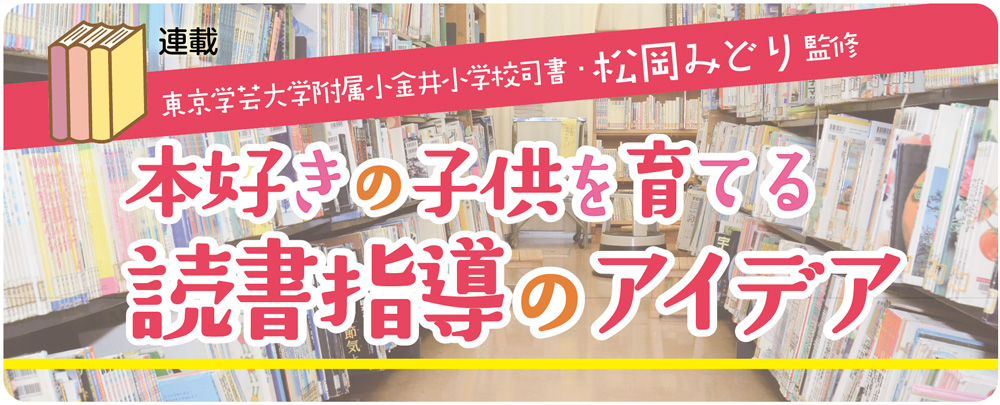
3回目のテーマは「紙芝居・大型絵本」。お楽しみ会を兼ねて「紙芝居」や「大型絵本」を楽しんでみませんか。子供たちはワクワクして、物語の世界に誘われていくことでしょう。読書離れが進みつつある現在だからこそ、子供たちが本を好きになるきっかけが必要となります。ここでは本好きの子供たちを育てるためのアイデアを紹介します。
監修/東京学芸大学附属小金井小学校司書・松岡みどり

目次
紙芝居でワクワク感を共有しよう
紙芝居は中学年、高学年でも楽しめる
紙芝居は1930年頃、日本で生まれた日本の文化です。紙芝居と言えば、小学校低学年のイメージがありますが、日本の昔話や防災を扱ったものなど、様々なテーマがあるうえ、すばらしい絵が展開されるので、中学年、高学年になってもおすすめです。紙芝居を読む人を「演じ手」と呼びます。演じ手と観客とが向かい合った空間に作品世界が広がっていきます。
紙芝居をエンターテインメントとして楽しむところから、本の世界へとつなげていきましょう。
紙芝居 準備~実践
1 紙芝居を選ぶ
紙芝居を選ぶところから始めます。紙芝居には「物語」「民話」「科学・知識」「生活・行事」「平和・環境」など、いろいろなジャンルがあります。また、物語で完結するもの、観客が参加するものなどもあります。
紙芝居を実際に手に取って、子供たちに何を伝えたいか、子供たちは何に興味をもつかなどによって選ぶとよいでしょう。季節や行事、そのときに学習しているテーマに合わせて選ぶのもおすすめです。
2 紙芝居を下読みする
演じる前には紙芝居の下読みをして、作品に描かれているテーマや内容を理解しておくと、落ち着いて演じることができます。
意外に忘れるのが、紙芝居のページの順番の確認です。本番で順番が違っていると、紙芝居が台無しになってしまいます。横に抜いて、スライドさせ、一番後ろに入れる手順も試しておくとよいでしょう。
可能なら舞台を使うことをおすすめします。舞台を使うことで、空間が仕切られ、作品への集中が高まるからです。舞台がある場合は、教壇に舞台を置くと子供たちがいすに座って見ることができます。観客が床に座る場合は、少し低いテーブルを用意し、教室の前半分くらいに子供たちを集めるとよいでしょう。舞台がない場合は、紙芝居をぐらつかないようにすることが大切です。

3 実践する
「紙芝居を始めるよ!」という言葉を聞いただけで、子供たちはもうワクワク。子供たちの期待感が高まったところで、紙芝居の世界へ誘います。今回は舞台がある場合を紹介します。舞台を開けるところから始めます。
演じ手は、舞台の脇に立って、子供たちに対面します。子供たちにしっかりと聞こえるような声のボリュームを心がけます。おおげさな演技は必要ありません。男性と女性、大人と子供など登場人物の違いで、少しだけ声のトーンを変えるとよいでしょう。例えば、登場人物が長老や大きいものなら声のトーンを低めでゆっくり、子供や小さいものなら若干高めで早いテンポにするのが秘訣です。
紙芝居は抜くことが重要な要素の1つになります。抜くとひと言で言っても、さっと抜く、ゆっくり抜く、ガタガタ抜く、途中で止めるなど、場面の様子によって変化を付けていきます。途中で止める場合は、抜くところまでの印を付けておくとやりやすいでしょう。紙芝居にはそのような印が付いているものも見かけられます。抜いた紙芝居は舞台の後ろに差し込みます。
紙芝居は演じ手からも子供たちの表情が見やすいので、反応をダイレクトに知ることができます。紙芝居の話が終わったら、少し余韻を残し、舞台を静かに閉じて終わりにします。
4 本につなげる
紙芝居はエンターテインメント性が高いので、みんなで物語を共有して「楽しかった!」で終わってもよいのですが、せっかく物語の世界に浸ったので、本につなげるようにしてはいかがでしょう。子供の楽しみがもっと広がっていくでしょう。
紙芝居が終わったら、「図書館に同じタイトルの本があるよ」とつなげたり、動物や昆虫の物語なら、「その動物や昆虫を調べに図書館に行こう」と言って、図書館に行くことを促したりするのもよいでしょう。
本を読むのが苦手な子の入り口が紙芝居で、紙芝居から本につながる場合もあります。子供が興味をもったときに、少し後押しするようにします。

