指導よりも空気(環境)をつくることが大切【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #2】

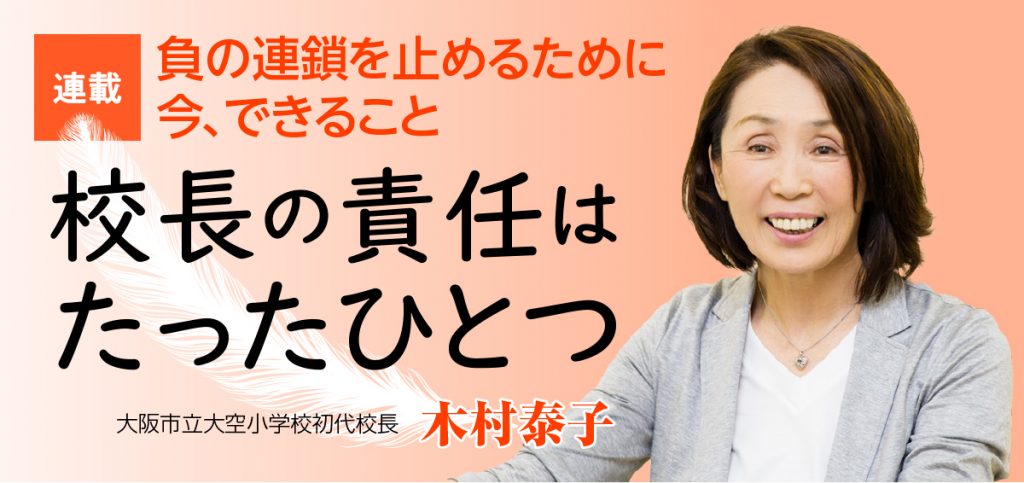
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第2回は、<指導よりも空気(環境)をつくることが大切>です。
「指導」は一瞬で「暴力」に変わります。一生懸命指導はするのですが、指導の結果を見ようとしない傾向があります。指導の結果、子どもの事実はどうであるかを見て、子どもが学びに向かう姿が見られたときに、初めて指導の成果が得られるのです。指導はするが、その後の子どもの事実を見ようとせず、指導に従わない子どものせいにしてしまう事実は、これまでにも数えきれないくらいあります。もちろん、教員は精一杯頑張っているのですが、頑張れば頑張るほど子どもは遠ざかっていき、保護者との信頼が途切れ、校長が教員を指導しても理解してくれないと反対に訴えられる。このようなケースが山のようにあるのが、今の学校現場ではないでしょうか。子どもも保護者も教員も管理職もみんながリスクを背負っている。だからといってどれだけ「働き方改革」を唱えても改善するどころか、ますますリスクを抱えてしまう。この負の連鎖を断ち切りませんか。
今の時代、従前のような教員の名人芸で子どもが育つ時代ではありません。多様な社会で生まれて多様な価値観の中で育てられた子どもが、義務教育をスタートするのです。どれだけ有能な教員を育てても、すべての子どもの学びを保障することなど不可能な時代に学校はあるのです。
「学校は子どもの命以上に守るものはない」を源に、これまでの当たり前は通用しない時代になっていることを全教職員で共有し、「新しい発想」で「システムをシンプルに」「チーム力を高める」手段を、日常的に雑談し対話し合える職員室の空気(環境)をつくり出しませんか。
学校に多様な空気(環境)を
学校に豊かな空気(環境)を生み出すことができれば、子どもは誰一人取り残すことなくその空気を吸いながら主体的に育ちます。大空小に転校してきた「不登校」のレッテルを貼られていた子どもたちは、画一的な正解ありきの学校の空気が吸えなくて行けなくなっていたのです。大空小に素晴らしい指導力を持った教員がいたから「不登校0」の奇跡の学校ではありません。教えられることが当たり前で、正解を常にゴールとして提示され、できないことができるようにならなければ評価されない、認めてもらえない学校の空気は一部の子どもしか安心して吸えないでしょう。
教員も同様ではないですか。あの先生のような指導力がないから自分はだめだ、努力してもあの先生のような指導力がないから仕事を続けていけない、結果として子どもや保護者や校長のせいにして自己肯定感を下げていくのではないでしょうか。この関係性の中に共通するのは、他者との比較による格差を持った評価です。まさに子ども同士の関係性も同じですね。もっと言えば、各校の校長同士の関係性も同様のことが言えるのではありませんか。

