リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #3 それっていいの?|中村優輝先生(奈良県公立小学校)
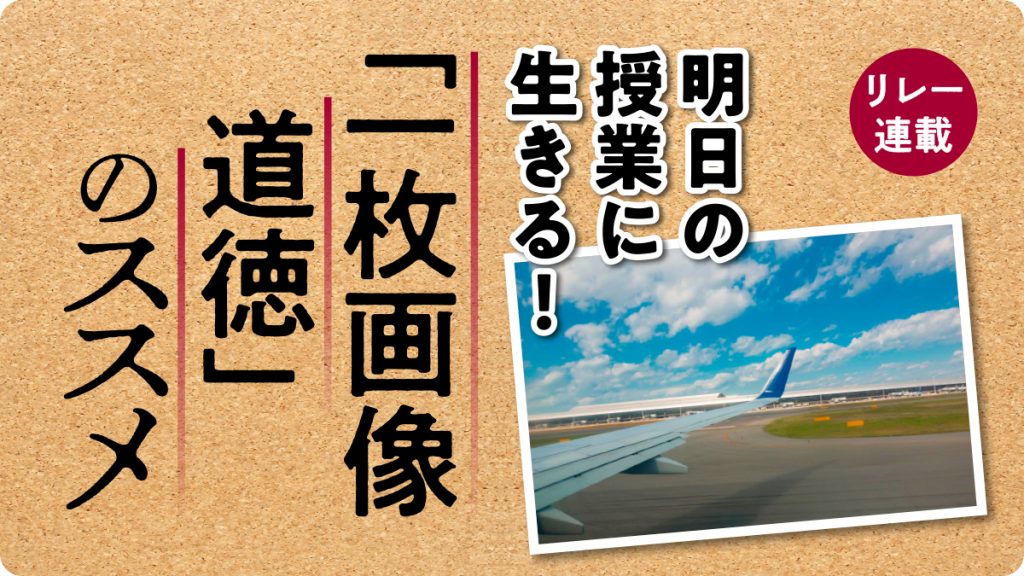
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促していく……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載です。第3回は中村優輝先生のご執筆でお届けします。
執筆/奈良県大和郡山市立平和小学校教諭・中村優輝
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
はじめに
「内容項目Dの視点、『主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること』は難しい」。こんな話を同僚から聞きました。
理由は、「命や自然が大切なことは、子供もわかっている」「教科書を読んでも、建前の答えしか出にくい」ことだと言います。
私は毎回、導入で写真やイラストを提示し、共に考えていきます。視覚的に訴えることで、本時の価値について考えることが容易になると考えるからです。 今回は、私の実際の授業の様子や児童の振り返りについてお伝えしたいと思います。
1 「一枚画像道徳」の実践
対象:小学4年
主題名:私たちの生活と自然
内容項目:D-19 自然愛護
自然のすばらしさや不思議さを感じ取り、自然や動植物を大切にすること。
以下の写真を提示します。

発問1 この写真を見て思ったことを教えてください
●飛行機だ。
●すごいいい天気。
●乗りたいな。
●空港だ。
●この人はどこに行くのかな。
●旅行に行くのかな。
「そうですね。この写真からたくさんのことを想像することができましたね。じつはこの写真は、関西国際空港という場所で撮った写真です。よく関空と略して言いますね。知っていますか? 行ったことがありますか?」
身近にある場所をとり上げることで、興味をもつ児童が多いことが予想されます。まずは、写真を見て思ったことを自由に交流させます。
その際、飛行機に乗るのが怖いなど、ネガティブな感情ではなく、「楽しいなぁ」「ワクワクするなぁ」というポジティブな感情を中心にとり上げ、クラスで共有します。
説明
ここで、次のように説明していきます。
「関西国際空港は、旅行や仕事などでたくさんの方が利用されることから、便利だと感じる人もいるでしょう。ところで、関西国際空港ってどこにあるか知っていますか?」。児童は、すぐに「大阪」と答えてくれました。
「そうです。じつは大阪の海の上にあります」と伝えると、児童は驚いた表情をしていました。
「もちろん海の上にぷかぷかと浮いているのではなく、埋め立てと言って海に土や砂を入れて陸にしているのですよ」と伝え、発問2につなげます。
発問2 人間が住みやすくするために、自然を壊してもいいの?
子供たちは、以下のように答えました。
●仕方ないことだから、いいよ。
●絶対だめだよ。
●よくはないよ。でもどうしようもない。
●できるだけ自然を壊さないようにすればいい。
●破壊せずに住みやすくする方法があるはず。
自然は大切であるという考えについては、挙手により全員一致で賛成であることがわかりましたが、発問2に関しては意見が分かれました。
『自然を壊してもいいのか、悪いのか』という意味を含んだ発問ですが、けっして二項対立で考えさせたいわけではありません。
「先生、どちらでもないかな」「もっといい方法があるはず」「どちらかなんて選べないよ。だって、いいって言ったら自然を壊してもいいことになるし、だめって言ったら住みにくくなるもん」……というように、多様な考えを引き出し、それらを基にした活発な意見交流を促すことを見据えた発問です。
子供たちによる話合いの時間を取った後、以下のリンク内の動画を見せます。
アニメで解説!!「5分で分かる環境問題~みんなで守ろう地球の未来」 City Ota Channel/大田区チャンネル
動画視聴後、感想を交流し、
「今日のテーマは『自然を大切にするって何だろう?』でしたね。今から読むお話は、自然を壊してしまったこと、または自然を守る取組のどちらだろうね。考えながらお話を聞いてね」と伝え、教科書教材(日本文教出版)を使った授業展開へと続けていく。
教材『小さな草たちにはくしゅを』(日本文教出版)を範読する。
タイトルにもある『はくしゅ』に着目し、「どうして拍手をしたのかな?」と問うと、「自然がすごすぎるから」「踏みつけられても、立派に草が生えているから」と答えてくれました。
子供から出てきた、自然はすごい存在であるという考えは、まさしく内容項目のDの視点に沿ったものでした。
その後、「自然のすごいところはどこだろう?」の発問に対し、『自然が人間をいかしているのか、または人間が自然をいかしているのか』『人間と自然が共に生きていくことはできるのか』という二つの問いが子供からうまれました。
『自然を大切にするって何だろう?』という切り口から派生し、たくさんの考えが広がりました。

