「教職員定数の改善」とは?【知っておきたい教育用語】
子どもたち一人ひとりに対するきめ細やかな指導や教員の負担減につながると考えられている「教職員定数の改善」。その意味とメリットについて紹介します。
執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・加藤崇英
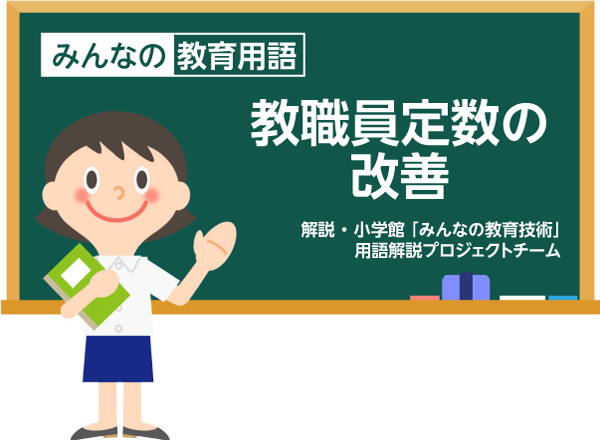
目次
「教職員定数」とは?
「教職員定数」という場合、特に断りがなければ、全国の公立小学校や公立中学校などに配置すべきとされる教員や校長、教頭、その他の職員などの総数を指します。
この総数は、法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」[以下、義務標準法])に従って、全国の公立小中学校等に配置される教職員の総数として算出される基礎定数と、政策目的に応じて措置される加配定数を合わせた総数になります。基礎定数と加配定数については、後述します。
では、これを「改善」するとは、どういうことでしょうか。これは端的には、教職員の総数を増やすことを指します。ここで最も期待される効果は、教員が増え、学級が増えることです。つまり、教員定数の改善により、1学級当たりの子どもの数を減らすことができ、よりきめ細かい授業や指導による教育効果が期待できるのです。
同時に、教員の負担を減らすことにもつながるといえます。よって、「40人学級」を「35人学級」にすることは「教職員定数の改善」(さらに基礎定数の改善)の代表的な例といえます。
法制度と財源
公立の学校とは、市町村や都道府県が設置する学校です。そして義務教育諸学校とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部が該当します(義務標準法第2条)。よって、義務教育諸学校の大部分は、市町村が設置する公立小中学校ということになります。
ここでいう教職員とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員、事務職員を指します(義務標準法第2条第3項)。このうち、もっとも多いのは教諭や講師になります。
よって、冒頭に述べたように、教職員定数の大部分は、公立小中学校の先生の数ということになります。ここでは算定方法の詳細は省きますが、それぞれの教職員の算定方法などは、先に挙げた義務標準法に定められています。そして国は、義務教育費国庫負担金という形で、この教職員定数に基づき算定された教職員の給与などの3分の1を負担しています。かつては2分の1の時代がありましたが、地方分権化が進み、負担割合が見直されました。
義務教育費国庫負担金は、およそ1兆5000億円になり、これは令和4年度文部科学省予算(一般会計)に占める割合でいえば、約28%になります。このように「教職員定数」は、国の教育財政に大きく関わる仕組みになっています。

