「心理的安全性」とは?【知っておきたい教育用語】
経営学などでも注目されている「心理的安全性」。その意味や仕組み、高めるための方法などについて理解することで、質の高い集団づくりに活かすことができるでしょう。
執筆/鳴門教育大学教職大学院教授・久我直人
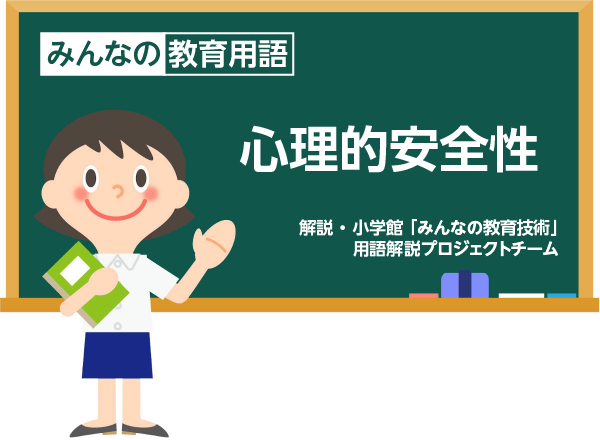
目次
「チームの生産性向上の最重要要素」
心理的安全性とは、エドモンドソン(1999)によれば、「チームにおいて、他のメンバーが、自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰をあたえるようなことをしないという確信を持っている状態であり、チームは対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義されています。
昨今、経営学の世界でこの概念が注目され、Googleの「プロジェクトアリストテレス」が、実証実験で「チームの生産性向上の最重要要素」と位置づけた概念です。
学級・学校における「心理的安全性」
現在、不登校の増加に歯止めがかからない状態が続いています。その要因の一つに学級等における対人ストレスが挙げられています。
また、子どもたちの資質・能力の向上のために、「主体的・対話的で深い学び」を日々の授業の中に組み込むことが求められています。しかし、筆者の数多くの学校訪問における課題として、「他者の目を気にして自分の思いを十分に語りきれていない子どもの実態」が散見されます。
この課題の原因として、個人が感じる集団への安心感、信頼感の醸成が不十分であることが指摘されます。個々の子どもが、集団からの同調圧力等から解放された「心理的安全性」の高い集団づくりが求められています。
逆に、学級・学校の「心理的安全性」の醸成が、不登校対策と主体的・対話的な学びの具現化を同時に実現する可能性のある教育的営みと言えます。

