「消費者教育」とは?【知っておきたい教育用語】
成年年齢が引き下げられたこともあり、消費者教育の重要性が高まっています。その目的や方法について理解しておくことが必要です。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
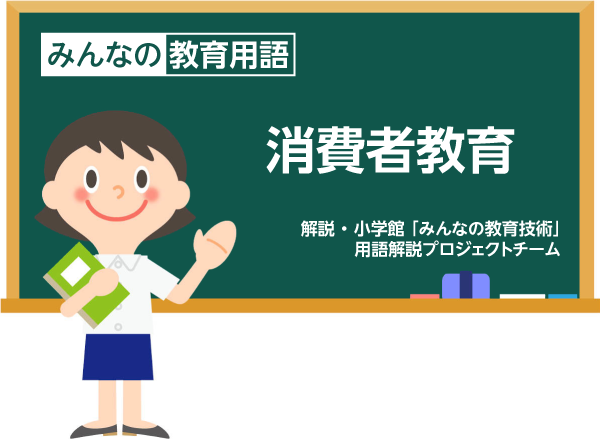
目次
消費者教育の定義
2012年、「消費者教育の推進に関する法律」が施行されました。この法律には消費者教育の定義が以下のように規定されています。
消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。)及びこれに準ずる啓発活動
消費者教育の推進に関する法律
消費者の自立支援と消費者市民社会の形成に参画のための資質育成が消費者教育の目的となっています。ここに示されている消費者市民社会については、消費者が社会の発展と改善に積極的に参加する社会であるとされています。
消費者教育の背景
消費者は商品を自由に選択する権利をもっています。その商品の品質や性能については生産者からの情報に依存せざるを得ない状況にあります。また、消費者の購買意欲は広告や宣伝に左右されがちです。こうしたことからアメリカでは1962年にケネディ大統領(1917〜63年)が消費者主権として、①知る権利、②選ぶ権利、③安全である権利、④意見を反映させる権利の「消費者の四つの権利」を提唱しました。
日本でも1960年代頃から商品の品質や安全性を消費者自らチェックするなどの消費者運動が発展してきました。現在ではクレジットカードやインターネット決済の普及、また、あとを絶たない悪徳商法などからより消費者の自立が求められる状況にあります。17の国際目標(持続可能な開発目標=SDGs)の12番目の目標にも「つくる責任、つかう責任」があげられました。
政府はこうした状況に対応するために製造物責任法(PL法、1994年)やクーリング・オフ制度を定めました。2004年には消費者基本法が制定され、2009年には消費者庁が設置されました。消費者基本法では「消費者の四つの権利」に、⑤消費者教育を受ける権利、⑥生活の基本ニーズが保障される権利、⑦救済を求める権利、⑧健康な環境を求める権利が加えられ、八つの権利となりました。
さらに2022年4月より成年年齢が引き下げられ、18歳以上であれば親の同意のない契約が可能になり同時にその責任も負うことになりました。こうしたことから消費者教育の重要性が様々な視点や立場から求められるようになったのです。

