「リフレクション」とは?【知っておきたい教育用語】
子どもの学びでも教師の学びでも、リフレクションの重要性が高まっています。有効な実践に向けて、その理論や方法について理解しておくことが必要です。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
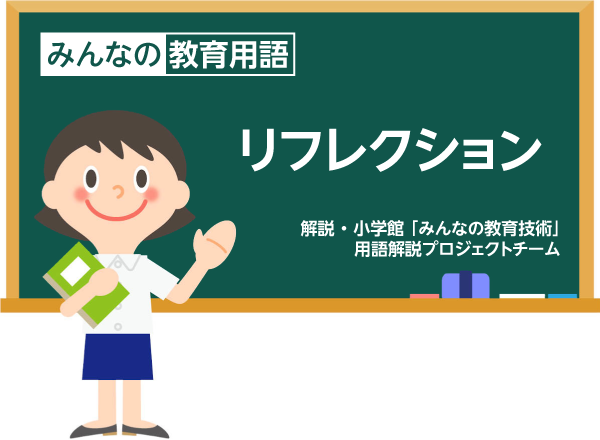
目次
学習の多様な機会で行われる「振り返り」
リフレクションは、日本語では「振り返り」と訳されます。「振り返り」は日常生活においてもさまざまな場面で行われていますが、学習指導の文脈で「振り返り」や「振り返り学習」が使われるようになったのは1990年代後半の「総合的な学習の時間」が登場してからです。2000年代になるとリフレクションと表現されるようにもなってきました。
その背景にはOECDの提言(2004年)でキー・コンピテンシーの中核としてリフレクティブネス(reflectiveness)が据えられたことや海外の諸文献からの引用として、リフレクションをそのまま用いるようになったことが考えられます。
こうした過程でリフレクションは主に体験的な学習において、体験を学びとして構築するための教育手法として定着してきました。現在では体験的な学習に留まらず、学習の多様な機会にリフレクションの機会が設けられています。
経験の連続性を担保する要となる理論
リフレクションは経験主義の文脈から登場したもので、理論的淵源はジョン・デューイ(Dewey, J.)の経験主義教育に求めることができます。デューイは経験の質を「連続性」と「相互作用」という二つの要素から言及していますが、このうち経験の「連続性」を担保する要となるのがリフレクションです。
「連続性」についてデューイは「経験がその後の経験にどのように影響を及ぼすか」が重要であり、そのためにはまず「自分の現在の経験から、自分が経験しているときの経験のなかにある自分のためになるすべてを獲得すること」として現在の経験から十分な意味を引き出すことの必要性を指摘しています。
デューイの経験論をリフレクションの方法を具体的な理論として構築したのがコルブ(Kolb, D.)です。コルブによれば、学習は動的なプロセスであり、以下の4つの局面を、検証を伴いながら連続していくものとされています。
Concrete Experience(具体的な経験)
↓
Reflective Observation(省察)
↓
Abstract Conceptualization(抽象概念化)
↓
Active Experimentation(能動的試行)
具体的な経験を振り返りによって概念化(意味の考察や今後の見通しの言語化)し、それを活用して次の経験をなすというサイクルをスパイラルに繰り返し発展させていくという理論です。
つまりリフレクションとは、学習者自身が学んでいることを意識化し、経験を解釈し、意味を構成する作業であるということができるのです。

