感覚過敏の子供を「虹色」と理解すると支援しやすい
低学年の不登校の大きな原因となっている「感覚過敏」。視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚など、多くの人が気付かないわずかな刺激が気になり、生きづらさを感じている子供たちのもつ「感覚過敏」の特色を解説し、学校生活をスムーズに送れるようにするための支援法を紹介します。
執筆/保健学博士・星山麻木
星山麻木●明星大学教育学部教育学科教授。一般社団法人 こども家族早期発達支援学会会長。行政や教育委員会と連携しながら、さまざまな地域の子育て支援、子育て支援ワークショップの開発、療育や特別支援教育の実践を行っている。著書に『星と虹色なこどもたち』(学苑社)『ちがうことは強いこと』(河出書房新社)。
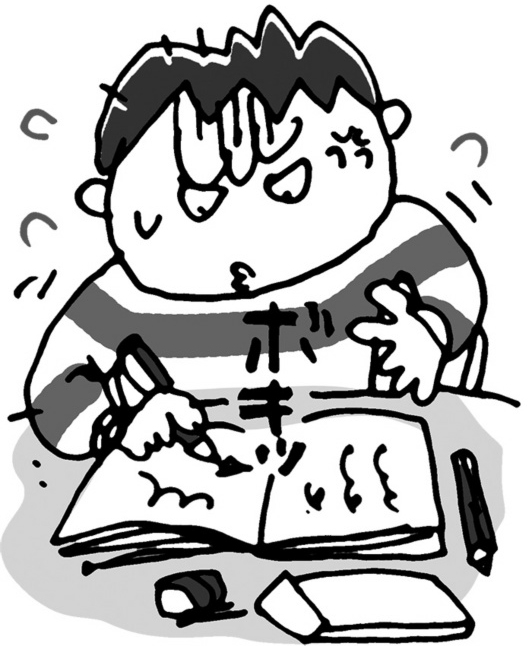
目次
「感覚過敏」「感覚鈍麻」とは
「感覚過敏」とは、感覚の特性であり、その子の脳の機能でもあります。
「感覚過敏」には、大きく分けると、感覚がとても過敏で生活に不便を感じる「感覚過敏」と、逆に感覚にとても鈍感で不便を感じる「感覚鈍麻」という特性があります。私は発達障害児の教育に携わって約40年になりますが、こうした感覚の特性のある子が、小学校の通常学級にも一定の割合で在籍し、最近は少しずつ増えてきていると感じています。
感覚過敏・感覚鈍麻には、
- 「まぶしくて目がチカチカする」
- 「字を書くのに時間がかかる」
- 「字の重なりが見分けられない」
- 「すぐに耳をふさぐ」「音でパニックになる」
- 「よく人とぶつかる」
- 「ガサガサした食感のものが食べられない」
- 「レモン石けんの匂いを嫌う」
など、さまざまな特徴がありますが、これらが「感覚の特性」であることがあまり知られていません。そのため支援が遅れ、当事者の子供はもちろん、先生や保護者など、周囲の人もとてもつらい状況になってしまう現状を見てきました。特に3歳から8歳までの子供は感覚の過敏性が強いため、ぜひ低学年の先生方には、この「感覚」における特性や対応法について学んでいただきたいと思っています。
この感覚過敏・感覚鈍麻は、脳の感覚刺激の処理の違いで起きるものです。
人間は聴覚や味覚、触覚、嗅覚など、いろいろな感覚器をもっています。これらに共通して言えることは、人と比べにくく、個人差が大きいものであるということです。
例えば、「空間の認知」とは視力だけで認知しているのではなく、形や色、奥行き、高低差など、目で受け取った映像を「脳」で認知しています。つまり、人間は目で見ているだけでなく、脳で見ているので、どのように感じるかは、その人の脳の刺激の受け取り方で違ってきます。
そして、感覚過敏は、まわりからは気付かれにくく、その人にとって不快な環境があったり、生活しにくい状況があったりしても、周囲の人に理解してもらえないため、努力や我慢が足りないと誤解されやすいのです。
「感覚過敏」の特性を理解することで問題行動の要因を知る
以前より、専門家の間では発達障害のある人の中には、「感覚過敏」の特性をもち合わせている人が多いという理解がありましたが、学校の先生方のなかには、ご存じない方も多いと思うので、ぜひ知っていただきたいと思います。
なぜならこの感覚過敏は、個人の学習や生活、対人関係などに非常に関係があり、問題行動の背景に、感覚過敏からくる要因が隠れていることがあるからです。
「上履きが足を締め付けられるようで履けない」という感覚の子がいる場合、そういった感覚への理解がないと、「上履きをちゃんと履きなさい」と言って無理にがんばらせようとするでしょう。これは実はとても危険な状態なのです。不登校や問題行動といった「二次障害」を誘発してしまうことになりかねません。
また、繰り返し指導するなかで、がんばって履けるときもあるかもしれません。しかし、本人はとても不快に感じながら無理をしているのです。私は「感覚過敏」の子供にとって、「がんばれないとき」がやってくるのをたくさん見てきました。そしてがんばり続けたお子さん ほど、いわゆる心因反応が出てしまうのです。
後々、「なぜ自分はがんばれないんだろう」と 自己肯定感が下がってしまったり、どうにもならないときにパニックを起こして、他の人を傷付けたりというようなことが起こったりします。
こうした二次障害の予防のためにも、これは本人の努力不足ではなく、もともとの脳の機能であるという理解が進んでほしいと思っています。特性への共通理解が進めば、本人もまわりの人も、自分や誰かを責めることなく、協力して支援の方法を探すことができるはずです。

