授業動画から考える! 学習意欲を喚起するオンライン授業のワザ
コロナ下、全国の自治体で採用されている「授業動画配信」。周囲に友達がいる授業とは違い、子供の学習意欲を喚起するためにはさまざまな配慮を要します。神奈川県横浜市作成の「学習動画」を検証することで、授業における「学習意欲の喚起」について再考します。横浜市教育委員会・関口和弘室長、岸田薫主任指導主事にお話しいただきました。
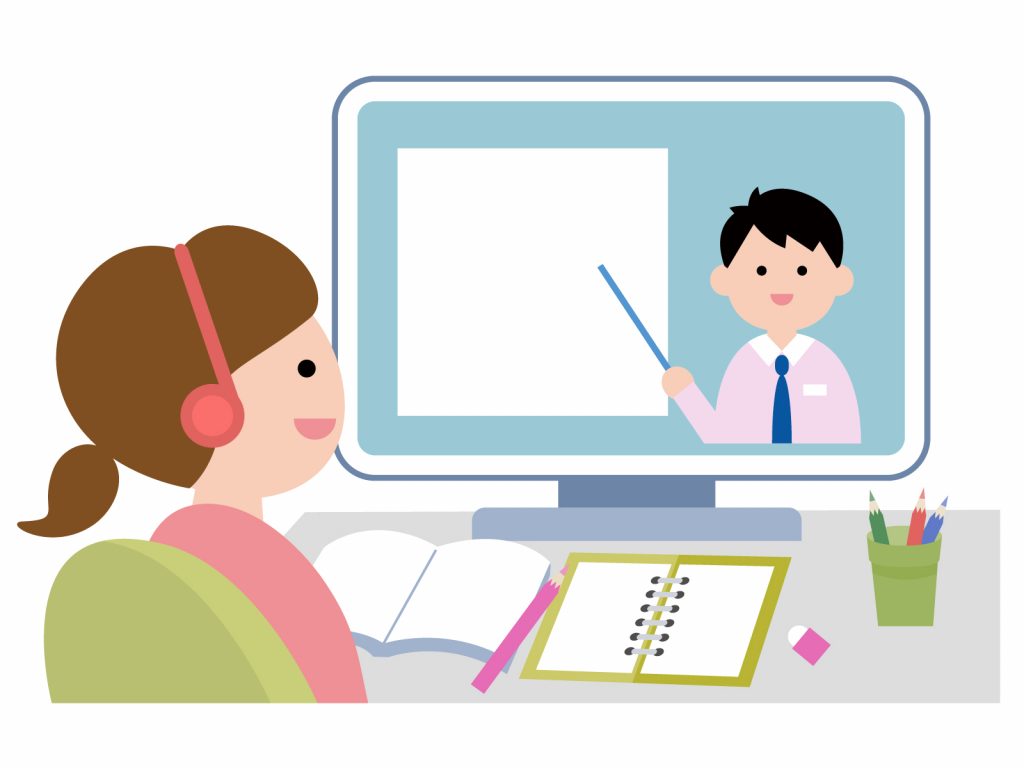
目次
単元で身に付けたい力など、ねらいを明確にすることが前提
今年度中のロイロノート・スクールのアカウントの全児童生徒配付に向け、動画教材の作成を進めている横浜市教育委員会学校教育企画部教育課程推進室の関口和弘室長は、まずオンライン教材について次のように説明します。
「既存のオンライン教材の中には一方的に先に進んでしまったりするものもありますが、本市で作成しているオンデマンド型教材は、前の場面に戻ったり、音声を繰り返し聞いたりでき、自分で考えたいところにしっかり時間を使うことができるのが魅力です。
しかも、画像や動画、音声、文字を併用しているため、子供たちの多様な認知特性にも対応できます。
教材は、例えば図工の場合、まず何を作るのか、ねらいを子供たちと共有するところからスタートします。そこで、必要な材料や道具、手順を分かりやすく画像や動画と音声で紹介し、それに沿って、各自が自分のペースで絵を描いたり、作品を作ったりします。各自の作品は写真に撮って送信すれば、教員がそれを評価できます。
学習結果の提出は、例えば、算数では式や表、図などを決まったスペースにかいて送信するとか、外国語ならば音読を録音して送信するなど、多様な方法で提出することが可能です。
評価する教員も、学校ならば一人ひとりの作品を各机を回って見て評価をメモしていくことが必要ですが、オンラインなら一斉に全員の作品を見て評価することができるなどのメリットがあったりもします」
教材のポイントについて、同教委の岸田薫主任指導主事(国語)はこう説明します。
「教材は、単元の時数に合わせて長短ありますが、めあてとふり返りを明確にしており、子供自身が学習のねらいを自分のものにしたうえで主体的に学習を進め、ふり返りも評価の3観点に沿って書くことを大事にしています。
学習に入る前には、生活経験や既習事項を出させ、より学習が実感を伴った深いものになるようにしています。
そのうえで配慮しているのは、例えば、『考えて書いてみよう』という学習活動をするとき、教科書通りのヒントを与えるだけに留めないことです。授業では子供と双方向のやりとりがあるわけですから、それをイメージし、子供が一人で学ぶときも、意欲を失わずに学べるような資料やヒントを用意しています。
ただしヒントが過剰だったり、解決する問題が簡単すぎたりすると、学ぶ意欲を失ってしまうので、例えば『100文字以内で書く』など、子供たちの実態を踏まえ、ハードルを上げたりしています」
まず教員が主体的に楽しく学ぶことが必要
このような、オンライン教材づくりから考えて、どのような点が、子供たちの学習意欲の喚起を行ううえで大切なのか、関口室長は次のように話します。
「本市では、昨春の一斉臨時休業の際には、10分程度の動画を作成しました。その作成に携わった指導主事や教員たちからは、『単元で身に付けたい力など、ねらいを明確にすることの重要性を再認識した』という声が聞かれました。
どんな形で授業を行うにせよ、まず身に付けたい力などのねらいを明確にし、そのねらいを子供たちと教員が共有して授業を始めることが、主体的に学びに向かい、対話を通し深く学ぶうえでの大前提となります。そのため、オンデマンド授業でも、最初に単元のねらいを示し、今、どこに向かおうとしているのか、児童と共有することを大事にしています。
しかもその前に、既習や既有の知識などを確認し、子供たちがより実感をもって問題解決に取り組んだり、学んだことをまた生活に生かしたりすることも、次の学びに向かう意欲となるため大事にしています。
また、単元の導入も非常に重要です。子供たちが、『なぜ?』と疑問を抱き、『知りたい』『考えたい』という思いをもてるような導入にすることが、問題解決に向かう意欲となります。
さらに、子供たちがねらいに沿って意欲をもって取り組めるよう、資料やヒントを出したり、問いかけたり、思考をゆさぶったりしていく教師の働きかけもとても大切です。加えて、学習後にふり返ることも、次の学びに向かう意欲を喚起するうえでとても重要です。
ただし、子供がめざす方向に向かって、主体的に学ぶような授業を行うためには、教師が本を読んだり、研修で学んだりすることを通し、多様な引き出しをもつことが必要です。それがないと、子供たちが自分の思うように考えなかったときに、強引に引っ張っていくような授業になってしまいかねません。
現在、横浜市では『授業づくり講座』を実施しており、教員が希望する教科等の講座を選んで学べるようにしています。そのような場は今は、オンライン講座なども含め多くあるので、それらを積極的に活用していくことも大切でしょう。
教員が自ら主体的に学ぼうとしている姿勢を、子供たちは敏感に感じていると思います。それを感じ取れると、子供の姿勢もより意欲的になっていきます。つまり、子供が主体的に楽しく学ぶためには、まず教員が主体的に楽しく学ぶことが必要だと思います」

